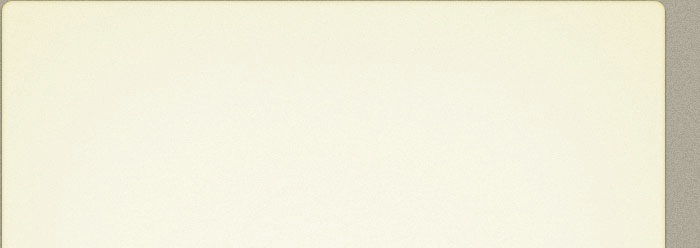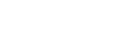日 時:2013年9月27日(金)19:00~21:50
場 所:国分寺市本多公民館
参加者:鷹取・鈴木ま・小川・五十嵐・阿久津・津田・町田・吉村・堀(記録)
生物サークルと合同でこの夏作成した「実践記録集」に、落丁などがあることが判明。手分けして確認作業をしたため、かなり遅れての開始でした。
1.夏の報告
(1)鷹取 健
未完成のものをみなさんが集まる前に見ていただいたが、自作ビデオ「関東地震」を制作中。多摩地区の震災記録が少なく、自ら調べる必要を感じている。小平については、小平市史に関東地震被害の調査記録を見つけた。日本地震学会などが主催する「関東地震90周年記念シンポジウム」に参加してきた。
『理科教室』編集部から「3.11以後の生物学教育」についての原稿を依頼され、現在苦労しながら執筆中。
(2)鈴木 まき子
サークルの岩手津波被災地フィールドワークに参加して、津波被害を防ぐ手立てについて考えていた。そんなとき『森の力 植物生態学者の理論と実践』(講談社現代新書)を読んで、がれきやヘドロを利用して盛り土をつくり、その地域の植生にあった常緑広葉樹を植えて森の防波堤にする“森の長城プロジェクト”を学んだ。
東日本大震災でなぜ松島の被害が他地域に比べて少なかったのか疑問だったが、長谷川修一(香川大学工学部)ほかによる論文で、巨大地滑りによって形成された(長谷川ほかの仮説)湾内に点在する島々が天然の防潮堤となったことを知った。
(3)町田 智朗
岩手大会では「作用反作用」の実践報告をしてきた。
阿久津さんから100円ショップで売っている「ぺちゃんこ水筒」を紹介された。阿久津さんは「口やボトルがしっかりしているし透明なので、ブタンの液化実験や、アルコールに熱湯をかける気化実験などに使えそう。町田さんなら何に使う?」と聞かれて、岩手大会の科学お楽しみ広場で手に入れた実験用器具を差し込んでみたらぴったりだった。
その器具は、気体を一方向にしか通さない弁がついている圧電素子。お楽しみ広場では風船を使っていたが、ぺちゃんこ水筒を使うと中もよく見える。ぺちゃんこ水筒に塩化コバルト紙(青)を入れてから部品を口に差し込み、水素20mLと酸素10mLの気体を入れ、圧電素子で発火するとボトル内で爆発、水筒内に細かい水滴が確認でき、塩化コバルト紙も赤くなった(と、実演しながらの報告)。
(4)五十嵐 伸江
傘と電線、ゲルマニウムダイオードを使って、傘ラジオを作った。傘を広げて電線を渦巻き状に貼っていって、傘を横にすると放送が聞こえた。
『目からウロコの中学校理科授業 ちょっとした工夫で授業が変わる』(坂井悦子著/明治図書)を参考に、教材づくりをしてみた。
(5)津田 弘毅
夏休みは初任研で明け暮れた。
アルミのカーテンレールにネオジム磁石を転がして、渦電流が発生していることを確かめる実験をした。
ティッシュと10円玉と1円玉で電池をつくった。
(6)阿久津 嘉孝
ぺちゃんこ水筒は官制研修で知った。研修自体はおもしろくなかったが、水筒は収穫。
子どもたちが双方向で議論するピュア・インストラクションの話を聞いた。「仮説実験授業は教材に縛られる(授業書通りに進める)。玉田さんの授業法はいいけれども、教員の力量が必要。ピュア・インストラクションは手軽で簡単にできる」とのこと。一理あり、最初にやる方法としては、いいのではないかと思った。
(7)小川 郁
8月末に毎年日大生物資源学部が開いているセミナーに、2度目の参加をした。富士山麓で土壌の見方、解析方法の実習や、鳥の観察、河川の水質検査などを体験した。
大会後、ドイツの環境対策で有名なフライブルグ市にあるソーラーハウスの市営住宅を見学したり、スイスのユングフラウの麓の町を散策して巨大なナメクジを見つけたりしてきた。
(8)吉村 成公
地震学会の見学会で栃木に行ってきた。地震計のデータはオープンになっていて、その引き出し方、加工の仕方を学んだが、加速度波形を積分して変位波形にするなど難しかった。地震の用語で「プレート境界型地震」とか「海溝型地震」とか「直下型地震」とかいろいろ出てくるが、「どのように区別しているのか」と聞いたら「気にしていない」とのことだった。
8月27日、「関東地震90周年記念シンポジウム」に参加した。避難する際に持ち出した荷物に火がつき、火災旋風が起きて3万8千人が犠牲になった陸軍本所被服廠(ひふくしょう)跡にできた江戸東京博物館が会場。大勢の人が亡くなった原因を聞くことができた。
(9)堀 雅敏
9月1日防災の日に、モンベル品川店で開かれたシンポジウム「防潮堤まつりin東京 東日本大震災と防潮堤計画 未来の海辺になにを残すか」(主催:公益財団法人 日本自然保護協会=NACS-J・NPO法人 森は海の恋人)を聞いてきた。くわしくは10月例会で報告することとなった。
2.プラン「平野部の津波災害=仙台市若林区=」…………………鷹取 健
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震。広大な仙台平野の沿岸部の地形と土地利用、地震による津波と地殻変動による被害、そこからの復興を、仙台市若林区を教材とした授業プランです。
新聞記事や貴重な図版など、ていねいに用意されての提案でした。「宮城野原平野(仙台平野の中の仙台市と名取市のあたりをこう呼ぶそうです)の浜堤分布図及び埋没谷基底等高線図」を見ると、七北田川や名取川の地下60mほどのところに基底を持つ谷が埋没していることがよくわかります。その上に沖積層が乗っているのですから、言ってみれば“天然の盛り土”です。地震の揺れには弱いでしょう。「国土地理院の、2万5千分の1の地形図と被災地の斜め写真は授業に使える」とのことです。
「仙台平野の地形と津波被災」「仙台平野の土地利用の変化」「若林区の復旧と復興事業」の3本の自作ビデオも用意されていました。今年5月に1回取材しただけですが、問題意識がしっかりあるためでしょう、的確な映像を切り取って撮影し、編集されていました。
吉村さんから「津波遡上高の方が津波浸水高(浸水深)より低いのはなぜか」との質問がありました。「おそらく仙台東部道路にぶつかり、生活道路と交差しているアンダーパスを抜けた海水が奥に進んだことや、より海抜の低い名取川方面から進んできたためだろう」とのことでした。
3.プラン「原子核と放射線」………………………………………町田 智朗
福島第一原発の事故を起こした国民として、また唯一の被爆国の国民として、科学的に判断できるように育ってほしいとの願いで、授業プランを考えてみたそうです。(何を大切にしなくてはいけないのか)を考え、「原子核の変化は、化学変化とは違う」ということを明確化したいと、これを到達目標として、全5時間の課題と授業の流れをつくってみたプランの提案です。
阿久津さんからは「5時間では難しい。核子の学習をここでするのではなくて、もっと前にする方がいい。それと、2時間目の課題の“原子”と“原子核”は、結局同じことではないのか」との意見がありました。小川さんも「『通常壊れる』との答えで終わり、になってしまうのではないか」との指摘がありました。町田さんとしては「少し考えさせたかった」とのことですが、小川さんからは「『どんな原子が壊れやすいですか』ではどうか」、との提案がありました。
また鷹取さんからは「“電荷”というのを既習事項として進めているが、中学校では出てこない。どこかで説明しないとわからない」と指摘がありました。これについて阿久津さんは「自分はその説明が難しいので“電荷”は使わず、“電気を持っている”としている」と紹介しました。
小川さんは「1時間目の磁石で斥力を説明する課題では、『磁石をひっくり返せばいい』という子が出てくる」と指摘、阿久津さんは「原子核の絵を見せてから、“なんだかおかしいと思わない?”と聞けばいいのでは」との意見でした。
10月例会で、再度検討することになりました。