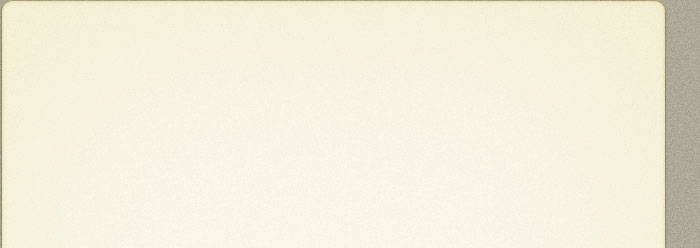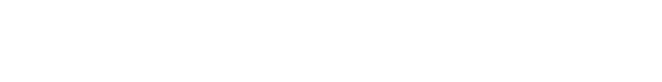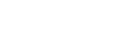-
日 時:2019年25日(金)19:00~21:45
-
場 所:国分寺市本多公民館
-
1.実験紹介「水の電気分解と水素の小さな爆発」
-
科学の祭典に出展する実験を、みなさんが集まるまでの時間に実演紹介していただきました。
-
医療用のピペットに、シャープペンシルの芯くらいに細い2本の短いステンレス棒(針金)を、手でプチッと差し込みます。そのピペットに硫酸ナトリウム水溶液を吸い上げて、いっぱいに満たします。
-
このステンレス棒に鰐口クリップのついた導線を介して手回し発電機をつなぎます。発電機のハンドルを回し続けると、泡が出てきます。水素と酸素の気体が発生しているそうです。手回し発電機では大変なので、9Vの乾電池につなぎ替えると、一気に泡が出て、やがて止まります。
-
水素と酸素がじゅうぶんにたまった状態で、爆発実験をします。水素:酸素が2:1だと大きな爆発になりますが、金属が溶けているために酸素は少なく、そこまでの爆発にはならないとのことです。
-
チャッカマンの圧電素子でもいいのですが、肆矢さんはナリカの圧電素子発火器を使っています。発火器と針金を導線でつなぎ、部屋を暗くしてピペット内に火花を発生させると、小さな音と同時に明るく発光するようすが確認できました。
-
「電極を針金ではなくシャープペンシルの芯にしてみてはどうか」などの意見も出ましたが、「一番いいのは白金」「高い!」とのことでした。
-
2.実践報告「地震と火山」
-
『学び合い高め合う 中学理科の授業 1学年2分野』(岩崎 敬道・鈴木 邦夫・山崎 慶太:編/大月書店)を参考に実践した報告でした。都立中高一貫校の附属中学校での実践なので、内容的には中学校+αということで、多少高校の内容を含んでいるとのことです。
-
発言記録と生徒のノートを元にしての報告でした。このレポートは4月21日の科教協東京支部・春の研究集会でも報告・検討され、その議論内容も紹介されました。以下、サークルでの話し合いです。
-
阿久津: スリンキーを使った実験で、P波の方がS波より速いことを示すことができるか?
-
手 塚: スリンキーを床に置くと床の摩擦でうまくいかないが、糸で釣れば見せられる。
-
※ ここで話された「スリンキー」は、(株)ウチダテクノの「コイルバネスリンキー」のこと。
-
掃 部: P波とS波の伝播速度の違いを示すことの意味は?地震波の伝播は地殻の物性によるから、一般論では言えない。海は縦波しか通さないし、宇宙空間では横波しか通さない。
-
阿久津: 固体に限って考えればいいのではないか。
-
掃 部: 縦波と横波の伝播速度とばね定数の関係は?土木で、物性の表はあるのか?
-
小 川:建築の構造力学ではあると思う。
-
堀 :どちらの波が先に到着するかは、実験的に見せてはどうか。NHKで大木聖子さんが実験していたのを見たことがある。
-
掃 部:縦波が速かった?
-
堀 :確か、そうだった。
-
※ 数年前の放送だったが、現在はシリーズ化されているようだ。下記サイトでも動画を見ることができる。「縦波・P波と横波・S波の発生から到着までの時間を別々にストップウォッチで計測し、縦波・P波の方が短いことを確認」「縦波・P波と横波・S波を同時に発生し、縦波・P波の方が先に到着することを確認」している。一般の学校でこのまま実験するにはちょっと大変かもしれない。
-
NHK「学ぼう防災 地球の声を聞こう」第3回<地震波が教えてくれること>
-
大木 聖子(おおき さとこ:慶應義塾大学環境情報学部准教授)
-
https://www.nhk.or.jp/sougou/bosai/?das_id=D0005180171_00000
-
掃 部:「海嶺でなぜ地震が起きるのか」という授業者の疑問だが、地震を伴う火山噴火と一緒。下からマグマが上がってきて岩が割れ、断層ができる。“マグマの上昇による火山性の地震”ということ。
-
鷹 取:火山噴火に関してだが、その事実と同時にデータが報道される。そうしたデータを示した方がいいのではないか。
-
手 塚:火山性地震の話は出てきていたが、資料を示すまではしなかった。
-
掃 部:海嶺が地上に現れているアイスランドの例を示すといいのではないか。
-
町 田:以前地学を教えたとき、NHKのビデオ「NHK地球大紀行 水の惑星・奇跡の旅立ち 引き裂かれる大地」を見せた。あのビデオはよくできていると思う。
-
鷹 取:昔の中学校では、どこで地震が起きたかを作図で考えさせていた。
-
手 塚:いま中学校ではやらないのではないか。
-
小 川:ちょっとはある。
-
手 塚:さらっとはあるが、今回はやらなかった。
-
鷹 取:「どのくらい深いところ?」「地表近く?」「かなり深いところ?」など、そんな話をすると、プレートが沈み込んでいくイメージがつかめるのではないか。
-
手 塚:深さについてのデータは、No.41「地震の種類」で考えさせている。
-
鷹 取:地震計で地球の構造を明らかにしてきた歴史があるが。
-
手 塚:No.44「地球の地震活動」でP波、S波が個体、液体、気体で違っていて、地球の内部構造解明につながっていることを説明した。ちょっと難しいのかな、という感じがした。
-
町 田:日本は地震がものすごく多い。大きな地震の世界地図だけでなく、日本周辺のも見せるといいのではないか。震源を示す赤で真っ赤になり、地図が見えなくなる(日本の形が分からなくなる)。
-
手 塚:なるほど。
-
3.“教育”論「エデュケートとティーチは違う」
-
遠山啓の『教師とは、学校とは』を読んで、(“教育”というのは、“する側”が主体なのではないか)(日本国憲法の“ひとしく教育を受ける権利”を憲法学者は“学習権”としているが、無理があるのではないか)という問題意識からの提案でした。
-
鷹 取:阿久津さんの憲法26条修正案にある“国”とは何か?
-
阿久津:国家権力かな。
-
鷹 取:国家権力は私たちがつくっているという理解をしたい。教育の内容 の一つの範疇が教科。科学に依拠して自然科学を教えることをやっている。
-
阿久津:“自然科学を教える”のではなく、“自然科学の概念を引き出す”と考えたい。
-
鷹 取:それが教育。
-
阿久津:それを区別したい。
-
小 川:“教育”という言葉の定義をどうするかということのようだ。阿久津さんのいうところの“教育”を“education”と読み替えればいいのかもしれない。1947年に文部省から出された学習指導要領試案の序論も変質しているという事実もある。
-
町 田:教育にこういう意味があるということをはっきりさせたい。
-
阿久津:言葉は大事にしたい。
-
小 川:それはそう。文科省も“主体的”とか“深い学び”などと言い始めている。
-
阿久津:“教育”というと、“洗脳”の面が強い。
-
掃 部:憲法26条修正案として出されている3点については、本当にその通りだと思う。では、我々はどうすればいいのだろうか。学校は教える意志を持つ集団だと思うが、生徒の要求を待つしかないのか。私は私立にいたが、「こういう教育方針でやりたい。賛同する人は来てください」という姿勢だった。
-
肆 矢:東大教育学部付属中等教育校は、教えない教育をやっている。極論すると教師の役割が違ってくる。いままで一方的に教え込むことをやっていたが、その反対。
-
手 塚:アメリカの映画で、探求型だけの授業をやっている学校を扱っているものがある。“人類の繁栄と衰退”についてだけ、長期間にわたって生徒が調べて発表するなど。
-
阿久津:いま二人の言われたことと、自分の考えていることは違うと思う。
-
小 川:修正案に“要求に応じて”とある。要求がなければ何もしないのか。
-
阿久津:遠山啓の言葉を参考にした。しかし言われるような意味では、この“要求に応じて”はなくしてシンプルにした方がいい。
-
4.書評「『理科教室』2019年5月号を読んで」
-
主に特集についてでした。「“酸化還元”は特集にするには難しいのだろうか。あまり内容的に関係ないものもあるように思った。」「殿村さんの論文は読みにくいと思ったら、最初の20行で句点が5個しかなかった。また、p.38の左段<そこが数々の>は<そこに数々の>だろうし、右段<有機物の>は<有機物が>だと思う。P.40左段でいくつか<等量>となっているが、<当量>ではないか。」「林さんの論文は酸化還元ではなくて、物質学習かな。物とは何かの部分が長く、酸の働きがあまり出てこない。」「金子さんの論文は、基本その通りだと思った。“原子の結びつきの強さ”というのは確かにその通りで大切。P.49右段の<銅粉と鉄粉>は<鉄粉とイオウ粉>ではないか。」「p.80のワイングラスの実験は楽しい、やってみたいとは思うが」とのことでした。
-
鷹 取:p.68~69で小川さんはいわゆる昆虫の話をしているが、ほかの動物も出したらどうか。
-
小 川:ダンゴムシは出している。ヒキガエルは出したかったが、原稿の時期に出てこなかった。