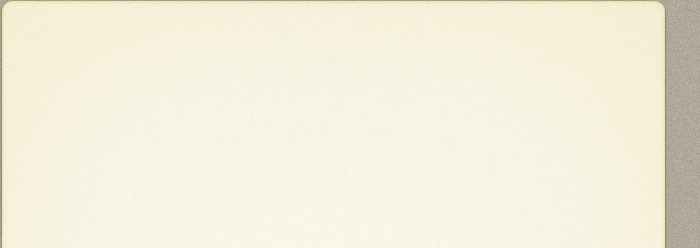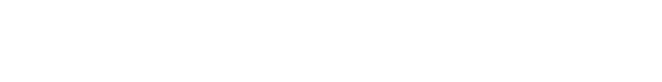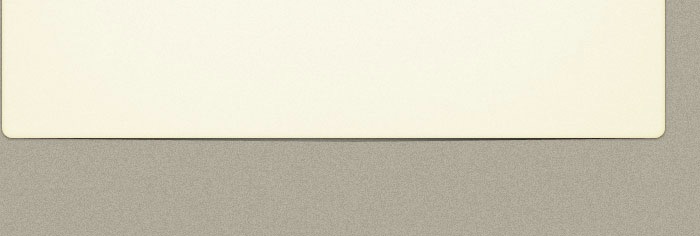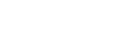-
日 時:2019年9月27日(金)19:00~21:45
-
場 所:国分寺市本多公民館
-
1.学習報告「夏に学んだこと」
-
01)
-
科教協福岡大会の物理分科会に参加した。印象に残った教材を2つほど。
-
・ 回転モーメントの話でふつうは輪軸を使うところ、100均の紙皿2枚を貼り合わせて1列に穴を開け、フックでおもりをぶら下げる教材は安価で作りやすいし、印象に残った。
-
〔参加者から〕「どうして円盤なのかな?」「釣り合いを示すのに“水平になっていなければならない”という思い込みをしている教師がいる」「昔の、ひもでぶら下げた棒を手に持ち、おもりを左右に動かす天秤棒の名残があるのではないか」
-
・ 台車を一定の力で引いてくれる、定力装置がおもしろかった。
-
〔参加者から〕「ワイヤーは装置から1mほど出ているだけだが、もっと長く巻き込まれているために、一定の力で引けるのではないか」「台車に輪ゴムをかけ、輪ゴムの長さを一定に保ちながら引っ張ることをやったことがある。どんどん速く走って引っ張らなければならなくなるので、大変だった。」
-
-
02)
-
・ 2年生が秩父の長瀞に修学旅行で行くので、1月から地学の授業をする。しおりをつくっているが、もっといい形のものにしたい。『理科教室』6月号の地学特集を読んで共感、科教協HPを見て町田さんに連絡し、このサークルへの参加を決めた。11月例会では「秩父長瀞修学旅行を見据えた授業プラン」を持ってくるので、検討してほしい。
-
-
03)
-
・ 科教協福岡大会の後、韓国へ行ってきた。30年前に行ったときと比べると、みんな親日でフレンドリーだった。太平洋戦争当時を知らない世代が増えていることも影響しているのかもしれない。
-
1980年5月 18日からの10日間に起きた、民主化闘争を進める学生・市民と、クーデターによって実権を掌握した全斗煥(チョン・ドファン)の戒厳軍との衝突(光州民主化運動)があった光州(クアンジュ)に行った。資料館や、収容所跡などを訪れた。日本語ガイドもいた。
-
-
04)
-
・ 家族の障害とつきあっている。病気で背が伸びない孫娘は、保育園の友だちや弟との関係の中で、手押し車で歩けるようになるとうれしそうにするなど、成長を自ら楽しんでいるようだ。
-
・ 玉川上水の開削工事のとき水が地下にしみこんだために流路を代えた水喰土(みずくらいど)公園を福生市は地震の避難所とするために遊歩道を広げる計画を提示、自然保護団体が反発している。
-
-
05)
-
・ 現役時代にお互いに交換留学をしていたハワイ・カウアイ島の元・高校教師が来日した。久しぶりに家族ぐるみで、横浜中華街で歓談した。
-
・ この夏は、量子力学を勉強した。いままで“なんとなく分からない”状態だったが、少しピントが合ってきた。いまは、“自信を持って分からない”。難しい。
-
-
05)
-
・ 科教協福岡大会には、このサークルの6月例会で検討してもらった「加速度」のレポートを持って行った。
-
・ 夏休みはそのほかに写真部の合宿や、宿泊防災訓練があった。
-
・ 文化祭では、担任しているクラスは生徒自身がモグラになる、大きなモグラたたきをやって、食品以外での1等賞になった。
-
・ 2022年から移行する新学習指導要領についての説明会に行ってきた。冊子が配られ、都教委からの説明があった。いくつか質問をしたが、「返答は後日」との返事で終了。未だ回答はない。
-
-
06)
-
・ 高3で、英語と科学のコラボを毎回やっている。アリの観察を英語で発表する授業をやった。生物教材は、なかなか大変。吸虫器でうまくアリを採れなかったので、掃除機で吸った。与えた砂糖水がよくなかったようで、つぎの日にはみんな死んでいた。掃除機も吸引力が強すぎると思ったので、透明ハンディークリーナーを使ったところうまくいって、無事授業ができた。
-
-
07)
-
・ 6月に、初任校の同僚が案内してくれるというので、福島県南相馬市まで行ってきた。3.11では、国道で津波が止まったので、同僚の家に津波の被害はなかったが、原発事故によりしばらく福島市に避難していた。
-
浪江町請戸地区まで行ったが、梅雨に入ったために福島第1原発の排気塔は見えなかった。海岸から500mほどにある請戸小学校がことし福島県初の震災遺構となったので行ってみた。まだ公開前ということなのか中には入れなかった。1階は津波にぶち抜かれ、給食室は当時のまま壊れた調理器具が積み重なって見えた。
-
例会では話しそびれたが、3.11当日、請戸小学校には給食後に帰宅した1年生を除く82人の児童がいた。児童・職員は地震の後すぐに津波を警戒し、学校から1.5km離れた大平山を目指して走った。途中背後に津波が迫ってきたが、40分後には全員避難できた。
-
その後、仙台市の震災遺構・荒浜小学校にも行った。トイレやエレベーターなども整備され、映像も公開されていた。請戸小学校の震災遺構への取り組みの中で、この荒浜小学校も視察に訪れているようだ。
-
-
08)
-
・ 科教協福岡大会後、帰りの飛行機を待つ時間を利用して、九州大学の演習林へ行ってみた。3.11の震災後の状況を見ると、海岸林の復活もなかなか大変そうだ。
-
海岸線には針葉樹がずっと連なっており、元寇に備えた防塁も残っている。日常的には防風・防砂林として、いざというときは攻められないように使われ、教材になるのではないかとビデオを撮ってきて編集した。
-
《ビデオ「北九州の海岸林」視聴》
-
林学を勉強するための演習林だが、植樹した樹木に囲いがないなど、手間がかけられていないように感じた。
-
2.書評「『理科教室』2019年9月号を読んで」
-
特集「授業に位置づけた本質的な実験」中心の感想でした。
-
まず特集名について、「“授業に位置づけない実験”というのはあまりあり得ないのではないか。〔授業のねらいに迫ることができる実験を!〕こそ特集名にふさわしいのではないか」との問題提起がありました。
-
これについて阿久津さんから「講義は講義、実験は実験でやっている人がいるからではないか」との指摘が出されました。
-
町田さんは続けて、丸山哲也さんの食塩が水に溶けるようすを顕微鏡で見る実験とか、小沢啓さんの力学台車をゴムひもで引っ張る実験など、興味を引かれ、いいと思う実験の感想を述べました。その一方、丸山さんの記事の中で「漏斗台」(漢字)と「ロート」(カタカナ)が混在していること、宮内主斗さんの記事中の写真に番号やキャプションをつけてほしいなどの注文も話しました。
-
町田さんからは、「岩間さんはサークルの実験紹介の中で、この記事のようななるほどと思う話はされたことがある。ただ、P.72左段のお勧めの実験装置については写真だけなので、せめて使い方ぐらいは書いてほしかった」との感想が出されました。
-
阿久津さんからは、「漏斗台とロートの話が出たが、p.44右段下の表Cの“滑らかな麺の上を”は“滑らかな面の上を”だろう」との指摘がありました。
-