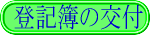
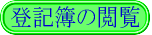
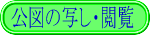
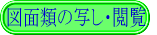
登記所での登記簿・公図等の交付及び閲覧の方法
皆様は、ご自分所有の土地又は建物の登記簿謄本や公図、地積測量図を見たことがありますか?
普通に生活されている中ではなかなか見る機会がないと思います。
見たことがあるにしてもご自分で登記所に行って交付の請求をしたり閲覧の請求をしたことある人はあまりいないでしょう。
このページでは自分で登記所に行って交付の請求及び閲覧をする方法を簡単にご説明します。
これを参考にすれば今日にでも登記所に行ってご自分で交付及び閲覧ができます。
ご覧になりたいものをクリックしてください。
最初は登記簿の交付及び閲覧についてですが、現在登記所はコンピューター化がすすんでいまして多くの登記所でバインダー式の登記簿が無くなっています。
もちろん全ての登記所という訳ではなく現在もバインダー式の登記簿がある登記所もあります。
バインダー式の登記簿をコピーしたものを「登記簿謄本」といい、コンピューターで打ち出したものを「全部事項証明書」と言います。呼び名は違いますが内容は一緒です。
また、「登記簿謄本」も「全部事項証明書」も交付の請求の仕方は同じです。
 それでは交付の請求方法について説明します。
それでは交付の請求方法について説明します。
最初は登記所に行くのですが、これはどこの登記所でもいいというわけではなく調べたい不動産の管轄登記所に行きます。例えば青梅市なら青梅登記所、福生市なら福生登記所です。(正式には東京法務局青梅出張所・福生出張所)
東京の登記所の管轄一覧は右のリンクボタンをクリックしてください。![]()
さて登記所につきました。次はいよいよ交付の申請です。
登記所に行くと数種類の申請用紙が用意されています。例えば登記簿謄抄本申請書、登記事項証明書申請書などがあります。
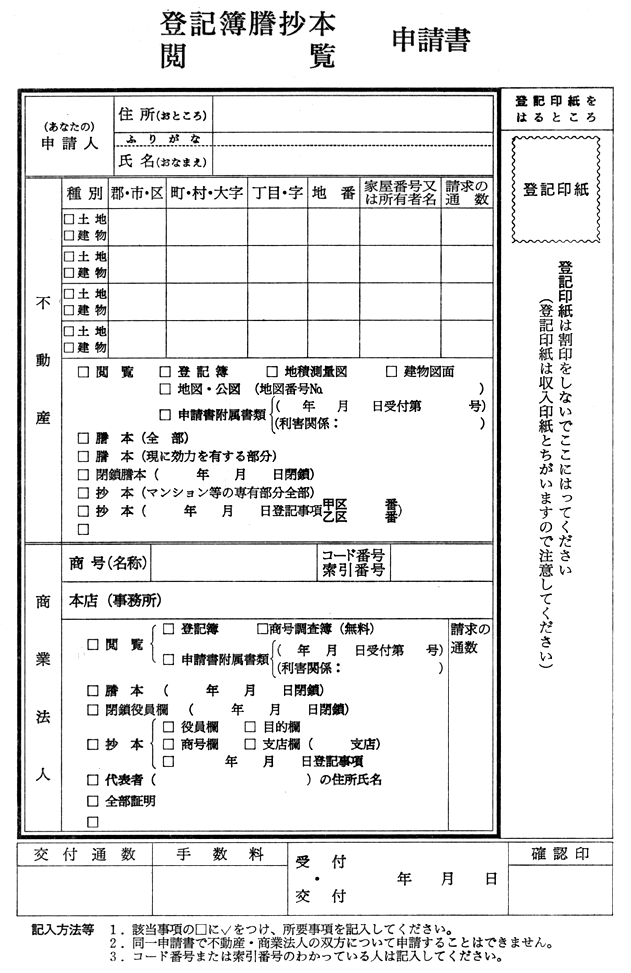
このような申請書に必要事項を記載して提出するのですが、土地の場合は「地番」欄に住居表示を記載しても謄本をとることはできません。
あなたは、ご自分の土地の「地番」はご存知ですか?
知らないという方のために地番を調べる方法を記載しておきます。
登記所に行くと住宅地図(ブルーマップ)があります。その住宅地図であなたの土地をさがします。
場所が特定できましたらその場所もしくは近くに住居表示とは違った数字が書いてあると思います。その数字を覚えておいてください。次にその住宅地図で特定した場所の近くに太字で公図○○番あるいはNO,○○と書いてあると思います。それが公図の番号です。
上記で調べた2つ(住居表示とは違う数字と公図番号)で公図の申請をし、その公図から地番を特定します。
ただし公図には、地番が記載されているだけで所有者名などは記載されていませんので住宅地図と公図をよく見比べて地番を特定してください。公図の請求方法については「公図の交付・閲覧」に詳しく記載してますのでご参照ください。
![]()
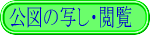
では、請求方法ですが、わかりやすいよう番号をつけて説明します。
①申請書にあなたの住所・氏名を記載してください。
②土地の□にチェック(レ)を入れて○○市○○町○丁目○○番のようにご自分の土地の所在地番を記載してください。(建物の場合は建物の□にチェック(レ)を入れて所在地番を記載し家屋番号又は所有者名を記載します。)建物の場合は同じ土地に所有者の違う家等が建っている場合があるからです。
③請求枚数の箇所は取りたい部数を記載してください。
④謄本の□にチェック(レ)を入れてください。(コンピューター化されている登記所では「登記簿謄抄本申請書」ではなく「登記事項証明書申請書」の全部事項証明書の□にチェック(レ)を入れます。)
⑤窓口に申請書を提出してください。
⑥ご自分の名前が呼ばれましたら窓口に行って申請内容と謄本があっているかを確認してください。
⑦あっていたら手数料(1通 1000円)を登記印紙で納めてください。
以上です。
 では、次に閲覧について説明します。
では、次に閲覧について説明します。
登記所に行くと机と椅子がある仕切られた場所があります。そこが「閲覧室」です。登記簿や図面類は外に持ち出すことが出来ないことになっており閲覧室で閲覧します。
ただし閲覧ができるのは、バインダー式の登記簿だけです。コンピューター化された登記所では簿冊の登記簿はありません。(無いといっても処分してしまったわけではなく閉鎖登記簿として扱われます。)
では閲覧したい場合はどうするのか?ですが、コンピューター化された登記所では従来の閲覧制度のかわりに「登記事項要約書」というものの交付を受けることが出来ます。
登記事項要約書とは、登記簿に記載されている事項のうち、普通必要だと思われるような部分(不動産の表示についての事項・所有権の登記事項のうち所有者の氏名、住所、持分、申請受付の日付・所有権以外の登記で現に効力を持っものの主要な事項)をピックアップして記載した書面です。
「登記事項要約書」の請求の方法は、登記簿の請求方法と同じです。ただし申請書は異なり要約書という箇所に□チェック(レ)します。記載事項は、登記簿と同じです。
それでは、バインダー式の登記簿の閲覧請求方法について説明します。
これも交付請求と同じで申請書に氏名・住所を記載し必要事項を記入します。(所在・地番)
交付請求の時は、内容確認後に手数料の印紙を貼ると説明しましたが、閲覧の場合は、先に印紙(500円)を貼ることをオススメいたします。
記載が終わり登記印紙を貼ったら窓口に提出します。その後登記所の方からあなたの名前が呼ばれますので呼ばれたら閲覧室に入り閲覧を始めるわけです。
閲覧方法ですが登記簿は「土地」に関しては、地番区域ごと(例えば青梅市河辺町四丁目)土地の地番の順序に従って編綴されています。また「建物」に関しては地番区域ごとに建物の敷地の地番の順序に従い編綴されています。規則正しく編綴されていますのでバインダー式の登記簿からあなたの「土地」又は「建物」の登記用紙をさがしだしてください。
さがしだしましたら何を閲覧したいかです。登記簿は「表題部」・「甲区」・「乙区」の順に編綴されています。「表題部」は不動産の物理的状況(土地なら所在・地番・地目・地積等)が記載され、「甲区」は所有者に関する事項が記載され、「乙区」は所有権以外の権利に関する事項(抵当権など)が記載されます。
これで自分が見たい箇所を確認するわけです。
以上です。
 ここでは公図の写しの請求及び閲覧についてご説明します。
ここでは公図の写しの請求及び閲覧についてご説明します。
「公図」とは何か?用語解説で詳しく説明していますが簡単にいうと、あなたの土地の位置、形状及び地番を表示したものです。(地図又は地図に準ずる図面の違いについては用語解説でご確認ください。)
それでは「写し」の請求方法ですが「登記簿の交付・閲覧」でも説明していますが再度ご説明します。
まずご自分の不動産を管轄する登記所へ行きます。そして数種類ある申請書の中から「地図等の閲覧・写し申請書」に必要事項を記載するわけですが、その前にいくつか確認事項がありますのでチェックしてください。
①ご自分の土地の地番はご存知ですか?
②公図番号はご存知ですか?
わからないという方のためにご説明します。
ご自分が住んでいる住所はわかりますね。ただしこの住所=地番とは限らないのです。住居表示というのを聞いたことありませんか?市町村区がつけるものです。これは登記所で管理している地番とは異なります。ですので申請書に住居表示を記載してもだめなんです。
次に公図番号(地図番号)ですが公図(地図)は1筆又は数筆ごとに作られていますのであなたの土地は公図番号何番に記載されているかを知らないとだめなんです。
申請書には、所在(○○市○○町○丁目○○番)公図番号(地図番号)を記載する箇所がありますのでこれを申請する前に調べておきましょう。
ではどうやって調べるかですが、登記所に行くと住宅地図(ブルーマップ)というものがあります。
この住宅地図は○○市ごとに作成されていますので地図上であなたが調査したい場所をさがしだしてください。
場所が特定できましたらその場所もしくは隣地(近辺)に住居表示とは異なる数字が記載されています。それが地番ですが、それがあなたの土地の地番とは限りません。
次に住宅地図上で特定した場所の近辺に公図○○番(地図○○番、№○○番)と記載されています。これが公図番号(地図番号)です。
住宅地図で調べた地番と公図番号で公図(地図)の閲覧の申請をします。閲覧で公図(地図)をコピーをとることができますのでコピーで用が足りる方は閲覧室にコピー機がありますのでコピーを取ってください。また、どうしても写しが必要な方は、これから説明する方法で地番を特定して再度「写し」の請求をしてください。
閲覧の請求については下に記載してあります。
| 1-1 | 1-5 | 2-1 | 3-1 | |||||||
| 1-2 | 1-6 | 2-2 | 3-2 | |||||||
| 1-3 | 1-7 | |||||||||
| 2-3 | 3-3 | |||||||||
| 1-4 | 1-8 | 2-4 | 3-4 | |||||||
公図は、上図のように所有者名などは記載されておらず土地の地番しか記載されていませんので先程調べた住宅地図とよく見比べて地番を特定してください。
順序が逆になってしまいましたが「写し」及び「閲覧」の申請方法を説明します。
写しも閲覧も請求方法は同じです。これも番号順に説明します。
①「地図等の閲覧・写し申請書」にあなたの住所・氏名を記載してください。
②所在記載欄に土地の所在・地番を記載してください。上で調べた地番です。
③写し□、閲覧□ の□にチェック(レ)を入れてください。
④地図・公図□及び現在のもの□にチェックを入れてください。
⑤公図番号(地図番号)を記載してください。
⑥閲覧の場合は手数料(登記印紙500円)を貼って、写しの場合は貼らずに窓口に申請書を提出してください。
⑦写しの方は名前が呼ばれましたら窓口にて申請した公図(地図)に間違いないことを確認して手数料(登記印紙500円)を貼ってください。閲覧の方は名前が呼ばれましたら閲覧室に入り閲覧してください。上でも説明しましたが閲覧室にはコピー機がありますのでコピーを取る事も可能です。その際に閲覧した年月日・地番区域名・縮尺・公図番号(地図番号)をコピーした公図に記載しておくと良いと思います。
以上です。
 ここでは図面類の写し及び閲覧についてご説明します。
ここでは図面類の写し及び閲覧についてご説明します。
登記所において図面類というと土地では「地積測量図」・「土地所在図」等、建物では「建物図面」・「各階平面図」等があげられます。
図面の「性質」については用語解説に記載してありますのでご参照ください。
図面類の写し・閲覧ともに申請書は同じ用紙「地図等の閲覧・写し申請書」です。
写しも閲覧も請求方法は同じです。これも番号順に説明します。
①「地図等の閲覧・写し申請書」にあなたの住所・氏名を記載してください。
②所在記載欄に土地の所在・地番を記載してください。
③写し□、閲覧□ の□にチェック(レ)を入れてください。
④取りたい図面の□にチェックを入れてください。
⑤閲覧の場合は手数料(登記印紙500円)を貼って、写しの場合は貼らずに窓口に申請書を提出してください。
⑥写しの方は名前が呼ばれましたら窓口にて申請した図面に間違いないことを確認して手数料(登記印紙500円)を貼ってください。閲覧の方は名前が呼ばれましたら閲覧室に入り閲覧してください。上でも説明しましたが閲覧室にはコピー機がありますのでコピーを取る事も可能です。
以上です。