はじめに
この前友達の家に遊びに言った日のこと、友達はパソコンでテレビを見ていました。アンテナはというと、自作で作っ
た八木・宇田アンテナがベランダにあり、しっかり画面が映っていました。私の部屋にはテレビアンテナが通ってなく、テ
レビを見たくても見れませんでした。そこで、友達の作ったアンテナを見て自分も作ってみようと思いました。このページ
では八木・宇田アンテナの理論と八木・宇田アンテナの歴史、さらに実際に使ってみた時のテレビの映りを紹介します。
た八木・宇田アンテナがベランダにあり、しっかり画面が映っていました。私の部屋にはテレビアンテナが通ってなく、テ
レビを見たくても見れませんでした。そこで、友達の作ったアンテナを見て自分も作ってみようと思いました。このページ
では八木・宇田アンテナの理論と八木・宇田アンテナの歴史、さらに実際に使ってみた時のテレビの映りを紹介します。
理論
八木・宇田アンテナは鋭い指向性で有名なアンテナです。このアンテナは3本の素子によって成り立っています。この
アンテナの構造を次に示します。
アンテナの構造を次に示します。
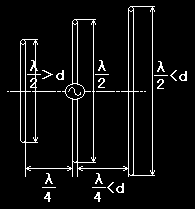
左から、導波器、給電素子、反射器となっていています。導波器は飛んでいる電波を拾うための素子で、この素子を
増やすことにより指向性が鋭くなります。給電素子は導波器で拾った電波を吸収しテレビへと電波を通します。反射器
は導波器で拾いきれなかった電波を反射し給電素子に導きます。実際はこの3素子だけでテレビは映るようになりま
す。しかし、導波器の本数を変えたり形を変えることにより、より電波を拾う量が多くなり、よりよい映像が映るようにな
ります。
増やすことにより指向性が鋭くなります。給電素子は導波器で拾った電波を吸収しテレビへと電波を通します。反射器
は導波器で拾いきれなかった電波を反射し給電素子に導きます。実際はこの3素子だけでテレビは映るようになりま
す。しかし、導波器の本数を変えたり形を変えることにより、より電波を拾う量が多くなり、よりよい映像が映るようにな
ります。
それでは、素子の長さやそれぞれの間隔はどうするのかというと、放送局の電波送信周波数の値からλを決めま
す。それにより設定する素子の長さや間隔が変えることができます。各放送局の送信周波数を次に示します。
す。それにより設定する素子の長さや間隔が変えることができます。各放送局の送信周波数を次に示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この表を参考にしてλを決めましょう。決めるときに使う式は次の通りです。
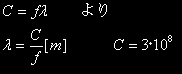
Cは光速で周波数と割ることによりλを算出することが出来ます。