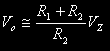目的
この度、直流安定化電源の製作をしようと思いついたのは、家で実験や製作をする環境がまったくといっていいほど
整っていないからです。ということでせめて直流安定化電源ぐらいは持っておこうと製作に踏み切りました。学校が移転
するという事で、内々で貰い受けることが出来るのですが、それには数ヶ月待たなければなりません。卒業研究などで
切羽詰った時のために家で実験をするため、作る事にきめました。という事で…。
整っていないからです。ということでせめて直流安定化電源ぐらいは持っておこうと製作に踏み切りました。学校が移転
するという事で、内々で貰い受けることが出来るのですが、それには数ヶ月待たなければなりません。卒業研究などで
切羽詰った時のために家で実験をするため、作る事にきめました。という事で…。
理論
一般に直流安定化電源は家庭用電源100Vを降圧し自分の必要とする電圧にし可変できるようにする、というもの。ま
ず直流安定化電源を構成する回路説明から入ります。(ここではシリーズドロッパ方式の説明をする)
ず直流安定化電源を構成する回路説明から入ります。(ここではシリーズドロッパ方式の説明をする)
直流安定化電源は
①② 全波整流回路
まず図1は電源トランスからの電圧を全波整流回路で整流を行うための回路である。全波整流回路の動作は、まず
入力の正の半周期の電圧でD1、D3がON、負の半周期の電圧でD2、D4がONとなり正弦波入力電圧の両半周期が正の
周期に現れ全波整流となる。波形を図2に示す。
入力の正の半周期の電圧でD1、D3がON、負の半周期の電圧でD2、D4がONとなり正弦波入力電圧の両半周期が正の
周期に現れ全波整流となる。波形を図2に示す。
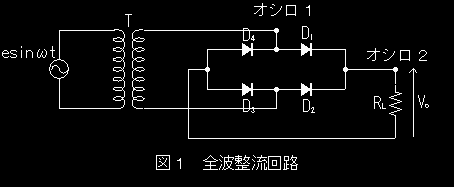
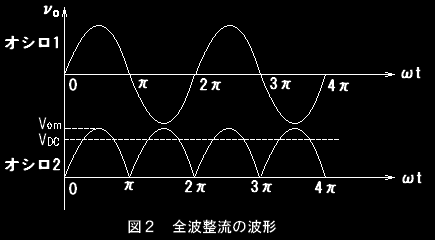
この回路から次に説明する平滑回路で直流となる電圧VDCは次の式で求まる。
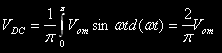
さらに直流電圧に平滑した時いかにどれだけ交流成分のない波形になっているかを判断する値をリプル率といい、
次の式で求まる。
次の式で求まる。
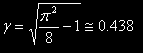
③ 平滑回路
次に平滑回路について説明する。平滑回路は交流成分を直流成分に近似する回路である。全波整流回路に平滑回
路を接続した図3を次に示す。
路を接続した図3を次に示す。
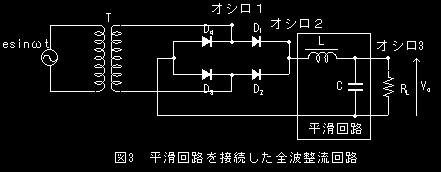
平滑回路がコンデンサCだけではコンデンサ容量が大きくなりダイオード導通時に急な大きいパルス電圧が発生し、
それがコンデンサやダイオードの劣化を促してしまう。そこでこのパルス電圧を防ぐためチョークコイルLを接続してい
る。
それがコンデンサやダイオードの劣化を促してしまう。そこでこのパルス電圧を防ぐためチョークコイルLを接続してい
る。
平滑した交流成分の波形を図4に示す。
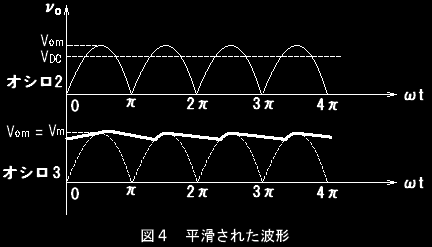
図4の波形ではまだまだ交流成分が残っており、実際に直流電源にするにはさらに直流成分に近づけなければなら
ない。実用上リプル率が0.01以下の時完全な直流成分となるので、図3の回路でのリプル率は、
ない。実用上リプル率が0.01以下の時完全な直流成分となるので、図3の回路でのリプル率は、
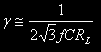
となる。なおこれらはダイオードが理想動作の時である。
④ レギュレーション回路(安定化回路)
これまでに述べた回路だけでは周囲条件(電源電圧変動・負荷電流変動など)の変動に対して、出力の直流電圧を
一定に保つのは難しい。そこでこのレギュレーション回路により、出力負荷や電源電圧変動を検出し負帰還をかけるこ
とにより、変動分を相殺する事が出来る。このような機構は2種類ありシリーズ・ドロッパとスイッチングがあり、ここでは
シリーズ・ドロッパ方式を説明する。
一定に保つのは難しい。そこでこのレギュレーション回路により、出力負荷や電源電圧変動を検出し負帰還をかけるこ
とにより、変動分を相殺する事が出来る。このような機構は2種類ありシリーズ・ドロッパとスイッチングがあり、ここでは
シリーズ・ドロッパ方式を説明する。
次に回路図を示す。
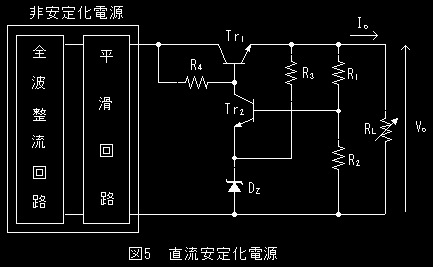
この図5のようにトランジスタのエミッタ・コレクタ間電圧降下を利用しレギュレーションを図っている。出力電圧VOは次
の式で表せる。
の式で表せる。