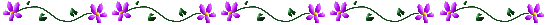= 明日のことは分らない =
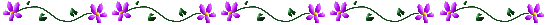
12’1’13
= 明日のことは分らない =
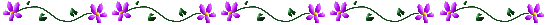
12’1’13
昨年暮れのうちに、年明けの一月末の新年会への参加者を募る回覧板が回り、年が明けてから集金に来てくれた。 「今年は参加者が多い」と言う。 今回はそう遠くはない店なのが良かったのか、子育て中だった人たちも、それぞれお子さんが大きくなって参加しやすくなったということか。 婦人部からの助成金があるので、会費は二千円で済むということもある。
「Tちゃんも参加するはずだったけれど、その分が一人減っただけで、五十人近い参加になった」と、集金に来てくれた副会長を務める隣の奥さんが言う。 「Tちゃんも行くはずだったの!」とびっくりした。 そのTちゃんは亡くなって、お葬式を終えたばかりだった。
少なくとも、一ヶ月前には、町内の皆さんと食事会を楽しもうと考えていたのだ。 八十六歳と言う年齢を考えれば、日本女性の平均寿命と同じだから仕方ないのかもしれないが、それほど元気だったのにと思うと切ない。
体調を崩して救急車で入院し、十日あまり後に亡くなったとのことだった。 ちょっと遠い病院に搬送されたことから見ても、普段、近くの病院にかかりつけていた状態ではなかったのだろう。 かかりつけていない病院では、救急車の搬送を受け入れてくれないのが現状だ。
若くても同じとは言え、年を重ねれば、本当に「明日のことは分らない」のである。
昨年は、山仲間だった元気な友人の急逝もあった。
山も、私たちのレベルでは物足りなかったのか、定年後は、ほかのグループに移り、西に東にと登山行脚を続けていて、行き会えば、「どこそこの山に行ってきた」と言う話ばかりだった。 同時に「世界遺産めぐり」にも熱心で、どこまでも出かけていたらしい。
たまたまウォーキング途中で行き会い、立ち話をした際に、「相変わらず行っているの?」と尋ねたところ、「前ほどじゃないけどね」と言う。 「また戻って来ない?」と誘いを掛けたが、「そうね・・・」と笑っていた。 彼女の訃報に接したのは、それから僅か十日の後だった。 私よりも四〜五歳若く、人一倍の元気者だった。
せわしないほどによく動く人だったから、「生き急いじゃったね」と彼女を知る人たちは話し合う。 娘さんの話では、その日も午前中はプールに通っていたと言う。 ご主人が出先から戻られた時に家の中で倒れていたとのこと。
一人になられたご主人も、「あれだけ遊んだのだから」とお思いだろうとか、「奥さんの留守には慣れていらっしゃるだろう」とか、外野は勝手な話をしている。 あんなに元気でも「分らないもの」と、つくづく感じた彼女の死だった。
今年は年賀状の中にも同級生の訃を知らせる文があった。 また、健康を害したとの文面も増えた。 年を重ねれば仕方のないことである。
人の世は無常と言う。 それを実感できる年齢になったと思う。 しかし、「今日明日は大丈夫そう」と、妙な自信があるのも事実である。 もっとも、そう思うから、元気で動いていられるのだろう。
今年がどんな年になるか予想は付かないが、できることならば、無理のない範囲で、楽しく充実した日々であればと願う。 「明日のことは分らない」ながら、「終わりよければ全て良し」と言う人生にしたいと思うのである。