〜 姉 と 義 姉 と 〜
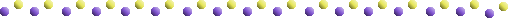
11’7’27
〜 姉 と 義 姉 と 〜
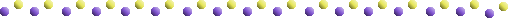
11’7’27
ご飯は好きだが、一日三食ご飯を食べると、ちょっと胃に負担がかかるので、朝はパン食にしている。 麺類の好きな人は多いが、親しい友達は外食するときも、私のために「両方」食べられる店を選んでくれる。
今はうどんもそばも食べるが、以前はほとんど食べなかった。 食べるようになったのには、うどんにまつわる「二人の姉」との経緯が大きいのかもしれない。
終戦から数年後、我が家には疎開先から戻ってきた姉一家が同居していた。 姉一家は義兄の実家に疎開していたのだ。
終戦の年に、ほとんど寝たきりだった母は亡くなったが、炊事は父や兄の仕事になっていたから、姉が一緒になったことはある意味では良かった。 ただ、私と姉との仲はあまり芳しくはなかった。
ある日曜日の昼に、姉はうどんを用意してくれていた。 私が「食べない」と言ったので、私の分はなかった。 それを見た父が、「ご飯が残っているならもって来てやれよ」と言ったものだから、姉のオヘソは曲がった。 「わがままだ」と言うのである。 気に入らなければ食べなければいいと言う。
私は「ほかのものを食べたい」と言ったわけではないが、父の一言でご飯が食べられた。 当時、私は中学生だったと思う。
姉とは十九歳の年の差があり、小さい頃から洋服を縫ってくれたり、私のことを気にはかけてくれていたのだが、へ理屈ばかり言う、生意気な妹に、我慢がならなかったのだろう。
男が三人続いた後に生まれた私を母が大変可愛がり、そのことが姉の機嫌を損ねたのだと、長兄は教えてくれたが・・・。
私が成人する頃には父もすでに亡くなっていたが、姉との関係はだいぶ良くなって、義兄が、「このごろはよく来てくれるようになったね」と言ったりした。
私が結婚して住むことになったのは、東京とは言え、田舎だった。 姉は義兄の実家に疎開して苦労したらしく、「あなたに田舎の生活は無理」と反対した。 確かに戸惑うことも多かったが、幸か不幸か、仕事を続けていたので、それなりに暮らしていた。
古い風習が残っている土地で、何かことがあると助け合う「組合」というものがあって、それは江戸時代の「五人組の名残」ということだった。
組合内の葬儀のときなど、仕事を休んで手伝わなくてはならなかった。 そして、必ず振舞われるのが「うどん」である。
私はやはり、あまり手をつけなかったのだろう。 ある時、夫の兄嫁に「嫌いでも食べるものだ」と言われた。 ここに住む以上、うどんを食べないわけには行かないのだと思った。
修行の甲斐あって、今では、うどんもそばも食べている。 我が家の食卓にも載せる。 ただし、みんながおいしいという「手打ちのそば、うどん」よりも、味気ないとされる「器械打ち」の方が好きだというのが本心である。 私にとって、「うどん」はどれでも「うどん」なのである。
時代が変わり、組合も有名無実となった感があり、うどんを「よばれる」機会もめっきり少なくなった。
姉と義姉と。 まったく違う経験だったが、うどんにまつわるこの二人との思い出も、今となっては懐かしい。