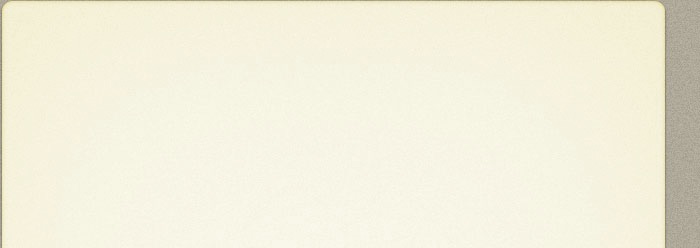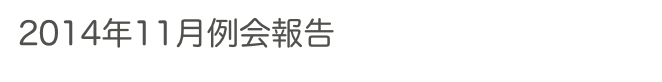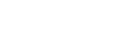-
日 時:2014年11月28日(金)19:00~21:45
-
場 所:国分寺市本多公民館
-
参加者:阿久津・小川・北島・勝田・岸・鈴木(ま)・鷹取・町田・堀(記録)
-
今回は、サークルのホームページを見て、北島さんと岸さん、横浜物理サークル(YPC)に参加していて、そこで紹介されたということで勝田さんの、なんと3人が初参加でした。今後とも、よろしくお願いします。
-
-
0.当日の配布物
-
・「江戸時代 八王子に隕石落下?」…………………………………………堀 雅敏
-
「東京新聞」の、江戸時代後期の八王子に隕石がたくさん降り注いだという記事で、古文書「桑都日記」の紹介や、“もしかしたらその時の隕石小片かもしれない”ものを国立科学博物館が所蔵している、などの情報です。
-
-
1.『理科教室』を読んで「『理科教室』2014年11月号」…………堀 雅敏
-
11月号の表紙写真、以前中央沿線理科サークルに参加され、いまは栃木で活躍されている山崎美穂子さんの実践記録、特集「小学校からの化学変化の学習―酸化還元反応―」の玉井裕和さん(大阪)の論文を中心に、気のついたことをメモしたプリントをもとに感想を述べました。
-
話の流れの中で、勝田さんから「小学校で“つぶ”の概念が必要だろうか」と質問がありました。鈴木さんが「温度と物の体積や三態変化などのところで、初歩的なイメージはできるのではないか」というような趣旨の話をされました。すると勝田さんは「それは分子運動の話になる。それが何かの学習につながるのか」との疑問を発言。
-
かつて理科が週4時間あったころは、温度と物の体積でも、三態変化でも溶解でも、“つぶ概念”の授業は科教協の中で結構行われていたように思います。いまは週3時間となり、『本質がわかる・やりたくなる 理科の授業』(子どもの未来社)の中では、4年(高橋洋・著)の気体の学習の中で「飛び回る気体分子の話」を取り上げているだけです。
-
ここで“分子”という言葉は使っていても、それは中学校の原子・分子概念への入口としての位置づけであり、初歩的な概念としてでした。故・玉田泰太郎さんは、その著書『理科授業の創造 物質概念の基礎を教える』(新生出版)によると、三態変化の授業の途中、「なぜアルコールや水は液体から気体に変わると、アルコールや水の実質の量が変わるわけではないのに体積が著しく変わるのかが問題になった」ということで、1時間とって「グループで討議して、みえないアルコールがみえるように図に書いて説明できるように指示」しました。
-
-
子どもたちが考えたイメージは、右図のようでした。「つぶ自体が大きくふくらんだ」「つぶがまわりに集まり、風船を押した」「つぶがばらばらに散らばって動き、風船を押した」「つぶとつぶとの間が広がった」などです。この後議論が行われ、最終的には玉田さんの方から「分子の集合状態やふるまいのちがいを、子どもたちの考えもひきあいにだしながら話した」ということです。
-
これについて、「本格的に分子・原子が登場した物質の追求は中学校の段階であろう。しかし、小学校でもマクロな事実とミクロなとらえ方を結びつけて物質を追求することを、溶解や物の三態などでとりあげることは意味があると思っている。この段階で、すべての子どもに実在としての分子・原子を理解させようなどと考えているわけではないし、またできもしない。
-
それは、中学校での分子・原子からはじまる組織的な授業にゆずるとして、物質を構成している目にみえない粒子(分子、原子)の存在とふるまいに目をむけさせておきたいのである」と、玉田さんは述べています。
-
初歩的とはいえ、玉田さんの授業の中では、かなり本質的な討論が行われていました。この後、例えば《炭素の酸化》の授業で「この炭素のかたまりを酸素中で熱すると、どんな変化がおこりますか」という課題で、つぎのようなやりとりがありました。
-
高橋:炭素と酸素が化合して酸化炭素ができると思う。
-
蔵田:酸化炭素といっても……。
-
鳥海:フラスコの中で炭素と酸素が化合して発熱することを、ふつうぼくたちは燃えるといっている。空気中や酸素中で木炭が燃えると二酸化炭素ができる。だから、このときも二酸化炭素ができると思う。
-
蔵田:(2人の賛成意見が続いた後)わかった。やはり炭素を酸素中で熱すると発熱して光が出る。それは炭が燃えるということです。炭が燃えたときには二酸化炭素ができるのだから、このときも二酸化炭素ができる。
-
元素記号や分子式など学習しているわけではないのですが、<炭素+酸素=酸化炭素>というような思考が見られます。つまり、多くの子どもたちの頭の中には、炭素のつぶと酸素のつぶがくっつくイメージがあったのではないでしょうか。
-
小川さんからは、教科書につぶの図が出ていることの指摘がありました。しかし、玉田さんのように子どもたちの思考の順次性に即した体系的な授業が構成されていないのでは、子どもたちには理解できないでしょう。つけ加えるなら、教科書の中には一部、大切な内容につながる、工夫された図版もありますが、どれも矢印が描かれていません。
-
-
2.教材研究・授業プラン「山麓堆積地・扇状地、町づくりと土砂災害」………………鷹取 健
-
「中央沿線理科サークル通信」2014年10月号と11月号に掲載された詳しい資料と、自作ビデオの映写による提案でした。日本における自然災害では1000人を超える被災者が出ることがずっとあったこと、仙台平野における内水と津波浸水区域はほぼ一致すること、山梨県南都留郡旧足和田村や広島市の土砂災害では土石流の直撃を受ける小さな扇状地上に集落ができていたことなどが話されました。
-
勝田さんと阿久津さんからは、「地形図を読みとる授業が、中学校でできるのか」「地形図を見て、写真のようにイメージできるのか」「自分も大人になってからスキーに行くようになって、付近の2万5千分の1地形図と実際の地形をつなげて考えられるようになった。実際に歩いてみないと、地形図とつなげるのは難しいのではないか」「地形図を読まないでも、この住宅は多摩川沿いにあって河原に建っているなど、ほかの知識で自分の住んでいる場所がみえるのではないか」などの意見が出されました。
-
これについて鷹取さんからは、「等高線などについては社会科でやることになっている」「写真やビデオなども使いながら地形図とつなげたい」「地形図、まずは土地条件図を読めるように、学校教育で責任を持ちたい」との話がありました。また、鈴木さんからは、「いまの小学校では社会科で地図の見方が少し出てくる程度。海抜高度の高い低い、自分がどちらに歩いているのか、山をつくって水を流して、等高線とは?等高線の幅が広いところは?狭いところは?などと地形図とつなげたい」「土地の削られたところや盛り土などは写真ではわからないが、地形図ならわかる」「地形図は、すべての子どもが読めるようにさせたい。大人になったときに、自分の住んでいるところがどんなところかわからない。市民としてそれでいいのか」との意見がありました。小川さんは、「地形図を読めることは大事。新しい地形図と、30年前の地形図を比べるとみえてくるものがある。生徒にとってもわかりやすく、将来自分で土地や家を購入するときにも役に立つし、自分の身を守ることにもつながる」などと、話されました。
-
阿久津さんも「地形図が読めなくていい」と考えているわけではないし、鷹取さんもこの単元だけで地形図学習すべてをさせようとしているわけではありません。
-
町田さんから、「“地形図が読める”というのは、小学校、中学校のそれぞれの段階でどういうことなのか」との質問が出され、小学校について鈴木さんは「方位、高低、地図記号がわかること」、中学校について鷹取さんからは「海岸線、水路、扇状地などがわかり、地形断面図が描けること、土地条件図から農業(人間の歴史)を読みとること」などの答えがありました。
-
こうした内容をきっかけに、地形図について、どこでどのような学習を組んでいくか、社会科も含めて検討していくことが、サークルの課題として出されたように思いました。