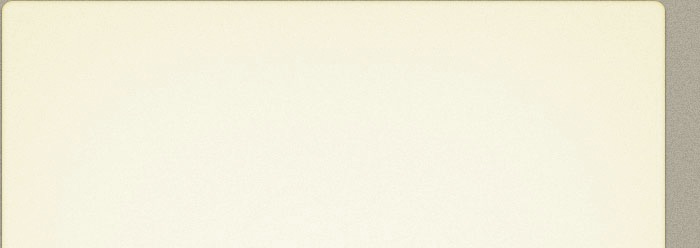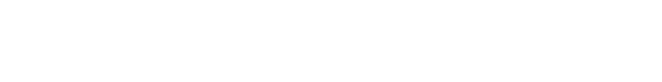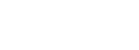-
日 時:2016年11月25日(金)19:00~21:45
-
場 所:国分寺市本多公民館
-
-
今回は、芝中高で生物の非常勤講師をされている小宮 英之さんが初参加されました。自己紹介で、持参されていたスダジイの幹を輪切りにした断面を見せてくださいました。中央部分が、黒っぽく変色していました。スダジイの幹に生えたキノコが菌糸を伸ばし、養分を得た結果だそうです。この部分はボロボロにもろくなっており、こうした木は強風などで倒れることがあるそうです。
-
今後ともよろしくお願いします。
-
-
1.授業プラン「“速度”と“加速度”の授業で大切にしたいこと」…… 町田
-
“平均の速さ”と“瞬間の速さ”を理解できていない生徒を前提にした「速度と加速度」の授業提案でした。
-
まず鷹取さんから2つの質問がありました。「科教協では瞬間の速度はいつ頃から検討されてきたのか。問題点は何か?」と、「子どもたちはグラフをどう理解しているのか」というものでした。
-
前者について町田さんからは、「古いことはわからない。ここ2年ほどの検討を聞いて考えた」とのことで、鷹取さんからは「1965年~67年頃、数教協では『数学教室』誌上などで瞬間の速度の検討をしていた。科教協の歴史を調べてみてほしい」との話がありました。
-
後者のグラフに関連して阿久津さんから、時刻(s)変位(m)速度(m/s)の表を元にして作成したという2つのグラフについて「このグラフはおかしくない?s-tグラフのようになるのなら、v-tグラフのようにはならないのでは?」との質問がありました。町田さんによれば、「“2~3秒くらいから劇的には変わらない”ということ」との説明がありました。
-
グラフについて鷹取さんからは、「生徒のグラフの認識はあやふやなのではないか。中学校では密度のグラフを描くことくらいしかやっていないし」との指摘がありました。
-
単元の流れについて阿久津さんから、「“速さ”と“速度”がごっちゃになっている。どちらかにそろえた方がいい」という指摘と、「“平均の速度”をやらない方がいいのではないか、と思っているが、やる意義は?」との質問がありました。
-
町 田:冬の研究集会での討論から考えた。まず平均の速度を出す。その時間間隔を短くしていくことで、瞬間の速度が出る。
-
阿久津:子どもの認識からすると、どうだろうか。自分としては“平均の速度”も“瞬間の速度”もやらない。“速さ”だけでやろうと思う。グラフも、IT計測器“イージーセンスビジョン”に描いてもらう。
-
鷹 取:中学での話になるが、時間と時刻は同じくらいよく使っている言葉。どう違うのか、というところから始めて、“瞬間の速度”を検討した。生徒はどう理解するのかを語らないと…。
-
阿久津:確かに、時刻と時間がどう違うのかを話してからv-tグラフをやらないと、わからないかもしれない。
-
さらに、町田さんの提案にある、「加速度の考え方」に「“浦邊チャート”がわかりやすい」とされていることに関して意見が出されました。
-
阿久津:初めて学習する生徒にとっては、浦邊悦夫さん(物理サークル)のやり方は、難しいのではないかと思い始めている。
-
津 田:“浦邊チャート”は、ベクトルがよくわかっていない子には、加えた力=速度と誤解してしまうのではないか。
-
町 田:「ここに描いているのは、すべて速度の矢印」と言わないとだめなのかな。
-
-
2.教育問題「東京都教育委員会教師道場見学会に参加して」…… 阿久津
-
都教委教師道場の“見学会”として、「物の温度と体積」の導入部分の授業を参観した報告でした。
-
阿久津さんは、「教材や発問が悪く、子どもたちが混乱していたにもかかわらず、協議会では褒めまくっていた」「授業者は多くの失敗をしているけれども、全く気づいていなかった。おそらく、自分自身がわかっていない内容の授業だからだろう」と感じたようです。
-
鷹 取:ちょっと感じ方が違う。そこに来ている人は、本当は物理現象について理解していたのではないか。固体→液体→気体の順はいいとして、自分ならこういう風にやるということを、やっていくしかないのではないか。その中で一人でも仲間になってくれればいい。
-
阿久津:若い人に、聞く耳を持ってもらうのは難しい。
-
鈴 木:付箋を貼ってから話し合うスタイルは、広まっているようだ。「批判がない」ということだが、自分が授業者なら痛烈な批判はされたくない。水位が元に戻ることはやったのか?
-
阿久津:授業者からの指示はない。やっている子はいた。水位の上昇はすぐに確認できるが、何の体積が増えているかわからない実験だ。
-
その他にも「管理職の中には“授業力をつけられるから”と、若い人を教師道場にしつこく誘っている人がいる。」「そこで科教協の授業ができるならいいが…。」「教師道場で科教協式にやっても、たぶん学習指導要領の枠を越えられないのではないか。」などの発言もありました。
-
-
-
3.『理科教室』を読んで「『理科教室』2016年11月号」……津田
-
11月号の、ほぼ全般にわたる感想の提案でした。話し合いは、特集「理科の学力とは」から始まりました。
-
鈴 木:松井吉之助さんの論文から、“教育予算の削減と学力調査が一連のものである”ということを、初めて知った。教科の“指導書”をきちんと分析して乗り越えなければならないと思った。
-
鷹 取:学力テストについては、松井吉之助さん、小佐野正樹さんと一緒に、何十回も会って勉強した集団検討だったけれども、論文はそういう形にはなっていない。また、この大問題である学テ反対について、科教協静岡大会での反応はよくなかった。
-
阿久津:特集に関して、津田さんは、もっと遠慮なく言っていいのではないか。岩崎さんと、学テの論文以外は特集の趣旨とちょっと関係ないと感じた。どんな原稿依頼をしたのか。学テについてもっとあってもいい。
-
鷹 取:学テについては、“連載”という議論もしたのだが…。
-
鈴 木:津田さんの指摘した地動説の話だが、箕輪さんは第1時で、もうやっていることにしているのではないか。
-
小 宮:(津田さんが調べたいとしている、岩崎敬道さんの論文中にある)ルーブリック評価やパフォーマンス評価などの資料を持っているので、協力できる。(池田亨平さんの論文に関して)生物の中では“誤差”はあまり出てこないが、科学的に定義づけられているのではないか。そうではないのなら、生徒にとってどこまでという目安を示したのか。
-
津 田:後者だと思う。「ここまでは誤差としていい」と…。
-
町 田:“有効数字”、“誤差”についてやっている高校もあるが、厳密にはやらない。
-
阿久津:1時間くらいかけてやった方がいいかもしれない。引き出しに入っている温度計を全部出してみると、すべてが同じ温度を示してはいない。
-
鈴 木:重さの量りだと、感量が表示されている。
-
-
4.教材研究「自然科学教育研究の原則」 ……鷹取
-
最後の残り少ない時間で、富士山のフィールドワークの映像を元にした「自作ビデオを作り直した」一言報告がありました。詳しい報告は、1月例会ですることとなりました。