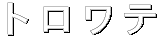 78
78駿河 昌樹 文葉 二〇〇八年七月
トロワ・テ、Trois thes。仏語で「三杯の茶」。筆者居住の三軒茶屋は三茶と略称される。
すなわち、トロワテ。ひたすら、益体もない文章のために。
『メモとかんがえ』集成 7
[20080623]
■メモとかんがえ20080623
[スタンダール『赤と黒』誤訳論争]
スタンダール『赤と黒』新訳にまつわる誤訳論争を、遅まきながら知った。フランス文学の古典作品をめぐって、この時代に、この日本で、まだ多少なりとも騒がれることがありうるのかと、まず驚く。
新訳を出した野崎歓東京大学大学院准教授自身の見解は目にしなかったが、誤訳箇所の指摘と批判をした下山茂立命館大学教授の書評、出版元の光文社文芸編集部・駒井稔編集長のコメント、および、これらについてのさまざま人たちの意見を読んだ。
駒井稔編集長のコメントは以下の通り。
「『赤と黒』につきましては、読者からの反応はほとんどすべてが好意的ですし、読みやすく瑞々しい新訳でスタンダールの魅力がわかったという喜びの声だけが届いております。当編集部としましては些末な誤訳論争に与(くみ)する気はまったくありません。もし野崎先生の訳に異論がおありなら、ご自分で新訳をなさったらいかがかというのが、正直な気持ちです」。
スタンダール研究者の下山茂教授からの批判に対しては、十九世紀フランス文学研究に関わる者や相当読み込んでいるスタンダリアン以外は口の挟みようもないから、一般の文芸趣味人や読書好きたちの中の一言居士たちは、この駒井稔編集長のコメントをめぐって言説をつくりあげる他なくなる。この編集長、さすがに光文社の編集長だけあって、たくみに、耳目を集めるような啖呵を切った。正面切って翻訳者を擁護する姿勢を見せて頼もしいが、その実、あきらかに商売優先。いったん出した商品は、とにかく売る。本当にダメな翻訳だとなれば、出版社は訳者を切ればいいだけなのだから、商人としての本音の本音はじつは明快なはずである。とにかく、こうあっけらかんと出られたら、市井のチシキジンさん、リョウシキジンさんたちは黙っておれなくなる。そこが編集長の狙いだ。
私としては、――というより、私だったらこのテーマについてどんなことを言おうとするだろうかと考えてみた。なにごとかを発言しておきたくなる要素というのは、今回の問題に関するかぎり、私の中にも多少集まっている。①肌身離さぬほどの大のスタンダール好き(家にいる時には、だいたい体から1メートル以内の特等席に並べてある。しかし研究をしたことはない)。②翻訳では読んだことがなく、原文でしか読んだことはない(自慢したくてこう言っているわけではない。ちょっとでも十九世紀フランス文学研究をした者が、原文でスタンダールの主著を読んでいないなどというのは職業倫理に悖る行為である。ただし、読んだからといって、ちゃんと理解したということにはならない。他の世紀のものより取っつき易そうな十九世紀フランス語の読解も、あまく見ると大間違いをする。わからないところ、いい加減に読み飛ばして、今後の宿題になっているところはいっぱいある)。③フランス文学研究に関わったので、理解や翻訳にまつわる諸事の面倒はよく知っており、翻訳の大変さも知っている。④『赤と黒』ほどの古典を訳す際にはトゥーサンやギベールを訳すのとはわけが違う精密さと研究史渉猟が求められると考えるタチである…
こういった因縁を「スタンダール」に対して持っている者からすれば、今回の誤訳論争に関しては、もう少し野崎歓東京大学大学院准教授が注意して訳すべきだった、と言いたくなるように思う。それだけのことだし、それだけのことにしておけばいい、とも言い添えたくなるように思う。他のことを、他のかたちで言いたくもなるかもしれないが、だいたいこんなところではないかと思う。そう自分に言い、そんなところで、ほぼ落着させる――ように思う。
下山茂立命館大学教授の指摘に全面的に従って訳していたら、訳文は停滞するだろうと思える箇所もあるから、現代的なノリを訳文で実現しようとした野崎歓東京大学大学院准教授に共感できるところはある。ただ、対象はなんといってもスタンダール、新訳をわざわざ出すとなれば、これは近未来の日本の文化になっていく。訳語の好みや理解にいくらか偏向があるという程度ならともかく、訳さずにすっ飛ばした部分が多かったり(すっ飛ばしたい気持ちはよくわかるし、すっ飛ばしてしまう事情もわかるが…。だいたい、スタンダール自身がすっ飛ばしの大家だった。長々と書く気にならない描写は省略してしまう人だったし、わざわざ小説中でそれを語ったりしたものだ)、基本的な時制の理解が誤っていたり、単語や熟語レベルの誤訳が多かったりでは、東京大学大学院准教授の仕事としてはちょっと困るんではないかね、と感じる。東京大学など国立大学の先生たちには、国民の血税が多量に投入されていることを忘れるべきではないだろう、と、一般庶民としては、いや、ボーナスも研究費も貰っておらず、すべて生活費を削って本も文具も海外渡航費用も捻出しているなんの栄誉からも遠い細民としては思ったりもする(こういう時、慎ましい生活の中で研究した本居宣長や極貧の中であれだけの研究をした宮本常一を都合よく思い出したりする…)。
野崎歓東京大学大学院准教授の『赤と黒』新訳が出た時、スタンダール研究者でもないものが、よくもまぁ蛮勇よろしく『赤と黒』の新訳を、と思ったものだが、研究や翻訳の大変さとともに、研究者たちの世界の淫靡な自意識の泥沼と怨念と嫉妬の凄まじさを知っている者として自然に抱いてしまうこうした思いを、さすが、東京大学大学院准教授は難なく乗り越えてしまうものなのか、と感心したものだ。あれだけたくさんの翻訳をし、フランス文学の紹介に活躍している野崎歓東京大学大学院准教授には個人的には敬意を持っているし、ヌーヴォー・ロマン後のフランス現代文学を追うのが専門かと思いきや、十九世紀小説もやっぱり大好きなのか、新訳まで世に問おうとするんだな、とさらに感心して見ていた私は、あえて『赤と黒』を現代小説ふうに軽く読もうとしてみる姿勢を打ち出したことに共感を覚えさえする。ただ、誰よりも思考力が速いと自慢していたスタンダールの文章を、現代ふうのスポーツカーとしてどこまで甦らせられるかを試みるには、やはり、メカの細部もちゃんとしていてほしいというのがスタンダールファン共通の願いだろう。せっかくの訳業なのだから、欠陥車ゆえに幻のモデルで終わってしまうというのでは残念至極というものである。
他方、駒井稔編集長の「当編集部としましては些末な誤訳論争に与(くみ)する気はまったくありません」というコメントには、やはり反対しておきたく思ってしまう。スタンダールは、世界遺産ならぬ、現になお躍動している世界文化なのであり、もちろんすでに日本文化の一部でもあるのだから、誤訳箇所は翻訳者に検討し続けてもらって、今後何年もかけて21世紀前半の決定訳となるものを作っていってもらいたいとでもコメントし直したほうが、出版人としても、会社的にもいいのではないだろうか。これが光文社にとって損になるわけがない。学術書も立派に手がけることのできる出版社として間口を広げていくいい機会になるではないか。 しかし、そう思う一方で、「もし野崎先生の訳に異論がおありなら、ご自分で新訳をなさったらいかがかというのが、正直な気持ちです」という意見にも、同感できないわけでもないところが困ってしまう。外国文学研究者の中には、自分で翻訳もしないで、他人の訳の批判ばかりをして気勢を上げている輩が多い。だったら、自分で訳せばいいじゃん?とつねづね思わされる。訳そうとしてみれば、翻訳には、深い学識や語学力ばかりでなく、自らの文体をたえず作り出し、認識上のあらゆる変貌や修正を受け入れつつもその流れを維持していく力が必要なのが、嫌というほどわかるだろう。そういう力を持っている人が、なんとか今ふうの訳をと頑張っているのを、頭ごなしに否定しなくてもいい。批判は厳密に行わねばならず、しかし翻訳への意欲と実労働は認めねばならず、という両立の構えを周囲が持つようにしないと、大切な外国の著作の翻訳などはなされなくなっていくだろう。大学の先生でありながらあえて翻訳をしてくれるような人たちは、本当なら自分だけで次々読んで楽しんでいればいい境遇にある。批判されたり、いろいろ陰で言われたりするのを覚悟で専門外のものを訳してくれるというのは、生半な自己顕示欲だけでできるものではないのだ。彼らが見せてくれるサービス面は、それはそれとして受け取っておくべきように思う。
翻訳者たちは「だったら自分で訳せばいいじゃん?」という本音をかならず胸に秘めているものだが、それだけでなく、「もともと翻訳なんて無理なんだから、がたがた言うんなら、外国語の勉強をして自分で原文を読んでみろよ」とも思っているだろう。外国の著作の受容に関しては、いかんせん、外国語ができない者は徹底的に分が悪いというのを忘れるべきではない。翻訳を読んでわかったふりをしようというのがもともと安易なのだから、あまり大きな顔をしないほうがいい。ひとつの新訳が誤訳だらけだというなら、スタンダールの原文を読めばいいだけのことだろう。原文というのはもちろん、「読めるもんなら読んでみな」と挑発してくる。ちょっとやそっとのフランス語のお勉強で〝Le rouge et le noir″を読んだら、たぶん、野崎歓東京大学大学院准教授が犯したという多数の誤訳どころでない壮絶な誤読体験が待っているだろう。
そうした誤読体験はいけない、絶対に避けるべし、というわけでもないところに、外国の文芸作品とのつきあいの微妙さというものがある。個人的には、誤読や誤解や誤訳のなにがいけないのか、と思う。それらは、より正しい理解とつねに一緒に存在するものなのだ。どちらかを取り出したり選んだりということはできない。誤読し、しばらくして誤りに気づき、修正し、より注意深くなって正しい読解を進めていけるようになる、――かと思うと、じつはそれらが丸ごと、もっとひどい誤読に陥ってました、などということがあり得る。それを翻訳というかたちでアウトプットしていくとなると、別の言語体系の問題や今ふうの表現の採用にまつわる上限下限の設定作業などが加わってくるから、複合的な能力を同時に調整して発揮していける人でないと、とてもではないがうまくは進めていけなくなる。
私は日本で珍しいシャトーブリアン愛読者でもあるので、その立場から要らぬ難癖をつけさせてもらえば、シャトーブリアン全著作を精読もしていない人がスタンダールに手を出すなどというのも蛮勇極まれりでしょうね、とも言わねばならなくなりそうに思う。十七世紀や十八世紀文学研究者なら、ラシーヌやパスカルやルソーやサン=シモンも極めずにシャトーブリアンを読んだってわかるまいよ、と言うかもしれない。文芸趣味にも文学研究にもこんな底知れぬ泥沼がどの作家や作品の裏にも口を開けている。
この泥濘のどうしようもなさに日々悶々としてもいない人が、今回のような翻訳問題について尤もらしいことを言おうとしてみても、あまり意味はないように思う。本当にスタンダールが読みたいなら、ちゃんと時間をかけて初歩からフランス語を勉強して読んでみるしかないし、それがいちばんいいし、まともな真性の欲望をもつ人はそうする。読んだ経験に照らして言えば、原文のノリはどんな翻訳よりもステキだし、徹底的に突き抜けている。行ッチャッテル。どんなに誤読しつつ読むにせよ、スタンダールの原文を読んだら、他の作家の本を読まずに死んでもいい、というぐらいの充実が得られる。文芸作品の傑作の原文を読むというのはそういうことなのだ。わからないところがあっても、それは原文のわからなさにじかに触れつつ「わからない」ということなので、スタンダールの脳から現われ出たものの裸体に触れているのに変わりはない。翻訳でいくらよく「わかった」ようでも、現実の裸体には一度も触れておらず、あくまでバーチャルな体験に留まる。どんなバーチャル映像を選ぶかとなれば、実物についてのいっそう正確な情報入力によって作り出されるバーチャル映像のほうがいいに違いないが、文芸作品鑑賞の世界では、そういうレベルを一気に踏み越えて実物主義で行くことが万人に許されているし、やる気さえあれば可能でもある。ただし、外国語というのはとにかく思い通りには行かないものなので、難行苦行が続いたり、時間もやたらとかかる。『赤と黒』原文を味読しようとする人には、芥川賞だの直木賞だの最近流行の小説のあれこれを読んだりする暇はなくなるだろうし、なんとかの品格とか最近の日本社会がどうだといった議論にまっとうに向き合う暇さえなくなるだろう。世間一般の人々との話も、どこか噛みあわなくなるだろうし、たまに若者の書いた小説を読んだりすると、「やっぱりスタンダールのほうが面白い。原文だと本当に面白いんだよ、あれ」などと不用意に発言して、なんてスノッブな嫌味なやつ、と思われたりするだろう。
人生、いかに生くべきかという問題が、ようするに、どこまでも追いかけてくる、というわけだ。
ひとつ言い忘れたが、フランス小説の紹介に大活躍の野崎歓東京大学大学院准教授の翻訳本は、じつはひとつも読んだことはないし、買ったこともないので、はたしてノリのいいコクのあるステキな文章家なのかどうか、本当のところはわからない。トゥーサンもギベールもフランス語版をほぼ全部持っているし、それで読んだ。個人的には、どうせなら、正真正銘の大作家フランソワ・ボン、ジャン・ルオー、ウージェーヌ・サヴィツカヤ、クリスティアン・オステルや、日雇い大工などをして細々と生きて早死にした詩人ティエリー・メスなどが、現代作家のうちではもっと紹介されるべきだと思うが、いかんせん、偏った外国紹介の好きな国なので難しいのだろう。クリスティアン・ボバンのある小説をせっかくぶっ飛んだ文体で翻訳したのに、翻訳のぶっ飛び過ぎと「売れそうにないから」という理由とで某出版社から拒否されたのは残念だったが、ボバンの他の著作にはちょっと聖フランチェスコふうの説教臭さがあるので、あれもどうか…、もっとも、宗教っぽいが宗教でないという微妙な清貧路線は、今の時代にはけっこう売れるのではないかとも思うので、出版社には再考をお勧めしたい気もする。
野崎歓東京大学大学院准教授の小説論、というかエッセーのようなものは手にとってめくってみたことがある。紹介文の謳い文句は凄かったが、格別新しいことも書かれていなかったようだし、ページごとの驚き度、新鮮度、意外度、トンデモ度が低かったので、“お買い上げ”とはならなかった。ボルヘスによる文学論やナボコフによる文学講義などの場合は、値が張ってもとにかく買って帰らずにはおれないような気持ちにあやしく心が燃え上がるようなところがあるが、そういうところで比較するというのはやはり酷だろうか。ただ、東京大学の先生たちの文学書というのは、どうもかなり巧妙にヤバイところに踏み入るのを避けており、キレイキレイに教養人の側に留まっているのが見えて、つまらないなぁ、やっぱり、という感じがする。セクハラだのポリティカル・コレクトだのをあちこちで踏み越えるようでないと、じつは今、まさに今、文学論も創作も前へは進まない。中立は消滅し、客観や共通認識の瓦解はすでに周知のことなのに、やっぱり地位と給料は惜しいんだろうね、…などと、私が言う必要もないし、言いたくもないし、べつに言ってもいないのだが、そんな声は聞こえてきそうな眺めではある。文学をいじくるセンセイと文学そのものである人とは、やはり永遠に平行線か……、しかしそれでいて、センセイたちのほうは、いつも高次元に立ってなんでもお見通しのような演技をしながら、生涯収入を確保していこうとするものなのか。いや、なに、べつに批判でもなんでもなく、どんどんヘンテコで面白い、かつ深刻な文芸作品がどんな立場の人からも出てくるようであってもらいたい、との本読み好きのつぶやき。
野崎歓東京大学大学院准教授と、『カラマーゾフの兄弟』新訳を出した亀山郁夫東京外国語大学長の対談を見ていたら、ドストエフスキーが『赤と黒』を読んでいた可能性があるということについて、野崎歓東京大学大学院准教授は「驚愕の事実」と言っている。あれっ?と、ドストエフスキー翻訳本好きなら思うだろう。ドストエフスキー研究者ではないので、どこのどんな本で読んだか忘れてしまっているのだが、そんなことは、もう何十年も前から言われて来ていることではないか。なんで今さら、「驚愕の事実」だなどと言う必要があるのだろう。「いや、これはドストエフスキー学会では周知の事実で、べつに『驚愕の事実』というほどのものではないんですが…」と亀山郁夫東京外国語大学長には言ってもらいたかったところだが、この先生、けっこう、おしゃべりを無理にも盛り上げるのが好きな人なのだろうか。
もっとも、6月20日のネット版産経ニュースに載った亀山郁夫東京外国語大学長「ドストエフスキー余話(5)」を読むと、 《 ―ラスコーリニコフの老婆殺害の場面などすさまじいですね
[亀山] それが文学のリアリティーだと思っているので、私などはそこにフランス文学の物足りなさを感じます。しかし、まだリアルな想像力をもたず現実を完全につかみきれていない若者たちが『赤と黒』を読み、そこに文学的な美のエッセンスとして死のイメージを受け入れる。それはとても大切なことだと思います。
結局、ロシア文学とフランス文学はお互いに補うような関係にあると思います。私自身、ジードやサルトルなどに多くを学びました。
―現在、翻訳されている『罪と罰』の新訳は9月に刊行の予定と聞いていますが、『カラマーゾフの兄弟』との違いをどう感じていますか
[亀山] 物語の完成度という点からいうと断然『罪と罰』が上です。でも『カラマーゾフの兄弟』のほうがはるかに深く、ナゾに満ちている。『カラマーゾフの兄弟』のときは、疑問点などを書いたメモ帳が何十枚にものぼりましたが、『罪と罰』は第1部が終わろうとしているのにたった「A4」1枚しかありません。やはり『カラマーゾフの兄弟』には、有無をいわせない迫力がありますね》
といった発言があり、この先生、なかなか大言壮語の人だなぁ、とわかる。「私自身、ジードやサルトルなどに多くを学びました」なんて、文学研究者も創作家もよう言わんでしょ。ははぁ、そうですか、学ばれたんでございますかぁ、である。もちろんフランス語でですよね、と付け加えると皮肉すぎることになろうか。「物語の完成度という点からいうと断然『罪と罰』が上です。でも『カラマーゾフの兄弟』のほうがはるかに深く、ナゾに満ちている」というのも、いくら新聞での一般読者向けであれ、あまりに粗雑な観念だろう。「物語の完成度」などということを平気で口走れる文学研究者が今どきいるのかということ自体に驚愕するが、一九四九年生まれとまだまだ若いこの先生にしてこれか、と思うと、さらに驚かされる。極めつけは、ラスコーリニコフの老婆殺害場面のような「リアリティー」を持たないフランス文学に「物足りなさ」を感じるとおっしゃっている点。シャトーブリアンの屈指の傑作『ナッチェズ族』や『殉教者たち』の、超絶的ともいうべき残虐場面の連続をご存じないのだろうか。ドストエフスキーというポスト・ロマン主義作家の翻訳をする人が、シャトーブリアンの全小説作品を読んでいないとは! 確かに、日本では翻訳紹介されていないが、我々シャトーブリアンディアンが翻訳したくても、出版社や世間が受け入れないから、いつまでも出せないのですよ。まあ、そのうち、『ナッチェズ族』は私が勝手に翻訳し、メール便で限定発表したりするかもしれないが。
ともあれ、こういったことはまだ、先生がたの個性ということで済ませられるともいえるかもしれない。しかしながら、なんともひどすぎるというべき他のことがある。いろいろなブログを覘いていると、野崎歓東京大学大学院准教授の新訳の誤訳を批判する下山茂立命館大学教授や日本スタンダール研究会を、誤訳部分の問題の実態も知らないだろうに、平然と批判してしまっている人たちが少なくないことだ。同好会ごときがやっかみからイチャモンをつけるな、とか、スタンダールを私物化するなとか、野崎歓東京大学大学院准教授は当然旧訳をすべて参照し研究し尽くした上で新たな翻訳をしているはずなのに、なぜケチをつけるのかとか、ずいぶん不思議な議論が沸騰している。あげく、「当編集部としましては些末な誤訳論争に与(くみ)する気はまったくありません」という光文社文芸編集部・駒井稔編集長の啖呵に、頼まれたわけでもないだろうに、パチパチと賞賛を送ったりしている。それとも、ひょっとして、頼まれているのだろうか。本の広告になるようにと、匿名の著者自身やその知人たちが好意的な書評や賞賛文をブログや新聞や雑誌にばら撒くのはもはや常識となっているが、ひょっとしたら出版社が手をまわして方々に書かせているのかもしれない。
個人的には、下山茂立命館大学教授にも日本スタンダール研究会にも関わりがないが、私物化する意図があって彼らが動くわけはないだろうし、やっかみからの誤訳批判とは考えないほうがいいように思える。わけのわからない部分の多いスタンダールの著作をもっと理解したいと思って、愛好する者同士で意見交換をしているうちに出来上がっていくものが外国文学の研究会で、そこに多少の権力関係なども生じないでもないにせよ、もともとなにが儲かるというほどの会派でもないのだ。このような研究会については、そのように見るというのが常識的な見方というものである。
国際的なスタンダール・クラブには、世界各国のはるかに強烈なスタンダリアンがごそごそと集まっている。そこには、正真正銘のスタンダール命!さんたちがいる。ワケもわからず、あまり理不尽な介入をすると、フランス語でスタンダールも読んだことのないブロガーさんたちは、どんな面倒を背負い込むやもしれまい。シシリーあたりのスタンダール命!さんたちに狙われたら、ちょっと怖いことになるかもしれないですぞ。
――――――――――――――――――――――
『メモとかんがえ』は、ここで終える。先に記したように、配信されなかった文章は多いが、削除すべき表現や伏せるべき固有名詞なども多く、校正は煩雑になり過ぎる。もともと、自分で保存しておくのが第一の目的だったので、ここに掲載しなくても、第一目的はすでに満たしていることになる。
スタンダール誤訳論争についての文の後で書くのもなんだが、『メモとかんがえ』はなんとスタンダール的な試みだったかと思わされる。多くの偽名を用い、奇妙なメモを多量に残したスタンダール。小説創作は、彼の活動のごく一部に過ぎなかった。
2008・07・06