木村恭子詩集『あざらし堂古書店』ノート
たとえば どこか遠い国の磨り減った石畳の街。菩提樹
の並木道をそれたところの路地裏の古本屋。ほら 本棚
の後ろ 壁に挟まれたほんの僅かな隙間にずり落ちてし
まい店の人にも気づかれないで 埃まみれになっている
一冊の本を想像してごらん。(「魚」より)
1 夜町のある場所
『あざらし堂古書店』は、散文詩集。著者の個人誌「くり屋」に98年から2005年にかけて連載された同名の「古書にまつわる詩のシリーズ」(あとがきより)がベースになっている。ここ数年、個人誌「くり屋」の連載を毎号楽しく拝見してきた者として、この単行本化はちょっとした嬉しい驚きだった。さっそく確かめてみたところ、連載の初出では発表順の番号がふられていただけの個々の作品にそれぞれタイトルがつけられ、初出時の作品内容にも手が加えられ、作品の掲載順序にもかなりの異同がある、などなど。いってみれば、個人誌掲載の連作をベースにしながらも、装いをあらたに独立した詩集(作品集)として構成・再編された『あざらし堂古書店』シリーズの決定稿の誕生といっていいのだと思う。
「あざらし堂古書店」というのは、この連作の中の、幾つかの作品に登場する、「夜町」という町に店舗を構えている古書店の名前だ。まず冒頭の詩集タイトルと同名の作品で、読者は語り手の「私」とともに夜町の停車場に降り立ち、この夢と記憶の情景の入り交じったような不思議な町に案内され、町角でリュックを背負って古本を売り歩いている「あざらし堂主人」の姿をみかけることになる。二編目の作品「はじまり」は、店に客からかかってくる電話、三編目の「手紙」は、店に届いた手紙、と、あくまでも古書店「あざらし堂」にまつわる世界が舞台になっているが、四編目の作品以降では、あざらし堂が表舞台から消えて、そういわれれば本にまつわる詩なんだ、と後で気が付くような、多彩な趣向の作品が並ぶ(あざらし堂主人は時々顔をだす)。そして二十九編目に当たる詩集末尾に置かれた作品「おわかれ」で、読者はふたたび、「あざらし堂古書店」の名に出会い、この古書店のある夜町が、「私」(語り手)が子供の頃、夏休みに預けられたおじいさんの住む田舎町の記憶をベースに構想されているらしいことを明かされる。このサンドイッチのような詩集の入り口と出口の配列はとても効果的にできていると思う。
「夜町」が、朔太郎の「猫町」のように空想の町なら、「あざらし堂古書店」もまた架空の店。その店に陳列されている様々な古書も、空想の本、ということで、読者は、こうした舞台装置の中でくりひろげられる古書にまつわるさまざまな詩的エピソードを堪能することができるのだが、その作品の中でどれだけ奇妙なことが書かれていても、また現実の出来事をスケッチしたような作品にであっても、最後まで読み終えてしまうと、これらすべてが、「夜町」という架空の町、作者の記憶の町に起きた出来事のように思いなすことができる。いわばこうした舞台装置の枠組みが、この詩集に収録されている多彩な詩の世界にひとつの奥行きをつくりあげているのだ。ここに記されたすべての出来事は、あざらし堂古書店の本棚に積まれた本のどこかに書かれている物語であり、またその本のある古書店も、その店のある町のことも、やはり一冊の本の中に書かれている。。。この枠組みは持続的に連作詩を書くという意図から発案されたことかもしれないが、結果的に、作者と詩と読者の関係に、ある濾過装置のようなものをつくりあげたり、統一感のあるヴェールのようなものを纏わせることに成功しているように思える。
たとえば、「スドウさん」や「絵本」といった作品は、そのまま作者の生涯の記憶のなかから「忘れ得ぬ人々」の思い出を切り取ってきたように読める生々しさをもっている。以前木村さんの「海馬」という作品について、
「この馬の所作には、ただ過去の記憶(球根)を思い出そうとしている、というより、どこか無くしてしまった大切ななにかを懸命に捜しているような切迫した感じがある。この切迫した、いつくしむような感じを、記憶を素材にした作品の情景に負荷してしまう心の傾きのようなものが、木村さんの詩作品の多くから感じとれる魅力的な特質のように思う。」
と、書いたことがある(リタvol.3 「木村恭子詩集『ノースカロライナの帽子』について」)。うまく言い足りていない気がするが、やはりこの種の「切迫した、いつくしむような感じ」を、作者が過去になにかの縁で出会い記憶にとどめた他者の像にまとわせる、という特徴は、「スドウさん」や「絵本」といった作品によくでていて、そういう意味で、作者が詩のことばで伝えたいイメージの原質的なものがでているように思えるのだが、そういう素材の舞台が、空想の町や本の中に封じ込められることによって、生な体験として語られるのとはまた違った象徴性を帯びる、ということがある。
一見すると「船」や「a trip」といった仕掛けやアイデアの面白さが印象のさきにたつ作品にも、こうした他者の人生に対する著者特有のまなざしがひそんでいるのだが、たぶん、この二種類のタイプの作品のめざすふたつの方向、それを直截な表現(記憶の再現)にむかう志向と、仮構(物語性)に向かうような志向と呼ぶとしたら、「あざらし堂古書店」というこの詩集の舞台装置は、その両者がきりむすぶようなところに、作者の記憶と想像力のとけあった懐かしくて豊かな幻の街の像をつくりあげている、と、いうふうに言えそうだ。
2 居留守屋とは誰だろう
詩集の末尾近くに置かれた「クラバートさん」「居留守」という連作のような二編の作品があるが、その中には「居留守屋」というファンタジックな職業の人物が登場する。この居留守屋は雇われると、人が家をあけて外出する間に、その本人に替わって家に残ってひそんでいてくれる。ひそんでいても、何をするでもなく、ただ、留守の間にその家で起きたことを雇い主が帰宅後に報告する、というのが彼の仕事なのだ。作品に登場するのは正確にいうと「もぐりの居留守屋」であり、その彼に向かって、古書訪問販売人のクラバートさんが語りかける場面がある。
「 ク
ラバートさんは一息置いて 天井を見上げて言う。昨日
という名の家に君が行くからこそ 今日や明日という時
間が確実にやってくるんじゃなかろうか。未来というの
は いつだって過去の居留守をしているようなものじゃ
ないかと思うんだけど。うまく言えないねえ....。でも
どこか僕の仕事と似ていないかと思って。」
「未来というのは いつだって過去の居留守をしているようなもの」という言い方は深淵な考え方だと思う。100年ものあいだ、古書の訪問販売をしているというクラバートさんは、ある意味で、人々に書籍という形の「過去」を売る仕事をしている。居留守屋は、雇い主に留守中に雇い主の住居で起きた出来事「過去」を報告する(売る)仕事をしている。そういう意味では二人は同類なのだ。けれどすこし立場が違うところがある。クラバートさんは、いってみれば「あざらし堂主人」の分身なのだが、このもぐりの居留守屋は、たぶんこのちょっとユーモラスでファンタジックな連作詩の中に、作者がそっとひそませた自らの詩意識の分身なのだ。
居留守屋は正確にいうと、「昨日という名の家」に行くわけではない。雇い主に向かって、雇い主が不在だった場所の過去(昨日)の出来事を報告するだけなのだ。けれど、雇い主にとっては、その事実は過去(すでに起きてしまったこと)として知らされるしかないから、自分が不在だった「昨日という名の家」を訪ねるのと同じ意味として受け止められる。そしてそのこと(過去になにがあったかという事実)を知る、ということは、雇い主の今日(現在)に属している。
ところでこの作品には登場しない居留守屋の雇い主とは誰なのか。それはまず第一に作者であるとはいえるだろう。想像をたくましくしていえば、居留守屋というのは、作者(雇い主)にとって、自らの過去の記憶を呼び起こす意識のはたらきそのものを意味しているように思える。そこで注意すべきなのは、彼(居留守屋)が、その過去に積極的に関わる存在ではないということ、ただ事実の観察者であり報告者でしかない、という性格付けにあるように思える。そうしてその観察、報告を通して、たとえば、その家に、かって「スドウさん」や「絵本」に登場する女性のような、訪問者がいたことを、雇い主に想起させる。スドウさんや、「絵本」に登場する女性は、ふつう人々が人生のある局面で出会い、深い交際もなく自然に縁が遠のいてしまったような、忘れられてしかるべき人々のように描かれている。それが彼女たちの残した幾つかの印象をもとに、遠い記憶の層から、ある個性のたたずまいとして呼び起こされている。居留守屋という作者の内面に住む「詩意識」によって、そのことが実現されたとき、雇い主(作者)は、たぶん、自分がある生の局面で、スドウさん(たち)でもあり得たことを確認している。わたしたちの生そのものが、存在から自意識をさしひいたような不在の視点(未来)から現在をみること(詩意識的な視線)によって、その実相がみえてくるような構造をもっているのではないだろうか、と。そうしたとき、雇い主とは誰か、という問いはまた、雇い主とは、あなたであり私でもあるような人の場のように、読む者に受け渡される。
3 収録作品「天使」について
天使
その本のどこかに わたくしの子供の病気の名前が書い
てあるはずです。ずっと前に一度だけ わたくしはその
本を読んだ事があるのです。変ですね。その時 ああ
この病気のことならよく知っているという気がしたのを
覚えています。わたくしの子供の 今の症状とそっくり
な病気。発病の時期も同じです。子供の場合は冬の終わ
り 風の傾斜が急に緩やかになる日です。
その年の冬は気が滅入るほど長いものでした。わたくし
にとっては 住み慣れた南の町を離れて初めての土地。
早口で話される強い方言を理解できず 毎日子供と二人
で部屋に閉じこもって過ごしました。かくれんぼをよく
やりました。子供を鬼にしてわたくしが隠れます。わた
くしは色んな所へ隠れたものです。貧しい娘が かきつ
ばたの花群れの中で 赤ん坊を産み捨てる小説の 谷沿
いの春の村にも行ってみましたし 眠っているようなお
婆さんが 真っ黒い包丁で一日中ラッキョウの根を切り
取っている 夏の海辺にも行きました。 部屋に戻ると
子供は縫いぐるみを抱いて炬燵にもぐり込み 涙ぐんで
眠っていることもありました。それでも次の日又 わた
くしは子供を鬼にして まーだだよ まーだだよ と言
いながら どんどん部屋から逃げていったのでした。
ある日 いつものように戻ってみると 子供がいないの
です。わたくしは夢中で探しました。近所は勿論 雪に
閉ざされた商店街の一軒一軒をも。警察にも届け ヘト
ヘトになった心と体で何とか家に辿り着きますと 子供
が玄関に立っているではありませんか。おかあさん 変
なんだよ あたしがどこにもいなくなるよ。----それが
最初でした。
戻って来るために去っていく準備を 冬鳥が始める日
あの子は病気になります。お医者さんは貧乏揺すりをし
ながら しばらく様子をと言います。でもわたくしは
思い出したのです。確か表紙に 天使が飾り紐のついた
ラッパを吹いています。ええ 幼い日に読んだ古い本。
その本のどこかに 子供の病気の名が書いてあります。
わたくしはそれをどこかで一度だけ 読んだことがある
のです。
小説・田中澄江著「かきつばた群落」
詩「天使」全編をあげてみた。春先のある日、神隠しにあうようにふっと子供がいなくなる。それが病気だといえるのは、それがいなくなる子供自身にとっても「あたしがどこにもいなくなるよ」という不都合な異変のように感じられているからで、子供の母である「わたくし」は、そのことを「体が透明になる病気」のように考えて医者に相談し、かって何かの本でその病名について読んだことがあるのだが、という気がかりを、読者にむけてうち明けている、という構図になっている。とても奇妙な味わいのある優れたできばえの作品だと思う。体が、そして存在そのものがなくなる病気。これは直接は子供の死を暗示しているが、ファンタジックなことには、これは春先にかかる一種の流感のようにみなされていて、以前にも、子供が一度かかったことがあり、その後で、ふたたび家に戻ってきたことがあるように言われていることだ。
ところで、この作品にはもうひとつ別の奇妙さがあって、それがすぐれた批評性を宿しているということがいえそうだ。というのは、子供がきえてしまう、という病気の本当の原因が、母親の行動にあることが暗示されていて、そのことに母親自身が気付いていない、というふうになっているからだ。要するに、子供を「鬼ごっこの鬼」にみたてて、ゲームをしていると偽り、実際には子供を置き去りにして家庭から逃げ出してしまう「わたくし」は、その当然のむくいのように、子供の側の存在を否定された心情(母親にみすてられて、生きる力が損なわれたような状態)によるゆりかえしを受けている。この「わたくし」は、自分では子供と「鬼ごっこ」をしている、と信じこむことで、そこに自分は別に子供を見捨てているのではなく、一緒にゲームをしているのだという主観的な自己合理化像(言い訳)をつくりあげている。ところが、実際に彼女が家をでてさまようのは、「貧しい娘が かきつばたの花群れの中で 赤ん坊を産み捨てる小説」の舞台だったり「眠っているようなお婆さんが 真っ黒い包丁で一日中ラッキョウの根を切り取っている 夏の海辺」だったりする。そのどちらの場所の情景の描写にもこの母親の我が子の存在を否定したい無意識の要求が、よく暗示されているように思う。実際に子供がいなくなってみると、この母親は、「わたくしは夢中で探しました。近所は勿論 雪に閉ざされた商店街の一軒一軒をも。警察にも届け ヘトヘトになった心と体で何とか家に」辿り着く。つまり意識のうえでは、まったくの善良な母としてふるまっているのだが、自分のしてきたことにまるで気が付いていない、という奇妙な構図になっているのだ。
この母親は、今度は子供を永久に失ってしまうだろう。と作者は書いていないけれど、この構図が読者だけに読み解かれるとき、たぶんとても現代的な悲劇のモチーフがここに潜められていることがわかると思う。
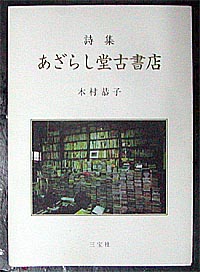
木村恭子詩集『あざらし堂古書店』(三宝社 2005年8月1日発行 1500円)