足立和夫詩集『暗中』について
足立和夫さんの詩の多くには、自分がこの世界に在る、ということや、この世界が世界として在る、ということ自体についての、深い驚きをともなう関心が息づいている。この「存在」ということをめぐる関心が、あるとき、詩のことばとして、現実の意識の表層を食い破るようにあらわれてきた。足立さんにとって、自ら詩を書くということとの出会いが、そのような事態の内的な発見であったことを、前詩集『空気のなかの永遠は』の「あとがき」が伝えている。
「初めて書いた詩も収めた。
「眠る部屋」がそうである。初めてことばが私を掴まえたリアルな詩であった。
ことばが私を絡めるように捕らえて書かれ、救われることがあることを知った詩であ
る。ふしぎな体験だった。まるで、生きて存在することの向こう側が裏返って見えた
ような気がしたのだ。
しばらく忙しい日が続いた。
その日常のなかで、あの体験の感覚の跡をいつしか追い始めていた。なんだか不幸に
なるように思われたが、追う姿勢が自分の姿なのだと思い込んだ。あの感覚こそが、
この世の鍵なのだと信じていた。
しばらくのあいだ、空をもがいた。
ときには現実の底に沈む永遠に近づいたと思うことがあった。
永遠ではなく無だったのかもしれないが。」
(詩集『空気のなかの永遠は』あとがきより)
詩集の略歴欄を対照すると、詩「眠る部屋」が書かれたのは1988年のことで、1951年うまれの作者が、37歳の時にあたる。あとがきの文章は、こうした詩作との初めての出会いが、当時の足立さんにとってどれほど衝撃的な意味をもったか、ということをあますことなく伝えていると思う。
眠る部屋
歪んだ(会社)のなかで、不意
に犬のような沈黙を口に押しこめ
られた男は、夕暮、痙攣する肩を
抱え、部屋のおくへ潜っていく。
床に転がった身体を覆うように、
いつのまにか、(部屋)の呻く声
が、冷蔵庫の辺りから滲み出て、
・・・その死体の怠惰を病気のよ
うにくぐりぬけていく。
そして、まどろむ朝を掴み、死
体を模して起きあがる振りをする
者が、当てにならぬ彼方を目ざし
部屋の夢を後にする。
この「眠る部屋」という作品は、作者にとって、いわば当時の作者の生活総体を対象化したような意識の内景の発見というような意味を持っていたように思える。日々会社に出勤して仕事を終え、帰宅して眠りにつく、そう言ってしまえばそれで足りてしまうような平穏な繰り返しの日常。そのように暮らしている「男」=自分を、そうした「事実」を重ねる日常の言葉でなく、ある他在とでもいうように、「存在」という詩の言葉のレベルでとらえること。そうすると、「男」は、「自分」という枠から抜け出して、任意のだれかに重ねられ、さらにいえば、人という枠さえはなれて、不可避な日々のなりわいの繰り返しという「永遠」のなかで、理由もなく生きる=在ることを強いられている「存在」のかたちに重ねられていく。そのことが、哲学書から借りだしたような抽象観念からやってくるのでなく、職場で強いられる不本意な沈黙や、暗いマンションの部屋の空気や、冷蔵庫の低い唸りや、窓から差し込む朝のひかり、といった生活を囲繞する肉感的な事象の体感から、言葉として訪れてきたところに、たぶん詩としての実質がおかれている。
この作者の第二詩集にあたる『暗中』もまた、前述のあとがきの言葉をかりれば、「あの感覚こそが、この世の鍵なのだ」と信じて、「あの体験の感覚の跡」を追う、という、確かな持続の成果なのだ、といっていいのだと思う。
暗中
暗く輝く舗道に
群れるひとの息
灼熱から遠ざかるからだに
ひっぱられ
脇道にそれて
ひんやりする暗がりに
肩を入れる
夜に流れる
うすい闇は
底なしだ
ぼくは冷たい空気のなかを
ことさらゆっくり歩く
いつでも闇は
孤独を新しくして
逃れられない人生を
葬るようにみえる
死は謎のように
いつもそばにある
ぼくは闇に溶けていく部分の
ひとつなのだろう
その冷徹な想いは
静かにあたりまえのように
からだじゅうに届いていく
反転することのない暗黒の奥底で
怜悧な星たちはみずから爆裂をつづけ
とてつもない大きな沈黙を
苛烈な天空に解き放ち
光の束とともに
ぼくを襲撃しつづける
逃れることはできない
詩集『暗中』には、夜や闇が登場する作品が多く収録されている。そうした言葉が登場しない作品にも、闇や夜の気配が漂っているように感じるのは、作者独特の闇や夜への親密感のようなものが、主調音のように流れているからのようにさえ思えてくる。この表題作「暗中」は、作者のそうした闇の世界への心の傾斜のありさまをそのままテーマにしている。都会の繁華街の雑踏をのがれて、林立するビルの落とすおぐらい影に閉ざされている脇道にそれる。自分が「闇に溶けていく部分のひとつ」である、という(いつもの)死の謎をめぐる想念がやってくる。その想念は、作者にとって、もう何度も反芻されて、なれ親しんだ体感のようなものになっていることが、「その冷徹な想いは/静かにあたりまえのように/からだじゅうに届いていく。」という詩行であかされている。後段の宇宙的な広がりを感じさせるビジョンは、作品に鮮やかな彩りをそえているが、ここで唐突なイメージの飛躍が行われているわけではない。この天体の光芒をはるかに仰ぎみたようなビジョンが、闇に消えていく自己存在、というイメージが招き寄せる、これもまた作者にはなじみのあるビジョンであることが、詩集の冒頭におかれた「序詩 目撃」という作品で明かされているからだ。
序詩 目撃
天の深い闇が
はじめて火傷を負ったのは
いつのことなのだろう
夢みる人間どもは
それを星の光と呼んでいる
烈しく焼きつくそうとする巨大な炎
無限の火傷の痕を
膨張する闇はゆっくり呑み込んでいく
人間どもはいずれ消えるだろう
いつの日か太陽系が銀河の中心にある巨大なブラックホールにのみこまれていく、というような説を想起しなくても、ここで予言者ふうにいわれている人類の滅亡が未来に確実に実現する、という世界像は、だれも疑いえないこととして、自然科学を奉じる現代人の認識を規定している(たとえば太陽の寿命は約100億年とされ、人類が誕生するまですでに45億年が経過している。この地球上が、生物が住める環境にあるのはあと20億年ほど、という天文学者もいるという)。ただ日々を様々な事象に遭遇し対処ながら生きているという実感からすると、こうしたビジョンは、あまりに現実感覚から遊離していて、ことさらに思いあぐねてもしかたのないことのように思われている、とはいえるだろう。しかし、世界=宇宙とは本来暗黒であり、やがてすべてがその暗黒に呑み込まれていき、自分もまたその闇のなかに溶けるように死んでいく、なぜか理由もわからないまま、そういう世界に自分がおかれている、というイメージは、もし、たちかえる、という契機さえあたえらえるとするなら、逆に常に新しくこの世界に生きてあるということの意味を謎として問い返してくる、と言っていいのだと思う。
失業中のマンションの自室で、ラーメン屋のカウンターで、通勤電車の車内で、地下の喫茶店で、、、詩集『暗中』には、日常世界のありふれた受感にふれながら、その受感をスライドさせるように存在の意味を問う、といった作品が何編も収録されているが、この問いかけには答えがない。「思うに「存在の謎」の最大の特徴は、答えが絶対にないということにつきる。最近は、そんなことに思い至っている。」(『暗中』あとがきより) だがもちろん、答えがないから問いそのものが無意味である、というふうな形で、この存在をめぐる謎があるのではない。作者がこの問いを持続するのは、たぶん問いかけがもたらす認識によって精神のなにかが救済され、深く生きることができる、という確信を、書くことの持続そのもののどこかで体感したからのように思える。それはたぶん世界に対する驚きに言葉をあたえたい、という、書くことの根源の欲求にかかわっていて、作品を読む者にもまた、暗い夜空のなかに明滅する孤独な光をみつけたときににた共感や慰めをあたえる、といえるのかもしれない。
アスファルト
コンクリートの部屋の
ドアノブをひねり
押しあけてそとに出る
湿った薄暗い廊下
頭をゆっくりまわし
天井のようすを見た
いく本か蛍光灯が切れている
一本は切れそうな音と光が
小さな炸裂を繰り返している
孤独な悲鳴だ
そのうち静かになる
いつものこと
気にすることではない
そのまま放って
曇天の外気のなかに溶けて
アスファルトの湿った黒色に
眼を落とす
泡立つ景色の意欲が
だんだんと収まり褪せる
残りをコンクリートが
削る
それでわかった
ぼくは
ひとのたましいを
背負うことができないことが
地面に横たわっている
コンクリートの重量で
湿った空気にくるまれて
うずくまって
囁く
昏い沈黙に降りて
姿を消す人よ
あなたがたこそ
ぼくなのだ
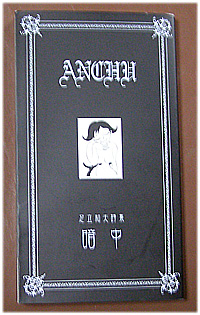
足立和夫詩集『暗中』(草原詩社 2006年8月20日発行)