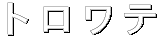 45
45駿河 昌樹 文葉 二〇〇七年十月
トロワ・テ、Trois thes。仏語で「三杯の茶」。筆者居住の三軒茶屋は三茶と略称される。
すなわち、トロワテ。ひたすら、益体もない文章のために。
長尾高弘さんの『人類以外』
長尾高弘さんから新詩集『人類以外』*1が送られてきた。彼の詩はいつもユーモアが際立っているが、今回も楽しい。なかには、それなりにシリアスな心理状態や困っちゃった経験から出てきているらしい作品もあるが、最高の「参っちゃったね、こりゃ」体験が最高のユーモアを香らせるところが長尾詩の真骨頂。手にとって一息に読んでしまえる詩集なんて、けっこう少ないものだが、彼の詩集を一気に読まなかった経験は、ぼくにはない。
いつも思うが、長尾さんの詩には、読者に格差をつけない優しさがある。おまえは現代詩読んできたか、こんなのは難しくてわかんないだろ、どうだ?…みたいに喧嘩を吹っかけてこない。長尾さんがどれほど頭脳明晰か知っているので、やっぱり本当に頭のいい人は、あらゆる種類の読者にたいして優しくなれるんだろうと思う。羨ましい優しさだ。
ちょっと前から、現代の詩の本当の焦眉の問題は、詩なんてふだん読まない人たちにどれほど届くものを書けるか、それでいて、自分が書きたいものを素直に出せてもいるか、ということになっている。じつは、たくさんの人たちが、質のいい詩につぎつぎ触れたいと感じている。それなのに、いわゆる現代詩のなわばりの中に居る人、居たい人、もぐり込んで次の時代のお山の大将になりたがっている人たちが、これでもかという脳内トレーニングをぶつけてくる。おかげで、現代詩はすっかり捨てられた。ろくなマーケットも、もう存在しない。小出版社は、詩人の成りたがりさんたちに吹っかけて詩集を作らせ、それで儲けているようす。読者から金を取らずに、著者から金を取る。どちらからであれ、金が入れば売本業者はかまわないらしい。いっぽう、現代詩さんというレトロさんたちは、世間から捨て去られた後で、読者たちのレベルが下がったとか偉ぶっている。でも、偉がっていても、もう誰も読まないですから、って感じ。こんな現代詩に誰がした、なんて、問うだけでも盛り下がる。わからないことを書く→偉がる、という構図は、ほんと、文芸の世界ではタチが悪い。
こういうマズイ回路をしっかりと逸れているというのが、長尾さんの詩のとっても気持ちのいいところだ。ひとつの作品に入り込んで、また抜け出ていくまで、読者にはよけいなストレスがかからない。なめらか、スムーズ、すらすら読めて、作者の体験も、内的体験も、感情も、思索も、当面の結論と決意までしっかり入ってきて、「うん、面白いこと書く人だな」と腑に落ちる。ブローティガンとか、プレヴェールみたいな人が、こんなタイプの詩人だったなあと思いながら、長尾さんがこの現代にあって、他ならぬ日本語で書いてくれていることに幸せを感じるのだ。
詩人ってどんな人かというと、やっぱりその時代のスタンダードな言語表現を控えめに見せつけてくれる人なんだと思う。その人の詩を開けば、ああ、こういうふうに書いたらいいんだ、と安心させてくれる、そんな人が詩人なのだ。長尾さんにはそういう安心がある。
生活の中で、というより、生活の中の心や頭は、いろいろとまとまりづらいことを感じ、考え、そこに体調の良し悪しが加わり、だんだん老いていくんだなあという慨嘆も出れば、ちっぽけなことや大きなことでの運の良し悪しへの気持ちの反応も加わって、いつもシュトルム・ウント・ドランクしている。そういう心や頭が詩を欲しているのだが、そこに長尾さんの詩は効く。彼の口調は、まるで最高度にすらすらと言葉が流れる時のようにとぅるとぅると饒舌っぽいが、それが効くのだ。おしゃべりのようだなぁと思って読んでいると、実生活から幽体離脱しながら、いかに実生活を料理しやすく眺めるか、その術がこちらにインストールされる仕組みになっている。人間が生きるとは、人間の思考が生きるということなのを長尾さんはよくわかっていて、その思考の部分にとってもよく効くのだ。ぼくらがふだん、振り返らないで使っているおかげで、いろいろと苦労や苦しみをそこから被っている自分の思考について、ちょっと使い方を変えてみる、反省してみる、ということが、長尾さんの詩を読んだ後では確実に起こる。それほどのものを、まぁ、なんとすらすらと書いちゃっていることか、と感心させられる。
たとえば、『意思表示』というこんな詩。
テレビも、
買ってから二十年もたつと、
意思を持つものらしい。
指示されたわけでもないのに、
自分の意思で消える。
といってもできるのはただそれだけで、
勝手についたりはしないのだが。
疲れたから休みたい、
というほんのささやかな意思表示。
それができるようになるまで、
人間ならどれだけかかることか。
これで全部。なんというスムーズさだろう。読むのに、なんのひっかかりもない。すらすらすら、なのだ。気持ちいい。詩なのに、読めるぞ、これ?!なのである。どの行にも句読点がしっかり付されていて、ちょっと気が変われば文になっちゃえるよ、なっちゃおうかな、まだ止めとくか、といった形式の揺らぎもうれしい。ぼくが文部科学省の詩歌課課長だったら、詩歌奨励賞を特別に儲けて授与したくなるような詩だ。
もちろん、ただの「すらすらすら」ではない。長年使ってきたテレビの不調を「意思」と見たてるムリのない楽しさから始めて、人間がテレビ以上に「意思表示」を許されない状況に追い込まれている現代を、言い過ぎず、やわらかく、温かく描いている。最後の二行など、切実で悲しくもある。それでいて、全体の口調はもたれず、あっさり、さっぱり。言葉にしていないことがいっぱい伝わる書き方になっていて、こういうものに出会う時に、詩人って、こわいなぁ、とぼくは思う。
この詩に出てきた機械と人間の問題は、どうやら長尾さんの意識に大きく引っかかっているようで、『人間機械論』なんていう文字通りの詩にも、ぎりぎりのところで深夜バスを逃した話の『運送業』などにも出てくる。他の詩でも、じかに機械が出てこなくても、人間の行動や思考や感情が機械のようになってしまっていること、なってしまう時などへのまなざしは共通している。しかも、たんに人間の機械化を批判するというような、すっかりインパクトの失われた紋切り型の指摘などしない。こんな驚くべき、微妙なことを言うのだ。
オイルが切れちゃったのか、
どうも関節がうまくまわらなくて、
とか、
どうも水道管がさび付いてきて、
出が悪いんだ、
などといったことを口にすると、
ああ、
無意識のうちに、
身体を機械にたとえてしまったな、
と思う。
(『人間機械論』)
人間の比喩行為はもっと根源的に批判されないといけない、とぼくは思っているのだが、長尾さん、はっきり言うよなぁ、と此処を読むと思う。無批判に用いられがちな比喩思考を、彼はいきなり俎上に上げてくるのだ。こういう思考が悪いなどと言えるほど、人間の思考は自由ではない。正直言って、どうにかこうにか、なんとかやってきたんだよね、という感じなのが、人間の知的営為というものだろう。長尾さんは、非難しているのではない。こういう比喩思考でやっていく以上、行きつく先は、やっぱりそれなりのものだってことにはなるだろうね、それは避けられないと思うな、と、当然の覚悟を持つよう人類につぶやいているのだ。人類はいつも、ぼくら自身の思念の中にいる。
もちろん、彼が比喩行為の大家だからこその、こうした指摘なわけで、『ものづくし』になど、いかんなく彼の能力が発揮されている。
本
狭いところに集められ、
縛り付けられている。
逃げたくならないのだろうか。
それとも、
好んで集まってきている、
ということになっていて、
逃げたくても逃げられないのか。
いずれはまとめて捨てられる運命なのに。
マグカップ
一つしかない耳で、
あまりにも多くのことを、
知ってしまった。
大きく開いた口は、
ふさいでおかなくては。
サンドイッチ
足を伸ばして寝ていたら、
ふとんごと食われてしまった。
鉛筆
身を削らなければ、
無用のものだが、
身を削りすぎても、
無用のものになってしまう。
必死の思いで、
生きた痕跡を残そうとしても、
いとも簡単に消されてしまう。
消しゴム
まちがえるとか、
考え直すとか、
そういうことがなければ、
まったく不要な存在。
でも、
不要になる気配はない。
あれば形を変えたくなる。
トースター
さっきは怒りすぎた。
炭にするつもりはなかった。
頭を冷やすと、
残るのはいつも後悔ばかり。
蛇口
あふれる思いを、
内に秘めている。
思いがあふれ出しても、
時が来れば、
きっぱりと口を閉ざす。
口を閉ざしているからといって、
思いがないわけではない。
窓
この通路はしょせん一方通行なのであって、
外からの働きかけを断固としてはねつけるのだが、
なまじ外が見えているような気がするもので、
そうだということを断固として認めない。
柱
考えもなく立っているわけはないはずだが、
考えもなく立っているように見える。
鏡台
自分では、
瞬くこともできないけれども、
その瞳に映る景色は、
奥深く、
物悲しい。
テレビ
柱に降臨した神が、
糸をつたって屋内に入り、
箱のなかに流れ込んで、
あられもない姿を現した。
全編を引用したが、それというのも、この『ものづくし』がどれほどの名作かを確認したいからだし、知ってもらいたいからでもある。「現代詩」なる過去のブランドの威光を脱ぎ捨てて、このように知的で温かなわかりやすい日本語で、無駄な装飾も不快な気負いもなく、完璧な作品ができたことに、ぼくは素直に脱帽したい。書かれて間もないのに、この詩はすでに平成の古典というべきものになっているのだ。
自分が書いたものでなくても、また、自分に書けなくても、いい作品に出会うと、自分の核心が永遠のものになったように感じる。それが詩歌好きの人間というものだろう。この『ものづくし』といい、長くなるので此処には引けない他の作品といい、平成十九年前後をただの日本人として生きているぼくの気持ちを、長尾さんにはすっかり書かれてしまったな、と感じる。
詩とはこういうものなのだ。
もうぼくは、なにも書かなくていい。もういいのだ、と、本当にさっぱりした気持ちに、いま、なっている。
「ぼくの声が聞こえる」……
かつて彼が記したこの言葉、ぼくの心に消えない痕跡となった言葉は、たしか詩集『長い夢』*2の中のものだったと思うが、あるいは詩集『イギリス観光旅行』*3の中だったか、それとも詩集『縁起でもない』*4の中だったか。
最新の詩集『人間以外』を読みながら、ぼくは、「ぼくの声が聞こえる」と随所で感じ続けていた。「ぼくの声が聞こえる」と感じさせるものだけが詩。長尾さんはこれから、いっそう「ぼくの声」を響かせていってくれるだろう。
つまり、下らない詩作のまねごとをして、ぼくが「ぼくの声」を書きつけようとする必要など、もうないということだ。
ぼくはもう終わってよい。
もう、なにも書く必要はない。
*1 長尾高弘『人類以外』(株式会社ロングテール、二〇〇七年十月二十日発行)
*2 長尾高弘『長い夢』(昧爽社、一九九五年)
*3 長尾高弘『イギリス観光旅行』(昧爽社、一九九六年)
*4 長尾高弘『縁起でもない』(書肆山田、一九九八年)
*詩集『人類以外』を希望される方は、著者・長尾高弘氏に直接連絡されたい。
電話〇四五―五九〇―一五四六。〒224‐0023横浜市都筑区東山田三−二六−一六。