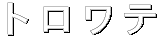 82
82駿河 昌樹 文葉 二〇〇八年九月
トロワ・テ、Trois thes。仏語で「三杯の茶」。筆者居住の三軒茶屋は三茶と略称される。
すなわち、トロワテ。ひたすら、益体もない文章のために。
■SURUGA’S詩葉メール便・編集贅言集17
[第一五八号〜一六一号・二〇〇八年七月二十四日〜二十七日]
第一五八号(二〇〇八年七月二十四日)
炎天下、都内を歩いてどれだけ早く移動できるか、考えている。
しかし、条件付き。排気ガスでいっぱいの幹線道路はなるべく避けて、裏道を歩き継いでいくということ。
きのうは三軒茶屋から新橋までを1時間半ほどで歩こうと意気込んだが、辿る道の選択をなんども失敗し、渋谷までで止めた。途中で、地図を買うためになんどか書店に入って検討したり、近くまで来た神社にわざわざ長い石段を上がって詣でたりして、だいぶ時間をロスした。いちばん辛いのは、近道できるだろうとあたりをつけて、長々と辿った末に行き止まりになっている細道。それをぜんぶ戻って他の道を辿りなおさねばならないが、次の道も行き止まりだったりということは、東京の裏道ではけっこうある。
三軒茶屋からは、うまく辿れば、池尻大橋あたりまで15分から20分ほどで出る。もちろん、246号線をそのまま歩けば10分で行くのだが、これは条件を逸脱してしまうので採用できない。この区間の裏道はまことに入り組んでいて、しかも、行き止まりが多く、なかなか難しい。なんども歩いたが、しばらくすると忘れていて、なんどとなく同じ迷路に引っかかってしまう。しかし、太子堂2丁目から三宿1丁目にあたるこの地域は、お年寄りが多かったり、家の建て直しを容易にできるほどの余裕のある世帯が少ないからなのか、ちょっと前の雰囲気の三軒茶屋が残っている。のんびりと散策するには、けっこう楽しい地域ではある。猫も多い。
辿る道の都合で、どうしても池尻大橋駅のところでは246号線に出ないといけない。これを避けようとすると、30分以上になりかねない大きな遠まわりをすることになる。この馬鹿げた遠まわりを、きのうはやってしまった。目黒川緑道のところには大きな断層のようなものがあり、池尻3丁目側から見ると、池尻4丁目や三宿2丁目が城砦のようにそそり立って見える。この上下のふたつの地域を容易に往復できると思ったのが間違いだった。
いったん、素直に246沿いのスーパー丸正前の繁華街に出てそこを通過し、東邦大学大橋病院の坂を大橋図書館側に登り直し、まっすぐ進んで淡島通りの松見坂に出るのがよい。そこで山手通りを渡り、三角地帯を突っ切って、さらに旧山手通りを渡り、神泉駅入口とある道に入っていく。ここは神泉町で、そのまま進めばラブホテル街で有名な円山町に入り、すぐに渋谷の道玄坂に抜ける。
池尻大橋駅から道玄坂までは、遠いような印象があるが、ぼくの足で10分から15分。歩くべき距離といえる。しかも、神泉町から円山町のあたりは、東電OL事件の頃のバブルの裏返しのような暗さとはだいぶ様変わりしており、癖や主張のある飲食店などが多く出来始めていて、冷やかして歩くには面白い。日が暮れての帰り、昨夜もこの道を逆に辿ってきたが、居酒屋やレストランやカフェなどのメニューをいちいち見て来た。ある居酒屋では、日本酒の地酒を五種類選んで飲めるという聞き酒コースが1000円だったが、ひとつひとつの量がそう多くないとしても、けっこうお得ということになるのではないか。
円山町を男がひとりで歩いたりすると、娼婦が声をかけてくるのではないかと思う人がいるかもしれないが、あのあたりではそういうことはない。むしろ、表通りの道玄坂のほうに娼婦たちは散見される。以前、そう馴染みのない赤坂に夕方に行った時、あまりに娼婦が多く、しかも美人の外国人女性が多く、文字通り左右から袖を引いてくるどころか、腕をこちらの腕や腰に早々とまわしてさえ来るのに驚いたことがあるが、道玄坂はそれほどではない。行き交う人でいっぱいの歩道の脇や街路樹の下に立って、客が寄ってくるのを待っていたり、時には声をかけてくる。東京の娼婦たちの特徴は、服装がやけにサッパリしていて余分な装飾を一切つけていないことだが、ゴテゴテと安手の装飾をぶら下げる傾向のある昨今の素人娘たちとの差は、かなりはっきりと現われる。
ともあれ、三軒茶屋から渋谷まで、うまく道を選んで最短で行ければ25〜30分ということがわかったので、六本木、新宿、五反田などは計算上は1時間から1時間半の範囲ということになる。六本木や表参道から三軒茶屋まで幹線道路を歩いた経験はあるので、実際上もほぼそんな時間になろうか、という予想はつく。
理想は、日本橋の丸善まで2時間ほどで歩いていって、ちょっと銀座を歩いてから、また2時間ほどで三軒茶屋まで帰ることなのだが、まぁ、そう遠くないうちにやるかもしれない。もちろん、熱中症などにならないように、いざという時にはすぐに中止できるようにする。そのためには、歩くという方法はいちばんいい。自転車だと、途中で放り出しづらいので、かえって無理してしまうかもしれない。大橋や円山町の坂の上り下りを自転車でこなすのも、かなりハードに違いないだろうし。
こんな炎天下の歩行が可能になるのも、汗の吸収と早乾に優れた新素材のスポーツTシャツを着ているおかげだ。コットンのシャツなら、びしょびしょになったまま乾かずに疲れ切ってしまう。このTシャツだと、リュックサックの肩掛け部分が汗を吸って濡れてしまうぐらいになっても、ボディの部分は不快にならない。
こんな素材でビジネススーツやワイシャツも作られれば、勤め人たちはよほど楽になるだろうに、と思う。役人や政治家が、クールビズだと言ってノーネクタイでワイシャツを着ていたりするが、夏になるとほぼ熱帯になるこの列島では、まずヨーロッパ由来のワイシャツのかたちやスーツを禁じるぐらいのところから発想しなおさなければ意味がない。なにをやるにも、この国はradicalラジカルでない。ラジカルでないということが、なしくずし的に確実に社会の命を奪っていく。そんなところが、生まれつきのジャコバン主義者であるぼくなどには苛立たしい。
ハワイのアロハやインドネシアのシャツなどのかたちを参考にして胸元の深く開いた形状にし、素材を汗の吸収と早乾に優れた新繊維にすれば、人々の夏の不快度はぐっと減るだろう。ついでに、黒やグレーや薄茶や濃紺や深緑などの盛り下がる色を禁じるのもいい。うるさいまでの総天然色で装う熱帯列島になっていけば、この国の未来はまだ可能性がある。ボスであるアメリカなどは毎日がひな祭りみたいにあんなに色彩豊かだし、この先、どんどんと国が斜陽になっていくのなら、そうだ、キューバになっちゃおう、という手もある。
第一五九号(二〇〇八年七月二十五日)
きのうは、おととい辿った三軒茶屋ー渋谷歩きコースの復習にくわえて、ついでに、表参道から外苑前まで歩いてしまった。道玄坂から渋谷駅まで出ると、表参道などは目と鼻の先である。ただ、坂を上らねばならず、三軒茶屋から歩いてきた足には楽ではない。こどもの城や国連大学や青山学院大学のかたまっているあたりに来ると、ちょっと景観が華やかになり、いろいろな渋い路地を歩いてきた目には楽しい。それに助けられて進む。
三軒茶屋からのルートもまだ決定版を選定するにいたっていないし、路上のあちこちにぐんなりして寝っ転がっている猫たちにちょっかいを出したり、写真を撮ったりして歩くので、ロスタイムもかなり多い。それでも、50分ほどで外苑前のベルコモンズに着いた。
きのうはナイトウォーク。夜の7時に出発して歩き出した。照りつける太陽はないし、空気には涼しさがある。しかし、歩き出すと、絶えることなく汗が出続ける。スポーツTシャツを着ているとはいえ、ちょっと胸のあたりに触ってみると、液体がじとっと手につく。乾く暇もなく汗が出続けているので、つねにシャツが濡れている状態だ。しかし、汗が出続けているかぎりは冷えることはないので、とにかく止まらずに歩き続ける。
せっかく来たものの、渋谷から表参道・外苑前までは、裏道をさがすことなく、宮益坂から青山通りをそのまま辿った。裏道主義者としてはこれは反則なのだが、このあたりでは致し方ないかと思う。表参道あたりの裏も、袋小路などが多く、手頃な裏道の接続をさがすのはなかなか難しいのだ。南青山5丁目で「たつむら」のあたりから「フロラシオン」のほうへ抜けるというのでは、六本木通りから来た場合ならともかく、青山通りを来た場合には馬鹿らしい。しかも、その先には青山墓地がある。墓地沿いの外苑西通りは、夜には幽霊が出るというので有名なところだが、いくらお化け好きとはいえ、わざわざ夜中にそこを目指す必要はない。
青山通りの反対側を、カプリースあたりから裏へ入ってハナエモリビルへと抜け、参道を渡って、伊藤病院あたりから神宮前4丁目と北青山3丁目の間の道を行くという方法はある。しかし、その先に何があるのかというと、キラー通りを渡った先にある青山高校だの國學院高校だの、さらには神宮球場だのがあるだけのこと。個人的には、あまり感動的な目標とは言いがたい。キラー通りを下って、よく朗読などもやった馴染みのバーの「ハウル」に寄るのは一興だが、飲んだら歩き続けることはできなくなる。
ずっと歩いてきてみてわかったが、ようするに表参道や外苑前というのは、青山通り沿いに立ち並ぶ軽佻浮薄なお店や不揃いなビル群以外には、たいしたものがない場所なのだ。旧跡もないし、名所もないし、質のわりには多めにお札とお別れしないといけないような買い物や食事が、どうにかこうにかできる場所でしかない。パリだったら、こういう通りのむこうに寺院や議事堂やエッフェル塔などが美しく照明されて見えていたりする。近代というテーマで、巧妙にテーマパークとしてのパリを拵えたナポレオン3世とオスマンは、興行師としてはなかなかの腕を見せた。パリにはつねに《むこう》や《かなた》があるが、人々はどんな時代どんな階層であれ、けっきょくのところ、《むこう》や《かなた》しか求めはしないものだと、ナポレオン3世はよく知っていた。
表参道や外苑前には、人に《むこう》や《かなた》を思わせるものはなにもない(ちょびっと見える東京タワーぐらいでは、ちょっと…)。なんの目的も持たずに、ただ歩くだけのためにやって来てみてわかるのは、これだ。此処にはなんにもなかったんだ、ということ。
そういう意味では、Take me to the moonとか、Slowboat to Chinaとかと、鼻歌で歌って歩くのにふさわしい場所ではあるのかもしれない。いまどきのChinaはどうかと思うが、moonのほうはなら、まだいけるだろう。あのあたりで、酔った女の子に、「こんなとこツマンナイから、もぅ、月にでも連れてってぇ」とか言われたら、オジサマがたは、さて、どこへ連れていくんだろうか。
こんな外苑前や表参道から三軒茶屋まで歩いて戻らねばならない時の、またひとつ楽でない小さな航海に出るような気持ちを、なんと表現したものだろう。オデッセイアなら、うまく表現してくれるだろうか。おお、ムーサよ、スルガマサキが表参道や外苑前には《むこう》や《かなた》がないと知り、ふたたび三軒茶屋に歩いて戻らねばならなかった時の疲弊した心を語れ。さすがに彼の足腰は疲れてきており、多少は精神力も必要になってくる頃のことだった。彼はじつは、5月に山歩きをした際に左足のヒラに故障を起していて、いまだに完治していないまま歩いていたのではなかったか。故障というか、たいへんな凝りがぎゅっと固まったままほぐれていないという感じなのだが、長く歩いた後など、きまって左足が動かなくなり、今春などよく、駅のベンチで回復を待って座っていたことがあったというではないか。おお、語れ、詩の女神よ、その後の彼がどうなったかを。
……べつに語ってもらわなくてもいいが、こんなノリから入っていけば、けっこうジョイスの試みにも親近感が湧くというものではある。
ともかくもその後、1時間ぐらいで、ほぼ同じ道を辿って(「ほぼ」というのは、やっぱり帰りにも裏道接続で失敗したからである…)、三軒茶屋へ。野菜や肉や魚などの買い物をして、ようやく帰宅となった。
歩いてみていると、なにが起こるかわからないものだが、きのうは、行きに、松見坂での信号待ちの際、ちょっとの時間を使ってアキレス腱を伸ばしていたら、わきにいた外国人が「ソレ、合気道デスカ?」と話かけてきた。そうじゃなくって…と説明しながら、どこから来たのかと聞くと、パリからだという。2ヶ月滞在して、こちらの劇場で舞台演出をしていたが、あしたパリに帰る、とか。あれ、フランス人?と聞くと、そうだという。そうなれば、話ははやく、フランス語であれこれ話すうちに、こっちも詩を書いたりしているし、それじゃあ連絡を取りあおうということで、メール交換となった。こんどパリに行った時には会おうね、その時はよろしく。ということで、これは、パリに行って歩きまわると方々で起こるようなことなのだが、さすがにトウキョウでは珍しいので、ちょっと楽しい出会いだった。脚本家で演出家。そういうフランス人とはまだ付き合ったことがないので、今後のお楽しみということに。
トウキョウ歩きも、ちょっと休憩しないといけないかもしれない。足腰は大丈夫だが、マメができてしまった。いつもながらのことだが、靴と靴下の工夫というのも、かなり歩く際にはなかなか難しい。
第一六〇号(二〇〇八年七月二十六日)
サメの美しさとやさしさに魅せられて、ドキュメンタリー映画を撮った人がいるらしい。たくさんの映画賞を獲得して日本でも話題になったそうだが、どういうわけかぼくのアンテナにひっかからなかった。
この映画、ロブ・スチュアートの『シャークウォーター』を見てきた友人に聞くと、サメと海の美しい映像は、もちろんこの映画の素晴らしい点だが、なんといっても毎年1億頭のサメが虐殺されているのに心を動かされたという。
魚の虐殺、などと言われても、胡散臭いなぁと思う。イワシやジャコやオキアミの虐殺まで数えたら、人類の犯罪は宇宙的な規模になる。小学校あたりから、魚を食べようなどと食育がなされているではないか。
しかし、食べるための魚コロシという意味ではないらしい。フカヒレを取るためのサメの虐殺だという。マフィアとフカヒレ・ビジネスの国際コネクションがあるそうだ。特にコスタリカでは、サメの密猟は禁止されているというのに、フカヒレ産業が盛んらしい。こういう仕事に携わる猟師たちは無駄なことはしない。サメを捕獲しては、ヒレだけ切り取り、まだ生きている体をふたたび海に投げ捨てる。サメの肉など二束三文にしかならないが、ヒレだけは富を生むのだ。サメの体の95パーセントが生ゴミとして捨てられることになるという。生きているサメは、すぐには死なない。時間をかけて失血死していくそうだ。生まれ育った海の底に沈んでいって、しだいに意識や苦痛を失っていくということになるのだろうか。
なんだか『史記』に出てくる「人豚」みたいだな、と思う。人間の手足を切って、死ぬまで大きな壺に入れて置く刑罰だ。肥溜めに投げ込んで置くという場合もあったらしい。
フカヒレだけを取るためのこういった殺し方が、肉を食べるために殺すのより残酷だとか、なにか倫理や魂のようなものの前で罪深いことと見なされるべきだと言ってしまえば、人間の側の独善ということになるのだろう。サメを捕獲したらまず殺して、それからヒレを切り取るようにしてやらなければ可哀想だというのは、いろいろなところで見られる欧米的独善である。少しでも殺される側の痛みを軽減してやらなければ、という欧米的思いやりは、痛みの生じている現場での現実的な処置法のひとつには違いないだろうが、痛がって苦しがっている当の相手が「殺してくれ」と本当に思っているかどうかは定かではない。救援のすぐには来ないような場所での戦闘で大怪我に遭い、出血も多くて、もう助からないだろうと思われる兵士を、心臓と脳を銃で撃ち抜いて少しでもはやく殺してやるのが思いやりというものなのか、それとも、止血方法さえままならなくても、最後の最後まで痛がらせ、尋常とは違うとはいえ、なんとか意識らしきものを保たせてやっておくのが思いやりか。
苦しんでいる本人は、ひょっとしたら奇跡で急に傷口が治癒するかもしれない、などとうつらうつらながらも信じているかもしれず、そうだとしたら、それを強制的に断ち切るのは罪が重いという気がする。たとえ3分後には失血死するとしても、その3分の間に、この瀕死者は、生涯でいちども抱いたことのないような何か決定的な幻想を抱き、彼の天界や神学を構築して逝くかもしれない。それを奪うことこそ罪深いというべきだろう。だとすれば、ヒレだけ切り取って、サメを母なる海に投げ捨てるほうが、すぐに船上で殺してしまうよりよほど慈愛に富んでいるといえるかもしれない。
いずれにしても、生命を奪ってしか生きていくことのできない人間存在をやっているというのは、いつもながらに、つくづく情けない。もし(ノーテンキな学校のセンセたちがノタマウように)生命が本当に重要なら、あちこちで命を食い散らしてばかりのわれわれは、ただ存在しているというだけで悪なのだ。(思考のこのあたりには、[カタリ派の世界へようこそ!!!]という標識が出ている…)。
そしてまた、これがもし悪でないというのならば、「神」なるものの本質が、われわれが抱きがちなものとは全く違っていると考えなければならない、…そういう方向指示器もピカピカ点滅しはじめるのだ。その場合、「神」は古今東西の悲劇や虐殺などと太い連絡網で繋がることになる。「神」を扱う思考にとっては、死や苦痛や悲惨を、聖なるもの、至上の価値として扱うことほど容易なことはない。「神」思考や「人生の価値」思考のここらあたりのポイントを積極的に操作すれば、ヒトラーが一先駆者に過ぎないと見えるような時代が、すぐに来ることになる。
(「悪」とか「神」という語を、ぼくはここで簡便な要約記号として使っている。これらの語にやたらと思い込みの深い方々は、あまり目くじら立てなくても大丈夫です)
チベットの有名な聖者ミラレパは、修行中、川のほとりでひとりの僧衣の男に会ったことがある。あきらかに修行者と見えた。ところがなんと、殺生を禁じられている仏教徒というのに、その修行者は川で魚を取って平然と食している。驚いたミラレパは、「仏教者の身で殺生をしていいのですか」と詰問した。僧衣の男の答えて言うには、「その通り。殺生をしてはならない。私も殺生などしていない。ほれ、このとおり…」。
見ると、男が手にもった魚の骨は、川の水に浸かるや、みるみるうちに肉を甦らせ、魚の姿に戻ってぴちぴちと体を振りはじめ、また川の流れに飛び込んでいった。
第一六一号(二〇〇八年七月二十七日)
きのうは再び、三軒茶屋から外苑前まで歩いた。夕方頃でいくぶん涼しく、もう秋かと思うほど。もちろん夏のじっとりとした底力は空気の底にあり、歩き出せばやはり汗だらけになる。
時間があるというので、めずらしく、妻を伴って歩いた。彼女は大学時代、ある競技で国際大会に出場した経験もあるし、暇さえあればこちらが感心するほど運動ばかりしているので、この程度のことはなんでもない。三軒茶屋から駒沢公園までマラソンして、公園内のトラックを数回走って、さらにうちまで走って帰ってくるというのをときどきやっている。ぼくなどとは体力レベルが違う。ただ、走ったり踊ったり撥ねまわったりは得意でも、意外と歩くのは苦手なところがあるので、出発前にそれだけは確かめた。 さすがに無駄のないルートがわかってきて、きのうはすいすいと池尻大橋まで進んだ。途中で猫たちにちょっかいを出しながらでも、気持ちがいいほどはやい。今回は、三菱電機のあたりから北沢川緑道を辿ることにした。世田谷区はこのあたりの緑道をきれいに整備し直し、散歩道の傍らに下水を浄化した水の流れる小川が沿うている。水の流れもきれいだし、金魚や大きな鯉も放流されていて、すずやかな眺めだ。鴨もかなりいた。小鴨を伴って泳いでいる母鴨もいて、遠い公園などに行くより、よほど楽しい場所が広がっている。こんな道が、下北沢ちかくを通って梅が丘方面へ続いていたり、また、別の緑道が経堂方面へ伸びていたりする。
大橋の東邦大学病院から松見坂まで4分で行けるのがわかった時には、東京をよく知っている妻もさすがに驚いた。松見坂からひょいひょいと道玄坂に出るのに7分ほど。
ぼくはいつもながらに、裸が透けてみえるような白のスポーツTシャツを着て歩いているのだが、そんな格好で渋谷に出てもいっこう気にしない。人のなるべく少ないところを選びながら、駅前でもマークシティーでも通過する。しかし、あまりお化粧をしないで来た妻は、このあたりで愚図り出した。さすがに渋谷から表参道、外苑前となると、彼女にとっては仕事の重要な拠点のひとつである。いつもなら、ばっちりメイクして、選びに選んだ服装で、靴はあれで、バッグはあれで、という出で立ちでないとけっして歩かない場所だ。そこへ、ジムのエアロビクス時のような簡易な髪結びをして薄化粧、ふだんならあり得ないようなリュック姿で、しかもすでに汗みどろという状態で出てきてしまったものだから、ふいに人生最大の事件の渦中に陥っている自分を見出したらしい。もし誰か知っている人に会ったら…、とびくびくしている。
このあたりから引き返すか、ついでに外苑前まで行ってしまうか。ここでは、かなり込み入った議論が交わされたのだが、面倒なので省く。せっかくだから外苑前まで行ってしまおうとようやく決定し、進むことになった。
数日前、ひとりで外苑前まで歩いた時には、このあたりの裏道に不案内なこともあり、宮益坂を上って青山通りを進むことにした。が、きのうは、妻といっしょである。彼女は仕事柄、表参道だの青山だの赤坂だの六本木だの銀座だのとなれば、ほぼ知らない通りも店もないので、さすがに心づよい。東口に出ると、宮益坂を採らずにもう少し行って野村ビルのところを折れ、急坂を上れば、青山劇場や国連大学の裏を抜けられる、というのでそれに従った。 この坂は宮益坂どころではない急さ加減だが、しかし、土曜の渋谷とも思えない人の少なさにほっとする。屋上に鐘楼のある清水とききものアカデミアを過ぎてしばらく行くと、白タイル張りの広い通路が遠くまで続いているところに出る。これが国連大学の裏手で、たまに犬を散歩させているおばさんや、なぜかハーレーダビッドソンみたいな大きなバイクが二台通っていった他は誰にも出会わぬうちに、もう国連大学の向こう側に出て、表参道に入っていた。
外苑前まで行って引き返す時、オレンジピールを無数に外面にくっつけたような姿の現在建築中のキノクニヤの巨大なビルディングの裏手にまわって、ぼくにはわけのわからない未知の細道を右左とたどりながら、ここは何々の店、ここは前とかわって何々、ここは何になる予定…などなどと、さすがにその道のプロは違うものだと感心しながら妻の案内を聞く。そうして歩いているうち、遠くから摩天楼のように見える青山パークタワーマンションに出て、なんとも豪勢なものだなあ、一戸一億ぐらいでも買えないかな、二億ぐらいなら買えるのかなと、まるで縁のない金額話をしているうちに、もう明治通りに出る。ガードをくぐってJRの向こうに出、オルガン坂をたどって、ビレッジ80あたりから東急本店へと抜け、さらに一気に円山町のホテル街を抜けて、神泉町に入り、松見坂へ。ここまで来ると、もう三軒茶屋は目と鼻の先に感じるようになっているのだから、慣れというのは怖いものだ。それに、なんどか歩いたおかげで、足腰がかなり楽に運ぶようになっている。
きのうは歩いている間ほぼ1リットルほど水を飲み、水だけではミネラルなどが足りなくなるだろうと思い、アクエリアスを500ミリリットルほど飲んだが、帰宅してからもしばらくはかなりの水が飲みたくなる。それが一段落してからのビールというのは、本当に旨い。けっこうな量を飲んでも酔わないのは、水が先に何倍も体に入っているからだろう。