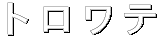 83
83駿河 昌樹 文葉 二〇〇八年九月
トロワ・テ、Trois thes。仏語で「三杯の茶」。筆者居住の三軒茶屋は三茶と略称される。
すなわち、トロワテ。ひたすら、益体もない文章のために。
SURUGA’S詩葉メール便・編集贅言集18
[第一六二号〜一六七号・二〇〇八年七月三十日〜八月五日]
第一六二号(二〇〇八年七月三十日)
三軒茶屋から外苑前まではすでに歩いてみたが、これを自転車で行ってみたらどんな具合になるか、やってみたかった。
試してみると、どうもよくない。
自転車が走るべき道というものがないのだ。
はやくも三軒茶屋のキャロットタワーあたりから、いや、自宅からすぐの世田谷通りに入るところから不都合に直面した。車の通行量が多く、その上、車のわきをひっきりなしにバイクがすり抜けていくので、いざ自転車で車道をゆくとなると、ひやひやものなのだ。三宿や池尻あたりの246号線の場合ともなると、もっとひどい。宅急便や店の運搬車などが何台も止まり続けていて、車道を走ろうとする自転車は、どうしても道路の中央に近寄って行かざるをえない。しかし、246のこのあたりは自動車が半端でない速度で走っており(実際、死亡事故多発地帯でもある)、しかも、曲芸のような運転のバイクがそのわきをビュンビュンと抜けていく。自転車はバイクと同じ場所を通らざるをえなくなるのだ。性能のいい軽いスピード用自転車でない場合、危ないというより、無謀といってよい。
そうなると歩道を通ることになるが、ただでさえ自転車の歩道通行は肩身が狭い上に(道交法上、禁止ではなくなったらしいが…)、商店街付近の歩道の混雑もすごい。なんのことはない、歩いていくのが一番安全で融通が利き、しかも速いということになる。 松見坂からは松濤に抜けて、文化村や東急本店の裏をまわって東急ハンズのほうに出、公園通りを横切ってタワーレコーズからJRのガードをくぐり宮下公園の陸橋をくぐって東口に出たが、どこもかしこも歩道は人で溢れ、車道は渋滞ぎみで、自転車に乗ってきてしまったことが馬鹿らしくなった。
渋谷周辺の、これでもかというほどの大小の坂にも参った。東邦大学大橋病院あたりの長い急坂も、松見坂のあたりも覚悟はしていたが、歩いていると気づかないような坂が他にもたくさんあって、自転車にはいちいちこたえる。変速ギヤがあっても、膝の筋肉に相当の負荷がかかる場面が多く、何度となく、「歩く」というシンプルな移動手段に備わる自動調節機能の素晴らしさを再認識させられた。
渋谷から裏道を通って表参道に向かったが、どこかで道を間違え、なかなか青山通りに出ないと思って進むうち、ひょいとハナエモリビルの脇から表参道そのものに出てしまった。三茶からハナエモリビルまで自転車で来てしまったか…、と多少の感慨もあったが、広い歩道とはいえ、ここでも人通りは多く、のんびり気分でサイクリングを楽しむなどという余裕はない。とにかく、人に、車に、信号に、左右に、後ろから近づいているかもしれない自動車に、道からはみ出している看板等などに注意し続けていなければならず、いちおう外苑前までという目的は達したものの、なんと所要時間は、歩いて此処まできた時より10分速いだけのことだった。歩く際には利用できる遊歩道や混雑した歩道などが使えないため、相当のまわり道を方々で余儀なくされたためだ。
帰り道はもっと空いている楽な道を、と思って、骨董通りから青山学院女子短大、中等部前を通って六本木通りを抜け、國學院大學前の坂を下って氷川橋を渡り、そのまま代官山へ。ここから、青葉台や東山や池尻を通過してスムーズに三軒茶屋に出ようと思っていたのだが、甘かった。往路どころではないとんでもない坂地獄に入り込むこととなった。代官山のブティックの並ぶ通りを抜けたあたりまではまだよかったが、勘に頼りながら近道しようとしたのがまずく、なんども道に迷った。このあたりで道に迷うと、せっかく下った坂をもう一度上り直さねばならない。それを何度かくり返すということになる。いつまで経っても旧山手通りが渡れず、ようやくそれを越え、西郷山公園を通過してひよどり越えのような超ど級の急坂を下ると、ようやく目黒川である。ここは勝手知ったるところ、と思ったのがまた失敗で、山手通りを渡ったあたりから、また道が怪しくなり始めた。東山1丁目と東山2丁目というのは平地だとこれまで思い込んでいたが、とんでもない。ここもまた大小の坂の展覧会のような地区で、地図上でのほんのわずかの距離を進むのに、下ったり上ったりをさんざん強いられる。日も暮れはじめ、へとへとになって、ようやく高低差が少ない地域に入ったと思って、少しほっとして走っていたら、怪奇ドラマにでも出てきそうな、どこかぼやけた雰囲気の古ぼけた病院が目の前に現われた。三宿病院だった。ここから、隣接する青島養護学校や世田谷公園あたりまでの一帯は、うすら怖いというか、どこか異界の雰囲気のある地域だった。
帰宅までに要した時間は、結局、3時間近く。歩いて外苑前まで行って帰ってくるのに要する時間が、ほぼ2時間なのだから、自転車使用のほうが1時間ほど多めにかかってしまう。歩行コースと全く同じコースを辿れれば、自転車が速いのは疑うまでもないが、同じ道を辿れず大がかりなまわり道を強いられる結果、こういうことになってしまう。東京23区内に住む者が車を持つと、かえって時間のロスになってしまう場合が多いが、どうやら自転車にも当てはまる可能性があるのがわかった。
ビジネス書でベストセラーを飛ばしている勝間和代という女性会計士が、都内を自転車で移動するのこそビジネスマンには効率的だと、『効率が10倍アップする新・知的生産術―自分をグーグル化する方法』(ダイヤモンド社)に書いているが、少なくとも、山手線外の住人や、渋谷から表参道あたりを活動範囲にする人々にとっては、まったく縁のない話である。幹線道路を自動車と競りあいながら走れば、走れれば、速いのかもしれない。しかし、あの排気ガスの中を?あの殺気立った喧騒の中を?汗みどろになって?246号線、明治通り、山手通り、環七や環八などといった道路を、毎日、自転車で颯爽と走り抜けるのが現代的なクールな効率的ビジネスマンだというイメージは、これはもう、ほとんど都市伝説かトンデモ本の領域だろう。自転車に乗りさえすれば健康的だとか、効率的だとか、そんな愚考が、どうしてビジネスなるものの世界でこう単純にまかり通ってしまうのか、不思議でならない。ああいう類のビジネス書は、特定の企業の製品の宣伝になるように巧みに書かれていて、著者の懐には企業からのお礼が舞い込む仕組みになっているものだが、まだ日本のビジネス界のオゾマシサやクダラナサを疑うすべを知らず、真に受けて、高価な自転車を購入してしまったりする若い社員たちこそいい迷惑だろう。それとも、いい薬というべきか。
第一六三号(二〇〇八年七月三十日)
見物対象としてのスポーツや野球にまったく興味がなく、ことにプロ野球には興味がない。ニュースを見ていても、スポーツやプロ野球に話が移った瞬間にチャンネルを替えるか、消してしまう。べつに悪い思い出があったわけでもない。小学生のあいだはご多分に洩れず野球少年で、暗くなるまで野球ばかりして過したものだし、新聞の野球欄を毎日切り抜いてスクラップしていた。左利きなので、守備はファーストやライト。打率がよかったとはいえないが、王の一本足打法の真似もそれなりに様になった。いつもジャイアンツの帽子をかぶり、ジャイアンツのジャンパーを着ていた。川上哲治が監督だった頃のジャイアンツ時代、関東地方の一少年としては、これはほぼ、あたりまえの流儀というものだっただろう。
いまでは、野球好きの人から来るメールによって、イチローの3000本安打達成なども知る始末だが、どうやら大変なことらしく、今後、50年や100年は破られない可能性もあるという。
あのイチローにして、プロに入団する時にあまり注目されなかったというのは面白い。阪急ブレーブスには4位だか7位だかの指名で入団したそうだ。契約金もとても安かったという。
その頃のイチローが、どのようにして現在の彼になっていったかには興味を惹かれる。注目されないところで本当の力をつけていく人たちだけが、人類のパラダイム転換を行うからだ。そういう意味からいうと、現在の彼の活躍には関心がないのだが、別の物語が進行中だともいえる。最高度に注目を集める中で、停滞せずにいっそうの力をつけ続けていくというのも、人類史においては珍しい物語なのだ。たんなるスポーツ読み物でなく、イチローのプレーヤーとしての具体的な変貌過程を緻密に分析・叙述していくような作品が出てくれば、文学作品も変貌するだろうと感じる。
第一六四号(二〇〇八年八月一日)
パン食ではないのだが、空腹をおぼえた時のために食パンを買い置いて冷凍してある。お菓子を食べるより、食パン一枚を焼いてジャムをつけて食べたほうが安いし、満足感もある。もう10年以上前から続けている。
このパンの値段の変化を記しておくのは、昨今の物価高騰の記録の一端になるかもしれない。近所の西友でつねに買うようにしていたが、昨年までは98円だった。ときおり、セールで93円ぐらいになるときもあった。それがこの春、107円に値上げ。ほぼ10円の値上げというのは大きい。当初、賞味期限間近のものは83円の処分価格で売っていて、よくそれを買った。すぐに冷凍してしまうので、こちらには賞味期限は関係がない。かえって、値下げされたようなものだった。
それがこの頃、処分価格のものがすぐに売れていき、なかなか店頭でお目にかかれない。しかたなく107円のものを買っていたが、数週間前、少し離れたマルエツで、パンを常時98円で販売することになったというのを見つけた。第一パン製「麦ゆたか」である。マルエツも第一パンも、なかなかの決断だっただろう。以来、食パンはマルエツで買うことになった。ときどき、ハナマサで賞味期限間近のパンが63円ほどで売られているのに出くわすことがあるが、パンについては、ほぼ、こんなところで落ち着いている。 どの店にも得意科目があり、他と比べて安いものや少し高いものがある。そのため、以前より店を多くまわることになったが、歩くのはもとより足腰の維持にはよいのだし、カロリー消費にもなる。それに、もともと、どの店にしても家から10分以内なので、大ごとに考えるほどのことではない。さらに、どんな場合にせよ、もっとも節約すべきは時間と意識内注意量だと思っているので、それぞれの店での買い物時間は極端に短縮し、てきぱきと動くようになった。結局、以前よりも効率が上がっていて、これは物価高騰のおかげでもあるかもしれない。
職場へは、ロールパンを手製のサンドイッチにして持っていくことにしている。これについては、西友の107円のレーズンロールがもっとも安い。これを開いてバターやジャムを塗ったり、マスタードを塗ってチーズを挟んだりする。これで、一回分の昼食はほぼ130円以内になる計算だ。飲み物は水筒やペットボトルに紅茶を入れていく。こちらは10円以下になるだろう。炭水化物は極力少量の摂取にすべきなのだから、これ以上の昼食は活動を逆に鈍くする。経験的な事実である。夕食にはパンも米も食べない場合が多いので(野菜や魚肉のみ)、毎日の炭水化物摂取は、ほぼ、この昼食だけとなる。
昼食は、しかも、立ったままや歩きながら食べることがほとんどだ。遠方へ出向くことが多いので、駅ホームや電車の中で食べてしまう。ロールパンというかたちは都合がよい。
20年ほどはこのかたちでやってきたし、今後もこの点はかわらないだろう。昼にラーメン屋やファミレスやファストフードに入ることはないし、夜はなおさら入らない。なんだか、常時、ゲリラ兵のようだが、こんなふうに生きてきた。死ぬまで変わらないだろうと思う。
第一六五号(二〇〇八年八月三日)
淡島通り沿いの太子堂の国立小児病院跡地にできた巨大なマンションのあいだを抜けて、三軒茶屋より明治神宮や代々木公園まで歩き、また別の道をたどって駒場東大付近を抜けて帰ってきた。
住友不動産と竹中工務店によるその「グランドヒルズ三軒茶屋」は、最上住戸146.12平方メートルで2億3300万円、最も安い住戸でも79.48平方メートルで8800万円。交通至便とはいい難く買い物にも不便なところなので、容易には売れないだろうと思っていたが、けっこう埋まっている。5重のセキュリティーシステムで外部者を完全にシャットアウトするシステムと、阪神淡路大地震規模の震度7クラスを震度4程度に低減できる免震構造を享受しているファミリーが、すでにたくさん住んでいる。 自分のまわりを見てもそうだが、数億程度は容易に調達できる人々で、じつは日本は溢れている。「ぼくだけは貧乏、すみやかに地上を過ぎ去るトルバドール…」と鼻歌しながら、滅亡への散策を、きょうも、ひとり進める。昭和・平成のルネとして、何十年も前からすでに終わっているひとつの人生、そろそろ終わらせるべきひとつの身体が、まだ歩み続ける……
第一六六号(二〇〇八年八月四日)
ついに皇居まで歩き、一周してきてしまった。
妻の休みの日なので、すでにジムで相当の運動をしてきた後だという彼女を伴う。
三軒茶屋から、裏道をおもに選びながら渋谷、表参道、外苑前と通過し、そこからは青山通りを素直に歩く。陽も暮れていたので、細道に入って間違うのを避けたかったためだが、ここを行くのには青山通りを通るのがいちばん近いらしい。伊藤忠商事から神宮外苑あたりは、徒歩で通過するのははじめてなので、銀杏並木のむこうに見える絵画館が照明で浮き上がっているのもはじめて見、国会議事堂の上が欠けたような景観を楽しむ。
青山一丁目駅を過ぎると、赤坂御所。ここが皇太子夫妻の住まいだそうだが、彼らの住所は元赤坂2ということになるわけか、と妙な感心をする。京都なら、こういう地区名称にはならないはずだろう。赤坂御所わきの青山通りは街灯が少なく、夜は暗い。ときどき警官が巡邏しているが、もう少し明るくしてもいいのではないかと思う。ジョギングしている人たちが音も立てずにすれ違っていくので、驚かされることもある。
面白いかたちのカナダ大使館や丹下謙三による新草月会館を過ぎる。やはり丹下謙三設計で、ピロティ建築で有名だった一九五八年の旧草月会館は、一階部分が横に吹き抜けになっていて、青山通りから見ると、吹き抜け空間を通して奥の庭園が美しく見えたという。一九七七年に丹下自身が作り直した現在のものは、壁面がガラス張りになっていて、そこに御所の緑を映り込ませている。ガラスによる緑の借景ということになるのか。
丹下は、一九七八年竣工のハナエモリビルの場合にも、ミラーガラス使用のカーテンウォールを採用した。こうした壁面ガラスの使用は、イオ・ミン・ペイによる一九七〇年代の高層ビル、ジョン・ハンコック・タワー(ボストン)に丹下が強い印象を受けたためという。壁面ガラスによって周囲の景観を映しとり、ビル自体の存在感を隠したり軽くしたりする意図に共鳴したらしい。
赤坂御所の終わりに虎屋ビルがある。夜なので閉まっており、黄色いネオンで、と、ら、や、の字が輝いている。営業中なら、ここであんみつでも食べたかった。東京人のくせに、まだ虎屋本店でいちども甘いものを食べたことがない。あんみつやクリームあんみつ好きで、旨い店と聞くとほうぼうに行きたくなるのだが、浅草の梅園などがまずくなってしまったこともあり、警戒しがちになる。根津を歩いていて偶然入った甘味処のあんみつがひどく旨かったのは覚えているが、店名を忘れた。甘味といえば、大阪の夫婦善哉も何度か食べて忘れがたい。あそこにはあんみつなどはあったっけ。いつも、馬鹿のひとつ覚えにぜんざいを頼んでしまうので、他のものをとったことがない。織田作之助ファンなので、まずぜんざいを食べてから、他のものについては考えよう、と思ってしまう。
ちょうど虎屋のあたりで、御所のなかに200メートルほど入ったところが秋篠宮邸のはずである。三笠宮邸や寛仁親王邸も遠くないが、彼らは御所内の散策のおり、虎屋の屋号を見ながら歩いたりしているのだろうか。
やがて、赤坂見付に出、赤坂の賑わいを右手に見下ろしながら、永田町に入る。赤坂プリンスやエクセル東急を左右に見上げながら、自民党本部を過ぎると最高裁だが、最高裁の向こうにある国立劇場への表示を見て、懐かしくなる。大学時代、毎月のように歌舞伎を見るのにここを通った。アルバイトで稼いだ金は、本を買う他は、ほぼすべて国立劇場や歌舞伎座に吸われていった。当時は、いい席が欲しければチケットを買うのにさえここまで来る必要があったので、ずいぶんと馴染んだ道である。
三宅坂で内堀通りに出ると、いよいよ皇居。夜闇の中にお堀が沈んでいて、不気味さがある。皇居まで歩くのが目的だったので、ここで折り返してもよいのだが、ついでに一周してみようかということになる。皇居ひとまわりは、5キロほどあるらしい。晴れてはいるが、ひじょうに蒸していて、不快指数の高い中では、すでに2時間ほど歩き通してきた上にさらに5キロというのは、多少つらいものがある。夜も遅くなってきたし、とにかくひとまわりだけはして、歩いて三軒茶屋まで帰ることはせずに、半蔵門あたりからメトロで帰ることにしようと決める。ひとりなら徒歩で帰るのは可能だが、妻のほうは歩き出す前にすでにかなりの運動をしてきているので、限界に近づいている。
皇居のまわりというのは、ジョギングや早歩きをしている人がけっこう多い。ひっきりなしにすれ違う。そういうコースになっているのは有名だが、実際に歩いてみると、ここを毎日走ったりするのはどうかと思う。夜なので、あまり排気ガスなどが見えないのだが、自動車の通行量から見て、よい環境であるはずはない。それでも北京よりははるかにマシか。
桜田門を過ぎて内堀通りを歩き続け、皇居外苑と皇居前広場に入ると、銀座や大手町のビル群がよく見える。振り返れば東京タワーが見え、東京の中心に来たという印象が強まる。夜なので、どれも光に彩られており、皇居の森の暗い広がりもあって、少し広々とした気持ちになれるのは悪くない。
和田倉濠を過ぎるとパレスホテルが見える。三十三年前、ここでいちばん若い叔母が結婚式を挙げ、高校生だったぼくはスナップ写真係になって、愛用していたペンタックスSPにナショナル製の大きなストロボをつけて撮影した。両親はまだ現在のぼくより若く、祖父母でさえ、現在の両親より若かった。
あの時結婚した叔母の夫は、昨年、大腸ガンで六十代で亡くなった。ビールの好きな人で、他の酒を飲まずに、どんな時もビールばかり飲んでいた。そんな彼に、一度、ビール以外のものをたくさん飲ませたことがある。うちの母方の菩提寺は厩橋の榧寺なのだが、法事が終わると蔵前から浅草のあたりで飲食することになっている。いつだかの法事の後、食事も済んで大方を帰宅させ、最年長の叔父、この義理の叔父、遠縁の叔父(この人の奥さんは学習院出で、スタンダールの『赤と黒』で卒論を書いたという)、それに従妹と残って、浅草の神谷バーで鯨飲したことがあった。はじめにビールをずいぶん飲み、飽きてきたので電気ブランを飲み始めた。あれはけっこう強いが、何杯飲んだかわからない。ビール以外のものをこんなに飲んだのは生まれて初めてだが、けっこういけるもんですね、と叔父は言っていた。そうとう酔ったが、まだまだいくということで、それから三定に移り、座敷に落ち着いて、山盛りのてんぷらに、またビール、日本酒とウィスキーとなった。店じまいは何時だったかわからないが、それとともに追い出され、業平の印刷業者の叔父は、浅草からうちまではぜんぶ庭みたいなもんですから、とすっかり千鳥足になって帰っていった。毎日、夕食時にはまず大瓶三本を飲んでから食事を始めると言っていたが、あそこまで飲むとビールも大腸にはよくなかったのかもしれない。
ところでその夜だが、最年長の叔父もタクシーで帰り、残った遠縁の叔父と従妹とぼくは、さらに飲もうということで新宿までタクシーを飛ばし、その頃よく行っていたワインバーでさらに飲み明かすことになった。朝がたまで飲み、さすがに遠縁の叔父はブッつぶれてタクシーで帰路につく。ぼくと従妹はとりあえず代田のぼくのマンションに行き、ぼんやりしている彼女にお粥などを作ってやって、始発電車が動き出した頃、下北沢駅方面へと送り出した。
意識のなかで場所の名や他の固有名詞や普通名詞はこまかく紡ぎあわせられており、パレスホテルという名から、ごく掻い摘んでさえ、これだけのことがひとつの塊となって浮かぶ。というより、ぼくの意識は日々、つねにこうした記憶の大きな沼として動いている。プルーストのような作品構造を打ち出せないまでも、自分の半生に出会った人々を題材にしてあの程度に描くことはあまりに容易なことだといつも思う。あれでも短すぎるくらいだろう。よく、文学好きの、しかし、研究者ではない人たちと話していて、プルーストは過大評価され過ぎているという話になり、共感しあうことがある。そういう時に中心になるのは、プルーストはあまりに短すぎ、掻い摘みすぎている、コンパクト過ぎる、という批判だ。もちろん、読む側にしてみれば、あれは長いものなのだが、自分が書くとなったら、あれではとてもではないが満足できないだろうという話になる。日本のぼくらの世代の成長譚ひとつ描くにも、実際には江戸末期から語り起さないと、曾祖父母、祖父母あたりの人生観や生活習慣、家族のなりたちなどを浮き彫りにはできない。うちの曾祖母は実家が近かったということで、若死にした樋口一葉にひじょうに親近感を持っていた。田端居住時代には芥川龍之介夫人の文さんと三味線仲間だったし、田山花袋なども近かった。田端に文士が集まっていた時代だった。うちの裏には陶芸家の板谷波山が住んでいて、いつも制作しており、窯の煙が絶えなかった。波山は、創作に行きづまると夫人の髪を握って庭じゅうを引き摺りまわすことがあったそうで、その様子がうちの二階から見えたし、夫人の悲鳴声もよく聞こえた。こういった事柄にくわえて、体の弱かった大店の主人で、俳諧だの書画骨董だのにうつつを抜かして三十代で亡くなった曽祖父のことなどが雑じることで、母方の家の文芸・芸術観はできあがっていったわけで、それとのつよい影響・反撥関係の中にぼくの現在の文芸とのつきあい方というものがある。自分のことを少し考えるにさえ、明治・大正までは軽く遡る必要がこうして出てくるのだ。そう考えると、プルーストの創作における歴史意識は、たとえばシャトーブリアンのそれとはずいぶん違っていて、遡り方があまりに短すぎる気がする。歴史意識におけるそうした抽象性は、それまでのフランス文学の中では異質なものだが、そこにプルーストの新しさがあったのかと考え始めると、カミュの『異邦人』におけるムルソーまではけっこう距離がない気もする。ムルソーとなると、家族史はほぼゼロに近づき、個人史も猫の記憶ほどに短い。カミュを大きく扱うことで発想されたロラン・バルトの『零度のエクリチュール』は、そうした語り手の歴史性の零度にも敏感だったものか、と思い直す。
ついでにつけ加えておくと、ずっと隣りづき合いしていた板谷波山の息子に板谷菊男さんがおり、この人は開成中学・高校の国語の先生だった。母方のうちのふたりの叔父は開成出身だったので、国語、とくに古典は、この板谷先生に習った。お化けが好きで、年中お化けの話をするので、開成では板谷菊男先生はお化けと呼ばれていたそうである。うちの家系は、男の子は絶対に開成に行かねばならないと言われて、ぼくも小学生の時、この板谷先生の田端のお家に通って、国語を習ったことがあった。習ったといっても、何度か通ってみて、この子は国語はべつに問題ないということになり、たいしたことを習ったわけではない。お化けの話は、例に洩れず、けっこう伺った。いわゆるお化け話だけでなく、いまなら都市伝説とか呼ばれそうな、もう少し広い領域を先生はカバーなさっていたという気がする。なにしろ、ご町内の名士同士の家ということで、直々に芥川龍之介などに会っている人なのだから、話の端々に、ぼくはアクタガワという人の雰囲気を嗅ぎとろうとした。お化け話の伝承というか、継承を通じての、東京の文化の受け渡しの一端に、その時のぼくは居たといっても、さほど大げさではないはずだろう。中学から高校まで、ぼくは芥川龍之介あたりの時代の日本近代文学研究か、保元物語や平治物語、さらには平家物語などの軍記物語研究だけをして一生生きていこうと決めていたが、それは小学生のこの頃の流れからいえば自然なことだった。高校二年生の終わり頃、ちょっとした気まぐれからフランス文学に転向してしまったが、まぁ、それが今生の運の尽きであった。必要もないのに、若気の至りからわざわざ志願して戦艦大和に乗ってしまったようなものである。
さて、皇居周遊に戻るが、乾門から代官町に入り大官通りを行くと、左手に皇居の暗い森を望みつつ、うっそうとしたところもある木立の中を行くことになる。あまり歩かない道なので、このあたりは少し面白い。右手に都心環状線を見ながらの道は、歩いてみて初めてわかる都心の道路網と景観の絡みあいを気づかせてくれる。
千鳥ケ淵を左折し、半蔵門方面へ。英国大使館から来たのか、首輪をしている猫がちょこちょこと内堀通りを渡って、千鳥ケ淵公園に入ってくるのに会った。英国大使館の猫か?リュックにいつも入れている煮干をやってみようと思ったが、藪の中に入っていってしまい、機会を逸した。時々、道で出会う猫たちに煮干をやってアプリヴォワゼ(馴れさせる、という意味のフランス語。『星の王子さま』で、狐が王子にこの言葉の重要性を説く。いろいろと訳語がありうるが、なかなかうまく訳すのは難しい言葉)を試みているのだが、ひとつ大課題があって、はたしてヨーロッパなど、肉食の国の猫は日本の煮干に好反応を示すかどうか、とつねづね考えている。フランスに行くときに煮干をいっぱい持っていけばいいのだが、いつも持っていくのを忘れるし、なんだか税関でめんどうなことになりそうで、やらないでいる。英国大使館の猫ならば、ひょっとして主食はビーフだったりするかもしれず、もしそうなら、日本にいるかぎりでは得がたい研究対象だということになる。
半蔵門の駅に下りることで、この三軒茶屋→皇居歩きはとりあえず幕となったが、駅の階段で、着ている白いTシャツの左腹部にひろく血が滲んでいるのに気づいた。鼻血でも出ていたか、指かどこかから出血したかと探したが、血の出どころが見つからない。シャツをあげて腹部を見てみると、おそらく長い歩きの過程でジーンズの端で肌が擦れたのだろうか、毛穴がたった一箇所、小さく赤くなっており、そこから出血していた。ほんの小さな出血なのに、かなり長いあいだにそうとう出続けていたらしい。まるで、腹を刺されでもしたように血が広がっていて、これでは電車に乗れないので、トイレで洗い、止血も試みる。完全とはいかないが、なんとか見えづらい程度に血を落として、乗車した。こんなことは初めてだが、歩く時にいつも着ているスポーツ用のTシャツと同種の黒のものなどを、今後は、着替え用に持っているのがいいかもしれないと考えた。
メトロに乗ると、当然のことだが、普通の乗客たちが普通の服装をして乗っている。こちらは汗みどろで、水をかぶってきたようなスケスケのTシャツ一枚、それも今日はうっすら血の色まで広がっているとあどろいで、多少の居心地のわるさを感じる。同じ東京とはいえ、この乗客たちとはまったく違った東京をさっきまで歩いていたのだという気持ちが、いくらか矜持のようにもなり、いっそうヘンな気分になる。ともあれ、自分の足にとっては、皇居までが三軒茶屋から地続きになってしまったのだという感覚には、なにか非常に東京観を変える力がある。歩けば歩けるものだとも思うし、昔の人がよく東京中を歩き回っていたのも理解できる気持ちになる。
第一六七号(二〇〇八年八月五日)
こんな世の中になってしまって、という慨嘆が溢れている。ややもすると、自分でも言ってしまっている。
しかし、考えればだれでもわかるように、これはおかしい。世の中というもののいろいろな属性は、使用する基準に応じて、善いとも悪いとも判断される。自動的に諸属性の入れ替わりも起こる。社会はどのような場合にもひとつの全体として機能するから、ある時代の属性Aは、次の時代の属性Bの出現によって、入れ替わりとして消滅するか、薄くなるということが起こる。後の時代の人が、属性Bを手に入れて享受しているにもかかわらず、失われた属性Aを惜しんで時代の悪化だと嘆くのは正しくない。
不可解な殺傷事件が頻繁にニュースになるように見えるにしても、不可解な戦争を大陸にしかけて大量死を発生させながらニュースにもされなかった時代よりは安全だし、まだしも「理性的」、「人間的」なのでもあろうし、行き過ぎの管理社会化が進行中のようでも、その管理体制そのものによって、淫靡ないじめを生むようなローテクな管理癖が軽減されたり骨抜きにされたりするという場合もある。昔なら村八分にされて追い詰められた異端者が、いまならインターネットを使って生活必需品を配達してもらったり、世論を操作しての逆襲も図れる。どの時代にも、ひとつの社会属性は、ある人には善であり追い風であり、べつの人には悪であり向かい風となる。ただそれだけのことで、そういう認識を正確にしたところから近未来・中未来・遠未来への戦略を練っていけばいいだけのことなのだが、人間には、いったん馴染んだ生活・思考様式が根源的に変化するのを厭うところもあるため、慨嘆という形式で生活形態上ないし思考形態上の保守を決め込もうとしがちなものでもある。
人間というものが、ひとりの場合、小集団の場合、あるいは大集団になった場合、さらに国家規模のハイパー集団となった場合にどう思考し、どう行動しがちな傾向を有するか、その定石を学んで、自分が所属する団体とその構成員たちの現状を幻想なしになるべくありのままに見、また、その帰属団体と他団体との関係も、とくに経済・政治側面からありのままに見ようとすることが、いかなる場合であれ人間活動の基本中の基本をなす作業だと思うが、この作業の遂行は、だれもが知る通り、それほど容易ではない。慨嘆が極力避けられるべきなのは、ただでさえ困難なこの作業を、致命的に停滞させがちになるからである。