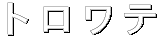 89
89駿河 昌樹 文葉 二〇〇八年十月
トロワ・テ、Trois thes。仏語で「三杯の茶」。筆者居住の三軒茶屋は三茶と略称される。
すなわち、トロワテ。ひたすら、益体もない文章のために。
SURUGA’S詩葉メール便・編集贅言集24
[第一九八号〜二〇六号・二〇〇八年九月三〇日〜十月十二日]
第198号(二〇〇八年九月三〇日)
月曜の勤め先までは最寄駅から十五分ほど歩くが、途中に古い魚屋がある。その店の前に、水槽や甕や大きな発泡スチロールの箱が置いてあって、金魚がたくさん飼われている。大通りを渡る信号のところにあるので、赤信号で待たされている時など、金魚を覗いてみていることが多い。
発泡スチロールの箱のひとつには、死にかけの大きな金魚が四月から入れられていた。ひっくり返ってしまっている。体はさらに傾き、泳いでいるというより、水中に浮いているといった感じだった。痛々しい。いつ死ぬかわからないというふうに見える。それでも、えらだけはちゃんと動かしていて、時どき尾をつよく振る。少し移動したかと思うと、また動かなくなる。えらだけはパクパクさせている。そうして、逆さまのまま、また水中を漂っていく… 毎週見続けたが、こんな姿ながらいつまでも死なず、ひっくり返ったままで生き続けているのだった。一尾では寂しいからか、元気な金魚も一尾入れられていて、こちらはひっくり返らずに、ちゃんと泳いでいた。
五月だったと思う。外に出てきた魚屋の主人に、毎週この金魚を見ているが、どうしてこうなったのかと聞いてみた。主人もわからないという。とにかく、半年ほどこんなになったままだ。もうダメだろうと思って、発泡スチロールのほうに移したが、死なないでいる。よくはならないが、悪くもならない。けっこう、このまま生き続けていくのかもしれない。そう聞いて、見つめ直しながら、金魚にも脳卒中のようなものがあるのかもしれない、それでひっくり返ったのだろうか、などと思った。
夏よりこちら、しばらく見なかったが、九月に入った今週、ひさしぶりに発泡スチロールの水槽を覗いた。元気な姿をして二尾の金魚が泳いでいる。あのひっくり返った姿はどこにもなかった。ひどく暑かった夏のあいだに、とうとう死んでしまったかと思った。ちょうど店の奥から魚屋の主人が出てきたので、あのひっくり返っていたのはどうしました、死んじゃいましたか、と聞いたら、死んでないよ、ほら、それ、その大きいほう、と言って指さす。ちゃんとした姿で元気に泳いでいるうちの一尾がそれだった。あれ、元気になっちゃったの、治っちゃったの、と聞くと、頷きながら、主人はにっこりとした。
信号がかわったのでそれ以上は聞かなかったが、十か月ほどひっくり返ったまま生き続けてきて、ついに回復してしまうなんて、たいした金魚だと感心した。来る日も来る日も、逆さまの姿勢で生き延びるというのも大変なものだが、それがあれほど見事に治って、何事もなかったかのように、ひらひらと尾びれを揺らしながら泳いでいる。気にしながら眺め続けてきた金魚が元気になる、というのはうれしい。小さいことながら、世の中というのはほんとになにがあるかわからない、などとも思わされる。
魚屋のあの主人も、ずっと見続けてきたのだと思った。水を替えたり、餌をやったりする他になにができたとも思えないが、来る日も来る日も逆さまの姿を見続けて、このまま弱っていくだろうか、いつか治るだろうか、などと思い続ける。心に分厚い濃い立体を抱え込むようなものであったはずだ。もう老いに踏み入れた身で、飄々としながら、オヤジもよく頑張ったな、と思った。
第199号(二〇〇八年十月一日)
急に寒くなった。もう十月なのだ、寒くなってもおかしくはない。外にいる時はなにかと気がまぎれるが、家にいると、ひとりのふとした時間、ふいに、過去のこの時節のさまざまな寂しかった時のことが甦って、いっぺんに心になだれ込んできたりする。
もう十年以上前のことだが、勤めていた塾での土曜日の授業がたったひとつになり、それも夜の七時半から九時半までだったことがある。他の曜日は夕方からで、だいたい二つや三つの授業を担当していたのだが、たまたまその年の秋の土曜は、遅くからのたったひとつの授業だけとなった。方々に支店教室のあったその塾は、その頃経営があやしくなり出し、授業数も削減され始めていた。空いていた土曜の夜にひとつでも授業を与えてくれたのは有難いことなのだが、それでも、住んでいた世田谷を暗くなった六時頃に出て、塾のある埼玉まで通うというのは、気分の沈んでいくものがあった。しかも、与えられたクラスというのが中2の出来のよくないクラスで、やる気の希薄な生徒ばかりだった。手ごたえはなく、復習はしてこず、小テストの勉強もろくにしてこない。そのうえ、教室は塾の事務所から数分離れたところにある雑居ビルの2階で、薄汚れた階段と廊下を抜けた奥にあった。薄ら暗い蛍光灯がさびしく白く照らしているだだっ広い部屋。
授業が終わって、生徒たちが帰ってしまうと、戸締りをし、電気を消し、あれこれの整理をし、教室に鍵をかけて事務所までひとりで戻る。時々、だれもいない教室のなかでぼうっとして立っていることがあった。べつに茫然自失したりしているわけではなかったが、毎週の土曜日のこの夜の時間、こんな殺風景な寂しい場所で、張り合いのない相手に教えながら過ごしている人生というのはなんなのだろうと考えたりして、自分がなんと誤った道を来てしまったものかと、しみじみ噛みしめるようにして、無人のうすら寒い教室を眺めていた。
家であれ他所であれ、秋にひとりでどこかの室内にいて、そうして、そこが暗かったり肌寒かったりすると、昔のそんな光景が甦ってくる。耐えがたいというようなことではないが、その頃の気持ちと現在の気持ちとが通底していて、なんら変化もないように感じられるのが、つらいといえばつらい。郊外の街の、雑居ビルの、だれも人のいない雑駁な薄汚れた教室に方途もなく立っている姿、あれがまぎれもなくあの頃の自分で、どうやら今もまったく変わっていないと思うと、もう自分という束の間の存在の結論は出ている、もういいだろう、もう十分だろうなどと思えてくる。
もちろん、このような思いも感覚も、光景の甦りさえも、なにか確かなものを定めうるわけではない。
「いまわれわれが列挙したもののすべての中で、一体、存在者の存在とは何なのか?こんなことさえわからないとは、一体、われわれはなんという愚かなうぬぼれと賢さとをもって、この世界の中であちこち走ったり立ちどまったりしているのか?(…)存在を捉えようとすると、いつでもまるで空をつかむようなことになる。(…)存在は、ほとんど無と同じぐらいに、いな、結局は無と全く同じく、見つけ出しがたい」。ハイデッガーの『形而上学入門』(川原栄峰訳、平凡社ライブラリー)の中のこんな考察を思い出すと、やはり、「もう自分という束の間の存在の結論は出ている、もういいだろう、もう十分だろう」などというのは全く誤っている、とすぐに思いを翻すのだ。
あのうすら寒い無人の教室に欠けていて、今もぼくを根本的に損なっているもの、それは決定的なまでの言語表現の不足であり、思考の量的不足なのだという気がする。不足をこのように認識するやいなや、奇妙なことに、他ならぬこれらの不足によってこそ、鼓舞されるような気がしてくる。これらの不足の深淵に向って、ただなだれ落ちていけばいいのではないか、不足を補填しきれずとも、埋めようとする方向へと崩れていけばいいのではないか。もしそうなら、これからの生は存外、簡単なものかもしれないとも感じる。敵艦を見つけた特攻機のパイロットも、同じようなことを感じたものかもしれない。見つけたものが敵といえるべきものかどうか、問わないでいる場合の話ではあるのだが。
第200号(二〇〇八年十月二日)
勤めから帰宅してみるといくらか時間がとれそうだったので、歩きに出た。昨夜は睡眠時間が四時間もとれず、帰宅時には多少ぼんやりしていたが、盛夏用の極薄のTシャツだけで肌寒い夕方の空気の中に出て歩き出すと、頭も冴え、体調がよくなってくる。
半袖Tシャツ、擦り切れたようなジーンズで急ぎ足で歩いて行く姿は、傍目にはきっと奇妙に見えているだろうと思いながら、ちょっと歩いてもなかなか汗が出てこなくなったのを実感しながら歩き続ける。夏なら、十分も歩けば汗が噴き出すようだったのに、四十分ほど歩き続けて、ようやく汗ばんできた。
毎日のように歩けるわけでもないので、はじめはなかなかペースが上がらない。無理をすると筋を痛めたりするので、楽に歩く。やはり、四十分ぐらい経って、汗が出るようになってからだろうか、ようやくハイペースで歩けるようになった。ウォーキングの指導などを読んでいると、姿勢を正し足を伸ばして歩くのがいいと書いてあったりするが、夏の編集贅言でも触れたように、現実に早く歩こうとすれば、前傾姿勢で前に倒れ込むような感じで、膝を伸ばし切らずに次々と足を前に出していくのがよい。少し上り坂の山道を急いで歩いていくような恰好で平地を行くのが、なんといっても早い。前に倒れ込むような姿勢が、そのまま体を押し出してくれる。倒れないように足は自然に前に出ていくので、疲れも比較的少ないのではないかと思う。
普段は寄らないのだが、今日は途中で、池尻の山陽書店に寄った。ひさしぶりに覗いたので、急ぎながらもすべての本をくまなく見る。めぼしいものは特になかったが、古い日本古典文学大系版の『平安鎌倉私家集』を買っておくことにした。式子内親王集がまるごと収録されていてわずか500円、これは買い得というべきだろう。他に好忠集、和泉式部集、大納言経信集、長秋詠藻(俊成の集)、建礼門院右京大夫集、俊成卿女家集が収録されており、便利という以前に、途方もなく魅力的な歌の集積である。和泉式部などはいくつかの版をすでに持っているが、俊成や俊成女の私家集を手元に置いておけるのは嬉しい。レシートか領収書を、と求めると、名前を書き込まないままの領収書を出してくれた。こういう気の利く古書店も珍しくなった。
並んでいた日本処刑・拷問方法史といった題名の本(正確な名は忘れた)をついでに見ていたら、大槌切りというのがあった。何人もで受刑者を押さえつけて、その頭を大きな槌で木っ端みじんに打ち砕く処刑法だという。斬首や鋸引きなどがずいぶん穏当な方法に見えさえしてくるような凄まじい図解付きだった。胴首切りという、生身の胴体を一刀両断に切断してから、返す刀で首を切断する方法も凄まじいし(当然ながら至難の技で失敗も多く、その失敗のさまの凄まじさが好まれたらしい)、耳鼻削ぎなども堪ったものではないが、大槌切りの衝撃はそれを超えるのではないかと思った。掲載されていたたくさんの処刑方法のいずれも、現実に江戸時代まで採用されていたものだという。斬首という方法が、いかにソフィスティケイトされた人道的な方法だったかということに気づかされる結果となったが、これほど多彩ないたぶり方や殺し方を考案せずにおれないような人間の精神構造というものは、現代社会に溢れる無限の意匠や書籍や映像や音を作り続けてやまない精神構造と、結局のところ、なんら変わるところはないのではないかと感じられてならない。
ところで、昨夜の睡眠時間が減ったのは、ひさしぶりに再読したブレヒトの『三文オペラ』が面白くて、最後まで読み通してしまったからだった。2005年に岩淵達治が改訳したもの(岩波文庫)は、前のものより楽しめるように感じる。以前はそれほど気づかなかったが、セリフの中に社会や人間についてのみごとな裁断や箴言をたくさん盛り込んであるのに感心した。ドイツ語で読んだら没入してしまうような楽しさに違いない。ブレヒトによる上演用のコメントが、また面白かった。ちょっとした彼の注意書きを読んでも、演劇や役者を志していた二十代の頃の情熱の熾火が再燃する。
そういえば、最近しきりに、もう一度役者の道をたどり直すべきではないかと考えがちになる。二十代の半ばで劇作も俳優の道も断念したのは、結局、文学形式のものを自分で書きたいと思ったからだった。たいしたものにはならなかったとしても、もう書いたではないか、とこの頃は思う。もういいではないか、そろそろ戻ってもいいのではないか、と。遅すぎるだろうか。だが、脇役としての独特の味わいの追求はできるのではないか、と感じる。そういうのは一生ものだろうから。しかも、劇もドラマも、脇役によってこそ陰影が出るのだし。
第201号(二〇〇八年十月四日)
アマゾンを利用した際に、アマゾン・シティカードを作っておいた。アマゾンでの買い物の決済以外には使わなかったし、上限額も最低に設定しておいた。持ち歩きもしなかった。が、ポイントがついたり割引があったりして、アマゾンでの買い物の時には少しは得をさせてもらった。数日前、そのアマゾンからメールが来て、シティカードとの提携を中止することになったと告知された。公共料金などの振込みなどをアマゾン・シティカードからするようにしていたら、面倒なことになっただろう。
このアマゾン・シティカードは学生でも取れる安カードだが、本当のシティカード自体は、いわずと知れた高級カードだ。旅行傷害保険1億円、バイヤーズプロテクション500万円が普通のゴールドカードに付いている。ステイタスも高い。そのうちの最高ランクのダイナースカードに至っては、あらゆる場面での無制限の保証がついている。これらのカードのプラチナカードともなれば、世界で大変な待遇を受けられる。
こんなカードにも象徴される世界金融の頂点にあるシティグループは、だが、昨年来の金融危機でかなり危険な状態になっている。2007年9月に32.69ドルだった株価は、今年の夏に8ドルになった。実質的なオーナーは、世界皇帝と呼ばれる93歳のデイヴィッド・ロックフェラー。このロックフェラーが中心となったアメリカ系金融資本は、バーゼルに、いわゆるバーゼル・クラブこと、BIS(国際決済銀行)を設置し、BIS基準(自己資本比率によって銀行信用度の格付けを行う。1990年よりこれを意図的に厳しく日本に適用することで、バブル崩壊は誘発されたともいわれる)を勝手に作って世界の銀行を統制し、国際金融を支配してきた。世界最大の金融グループであるシティの株価が8ドルになり、さらに下落中であるということがなにを意味するかは、かなり明白であるとともに、どこまでも「まさか…」という空想物語のような事態を考えさせる。かつての大恐慌程度では留まらない事態が、これから押し寄せようとしているということなのだが、これが現実にどのような出来事を次々発生させるかを考えていた矢先、アマゾン・シティカードの廃止の知らせが来たので、こんなふうに未曽有の大崩壊が少しずつ出現しつつあるのだな、との感を深くした。クレジットカードの負債のえぐり出しも今、アメリカでは進行中であり、企業間での契約破棄や廃止が相次いでいる。
この数週間は世界の金融の動きを追うのに忙しかった。とてもではないが処理しきれない情報量でもあり、変化の速さでもあって、原理的な部分を見抜くのもなかなか容易でない。が、ひとつだけ確かなのは、アメリカ国民のノーテンキさもさることながら、日本人がかなり事態を甘く見ていることだろう。アメリカへの輸出が減るのでいっそう景気が悪くなるなどという程度のことではなく、日本の金融機関が抱え込んだサブプライム由来の不良債権額の莫大さは、これから至るところで金融機関を揺るがすことになっていくはずである。たとえば、三菱UFJ銀行は、経営危機に陥ったアメリカ二大住宅公社の債権を3兆3千億円買い込んでいた。政府系の農林中金に至っては、5兆5千億円分の債権を買ってしまっている。日本生命が2兆6300億、みずほが1兆2000億、第一生命が9000億などと続く。問題は、この債権の出どころであるアメリカ二大住宅公社のフレディマックとファニーメイが、国営企業のgovernment guaranteed enterpriseでなどなく、民間企業のgovernment supported(sponsored) enterpriseにすぎないという点だ。「公社」という訳語が曲者で、誤解を生んでいる。しかも、アメリカ住宅公社債はアメリカ国債に次ぐ安全な公債、との虚偽の広報も意図的に行われているが、民間企業の社債である以上、企業破綻の際にはこれらは戻ってこない。アメリカ政府が、これらについて保証する発言を仮にしようとも、これから起こっていく無限の破綻と果ての知れない金融溶解(アメリカのニュースは「メルトダウンmeltdown」という表現をはやくから使っている)のなかで、それが守られる可能性は少ない。
そもそも、今回の危機が本格的に始まることになった発端として、7月22日のポールソン財務長官の爆弾発言があった。「すべての世界の金融機関と密接に結びついている機関」である二大住宅公社の、債券や住宅ローン担保証券の発行総額が5兆ドル(約530兆円)に上っており、このうちの1兆5000億ドル(約160兆円)は海外の中央銀行や金融機関が保有しているということを暴露してしまったのだ。彼の発言は、公的資金注入の正当性を示すために行われたものだったのだろうが、これによって、それまで二大住宅公社の債権保持をひた隠しにしてきた海外の金融機関の信用は一気に揺らぐことになってしまった。
海外に散った二大住宅公社の債権のうち、日本には23兆円、中国に40兆円、サウジアラビアに30兆円、イギリス、フランス、ドイツに10兆円ずつほどが渡っているといわれる。日本などは、アメリカ国債等をすでに600兆円以上買い込んでいるのだから、これからアメリカの金融が崩壊していけばどうなるか、想像するまでもない。アメリカは最終的には信頼できるだろうなどと考えるのは甘く、すでに4月時点で、アメリカ証券取引委員会は時価会計の放棄を決定し、有価証券評価に恣意的に下駄を履かせて危機的状況を曖昧化できるようにした。BIS基準そのものの放棄を、自らが国内的に決定したということになる。BIS基準によるかぎり、銀行は自己資本比率を、国際金融業務用には8パーセント、国内業務には4パーセント維持する必要があるが、現在、アメリカ連邦銀行FRB自体の自己資本比率が、すでに4パーセントを切ってしまっている。他の国内銀行はさらにひどく、これを隠蔽するために、アメリカ金融自らが決めて世界を牛耳ってきたBIS基準の自己放棄に至ったということになる。こんなことが、今年の春から一気に連続して起き、現在、いっそう深化した第2ラウンドが進行中なのだ。
緊密に絡まりあった事態についての大小の情報が世界中から流れてき続け、国際金融を専門にしているわけでもない者には整理も処理もしきれない状態になっているのだが、とりあえず来年の今頃の東京の風景を想像すれば、生活費を縮小してかろうじて日々をやりくりしていく人々の往来や、困窮のあまり家に籠って死んでいく人々、街にあふれ出た多くの人々の群れが力なく漂っているというようなことになるのではないかと思う。自動車をはじめとする日本の代表的な製品が、どれほどまでにアメリカと中国(中国の経済発展は、米ドルと米国債の世界的信用にかかっていた)で売れなくなるか。どれだけの数の労働者や技術者やホワイトカラーが、これによってどの程度仕事を失っていくか。来年の風景は、このあたりにかかっているだろう。仕事のペースダウンはあらゆる業種に伝播し、多少なりとも余剰的・娯楽的性質のある商品やサービスの切り捨ては大がかりに行われるに違いない。それらに関わる人々の失業も、輸出品製造業における失業に引き続いて発生する。質の変換を発生させるのはつねに巨大な量的変化なので、社会の各所における量的変化は、政治や社会や価値観や倫理の突然の変貌を招来する可能性もあるだろう。
個人的に思い出されてならないのは、アフガン侵攻とイラク侵略が発生した時、あんな理不尽で不条理な侵略をやらかす国には、かならず「バチが当たる」と思ったこと、また、深く神にそれを願ったことだ。忘れていたが、たしか或る夜、神の声が聞こえてきて、こう繰り返した。「復讐するのは私の仕事。私がそれを行う」。バチは当たった、というべきだろう。東大駒場まで、イラク核施設の不在を証明するスコット・リッターの報告を聞きに出かけた夜のこと(しかし、講堂はすでに超満員で入れなかったが)や、イラク攻撃に反対する詩人たちの朗読会に行ったことが思い出される。ツインタワーを攻撃したわけでもない普通のイラク市民の家族たちの上に爆弾を落とし、買い物に出た少年少女を射殺し、ファルージャでは未だに幾重もの隠蔽がなされている虐殺を平然と行い、それら一連の行為を正義だ正義だ正義だと言い募ってきた国の核心部分に、今、呵責ない「バチが当た」っている。
国連決議を踏み倒してアメリカに従っていった日本にも、もちろん、相応の「バチが当たる」だろう。今回の神の報復の特徴は、どうやら世界的にメルトダウンmeltdownを引き起こすということらしい。日本でも、炉心熔解ということなら、もう、至るところで精神的に、倫理的に、社会機構的に起こっているというべきだろう。こういう時には、物質たちまでもが熔解のしぐさを方々で真似しがちになるものだから、原子力関係や爆発物関係の危険施設に関わる人々は、よくよく注意したほうがいい。これは予言ではなく、ものの倣いということ、大げさにいえば法則ということである。
第202号(二〇〇八年十月七日)
「商業資本主義」→「産業資本主義」→「金融資本主義」という資本主義の変化。金子勝が『閉塞経済―金融資本のゆくえ』(ちくま新書)で用いているような単純化に従って、とりあえずこう考えてみるならば、現在起こっているのは、「金融資本主義」の溶解だというのが、大方の解釈だろう。実体経済に戻ろうとしているという言い方にも接するが、つまりは「産業資本主義」時点まで戻るという話である。
経済学において、言うまでもなく貨幣の無根拠性はありふれたテーマだが、「金融資本主義」の暴走は、そもそもこの貨幣の無根拠性を最高度に発揮させたところに出現したもので、誤った行為というわけでもなく、貪欲さの果ての狂乱状態でもない。人間が貨幣を発明した時点ですでに、金融過熱や金融溶解の芽はしっかりと組み込まれていたのだし、マルクスが『資本論』で展開したように、商品にも同様にこの芽は包含されていた。すべては「貨幣」と「商品」という概念の機能から出来してきている。大航海時代を経、18世紀から現代に至る流れの中で、たまたま好条件が整い、それらの芽が大きく伸び広がったにすぎない。巨視的に長いスパンで考えれば、「貨幣」と「商品」という概念の機能をふたたび研究し直した上で、金融過熱にブレーキをかけるようなシステムを今後の人類は模索していけばよいと思われ、決して「産業資本主義」に戻るべきだという議論に与するべきではないように思う。マルクス研究が、再び、いよいよ重要になってくる所以である。
こうした見方とは別に、国際金融の裏面を覗いた場合として、今回の金融溶解の真の震源は、けっきょくは、BIS(国際決済銀行)を設置してBIS基準で世界の金融を実質的に支配しているロックフェラー家内部の権力闘争である、という話がある。シテイバンクを握っているデイヴィッド・ロックフェラーに、甥のジェイ・ロックフェラーがついに本格的に襲いかかったというのがそれである。デイヴィッドはロックフェラー2世の5男だが、ジェイは1世以来の正統の嫡男で、4世になるべき資格がある。彼から見れば、ロックフェラー家は一時的に傍系によって簒奪されていたにすぎず、これからそれを正そうと考えているということになる。
甥のジェイがゴールドマン・サックスのオーナーであること、ポールソン財務長官もゴールドマン・サックス出身であること、また、三井住友銀行の筆頭株主もジェイ・ロックフェラーであること、いっぽう三菱は、デイヴィッド・ロックフェラーとシティバンクと密接な関係を続けてきていること、さらには、6月の、ロスチャイルド家の所有であるイギリス・バークレイズ銀行への三井住友の出資救済によって、ジェイ・ロックフェラー+三井住友+ジェイコブ・ロスチャイルド男爵という連携が明瞭になったこと等など、多くのパーツを集めて考えあわせていくと、概要としては、ジェイ・ロックフェラーとロスチャイルド家が連携してデイヴィッド・ロックフェラーを倒そうとしているという構図が浮き上がってくる。デイヴィッド側の金融機関が次々と破綻や吸収を蒙っているというのが現在の状況で、もうしばらくすれば勝敗は決することになるのかもしれない。今回の混乱は長引くと見るのが常識的な見方ではあるのだろうが、こうしたお家騒動が真の震源だとすれば、案外、混乱の収束は速いかもしれない。多くの破綻や合併吸収が起こった後で、何事もなかったかのように収まる可能性もありうる。ちなみに、新銀行東京を破綻させた石原慎太郎は、これまでデイヴィッド・ロックフェラーの後ろ盾を得ていたために保身が可能だった。ロックフェラー家のお家騒動に端を発する今回の世界金融の再編の後には、石原慎太郎は身の置き場所を失いかねない。
FRB議長のバーナンキが、じつは、高橋是清と昭和恐慌の研究者だということにも注目しておいてよい。自由主義と個人主義を抑制し、それまで個人が蓄えた資産を国家が収奪したり無価値化して一気に管理国家へ移行し、それによって経済的難局を乗り越えようとするネオ・コーポラティズム手法を、バーナンキはかなり深く研究してきた。これは、私見によれば、9・11以後のアメリカ国内でじつは限定的に実験済みで、世論誘導から経済誘導までかなりの点での成功を収めたといえるが、今回はさらに大々的に正々堂々と適用する可能性がある。これからなにが起こっていくのか、それは昭和恐慌で採られた政策をふり返れば、かなり見通せるかもしれない。
第203号(二〇〇八年十月九日)
また、驚かされた。
会うこともなくなって久しい知り合いから、突然、フランス語文献の不明箇所について教えてほしい、その部分をちょっと翻訳してほしいとの連絡が来た。だれか引き受けてくれる人を紹介してくれてもいい、という。分量と期限をまず教えてほしい、それを見てから判断する、と返信したら、「ありがとうございます」という言葉とともに、原稿のファクスをお送りしておきました、とのメールが返ってきた。「ありがとうございます」?ちょっと待ってくれ。やるなんて、まだ、言ってないんだけど…
帰宅してファクスを見てみると、A4ぎっしりに8枚という分量で、期限は10日ほどで、とか。不明箇所を訳してほしい、ということだったから、せいぜいが10行かそこらかと思っていたら、短めの論文一本にもあたる量を全訳してほしいということらしい。最初の打診と話がまったく違う。受け入れたわけでもないのに、もうこちらがやると思ってもいるらしい。これだけの分量を訳すとなれば、これは知り合いのあいだの“お知恵拝借”で済むことではなく、もう立派な仕事というべきである。相当の時間と労力を費やすことになるのだから、頼むほうとしてはしっかりと報酬を提示してかかるのが常識では? 安く見積もっても、2万円は下らない翻訳料になるだろう。自分が頼むとしたら、どうするだろう。2万円ではギリギリ過ぎて失礼になるから、2万5千円か3万円を提示して、原稿を見せ、これでよければ10日ほどでお願いしたい、と言うと思う。仕事を依頼するのだから、条件をはっきり提示するのが当たり前である。後でなにかお礼をすればいいなどと思いつつ、はじめになにも提示しないというのは最も失礼にあたるし、卑怯でもある。相手の貴重な時間と労力を割いてもらうのだから、受け入れるかどうかを相手が判断しやすいように、全条件を前もって提示しなければいけない。
忙しい日々なので、これだけの分量を訳すのは今回は無理、とけっきょく断った。報酬額も提示してこないような仕事を、無責任に誰かに紹介するわけにもいかない。プロの翻訳業者に頼むのが最良です、安くても2万円以上は払わねばならない仕事なので、その準備をしてあたってください、と書き送った。
はっきりとは答えてこなかったが、こんな程度のことをどうしてしてくれないの、と思っているらしい。はぁ?、翻訳料?、なんで?、といった怪訝な気分でもいるらしい。そんな雰囲気がむこうからは伝わってきた。ちょっと腹が立ちそうになったが、こんなのを相手にしても無駄なだけ。はい、ここで終わり、この件も、この人との付き合いも、と、思念を強制終了することにした。すでに、最初の打診をもらってから、翻訳をすることにした場合の時間のやりくりや労力の見積もりや、文面に注意しながらのメールのやりとりにけっこう時間も頭も使っている。それだけでも損失なのに、だいたい、こんな多量の文書を勝手にファクスしてきて、紙代はこっち持ちなんだけど、どうしてくれるの?…
若い頃なら、こんな時、ガタガタして心理的にもひきずったものだったが、さすがに少しは知恵もついたので、こういう場面では自分の感情も含めて一切をその場で落とす、捨てるというのが最良だとわかるようになった。時間と心的エネルギーを、より価値のあるテーマに向けてサッと舵を切る。これに限る。失ったちょっとのものを取り返そうとして相手に要求するその時間と労力が、いっそうの無駄を生むことになっていきがちなのだ。その場で、そのテーマ自体を、そのテーマの土壌ごと捨ててしまうのが、けっきょくは、いちばん損失を少なくしてくれる。最初の損失を取り戻そうとしないでおくのが、もっとも利益をあげることに通じる場合が多いのだ。いちばん尊ぶべき利益、とはなんだろう?決まっている。時間と、現在から近未来を生きるための心のエネルギーだ。このふたつだけは損なわないようにする。この点では徹底したエコロジストであるべきだし、これ以外のものなど、なにを失おうとも、どうにでも取り返しはつく。
それにしても、こういう人たちが増えた、増えた、増えた。どうしちゃったの、みんな?、と思う。いまの世の中の批判ばかりを馬鹿のひとつ覚えのように続けたくはないのだが、どうも、世の中のふつうの部分を構成しているふつうの人々が、かなりの規模でオカシクなってしまっている気がする。形式的な表だけの付き合いをしたり、世間話をしたり、お世辞を言いあったりしているうちはわからないが、ちょっと踏み込むと歪みや狂いが露呈し、つまらないちっぽけなところでギシギシと齟齬を来すようになる。今回、翻訳を頼んできた人など、十年以上にもわたって、こちらからの手紙や連絡に、おそろしく形式的な空虚な返事をよこすか、なにもよこさないかを続けてきた人だった。そういう程度のことは、この人の性格だと思ってしかたないと諦めていればいいのだが、そんな態度をとってきた人が、突然このような依頼を平然としてくる、してこれる。こんなところに、今のニッポンというものが、まぁ見事に露呈しているっていうことなんだろうなぁ、と、また思わされた。
第204号(二〇〇八年十月十日)
仕事から帰った後、三茶―道玄坂(渋谷)歩き往復を敢行(!)。小さなことながら、45分から1時間かかりがちな片道行程を35分で踏破できた。復路もほぼ同じ時間で消化したが、信号で止まったり、猫をかまったりという予定外のことが起こるので、35分×2+10分ほどが昨日のタイム。
いくらか温度が高めの日だったからか、20分ほど歩くと夏のように汗が出始め、その後はずっと汗だらけだった。HEADというスポーツウェアブランドの長袖シャツを着てみたところ、性能がよくてなかなか快適だった。「吸汗速乾加工」だそうだが、体じゅうから出続けている汗が、シャツの表面には出てこない。ふつうの綿Tシャツのような発汗時の不快感は全くない。とはいえ、「吸汗速乾」というほどの効果かというと、微妙なところ。かなりの速さで乾いていってはいるのだろうが、出てくる汗の薄い滞留がつねにウェアにある(他の衣類に比べれば、それがすばらしく軽微なのは確か)。汗というのは、やはり、なにを着ようとも完全解決には至らないものか。
軽いリュックを背負って歩いている。夏の甚だしい汗で汚れきったうえ、洗濯までしてしまってフニャフニャになったリュックだ。その中に水やスポーツ用ジャージの上着を入れてある。アディダスのクライマライトという素材でできているジャージで、「ボディをドライで快適に保つ素材《クライマライト》。汗は出るそばから外気へ発散、ウェアの中はいつも爽やかです」と説明にあった。なんだか凄そう。実際はどうだか、まだ試していない。ともかく、昨日は出番なし。寒くなってくれば、出番は多くなってくるだろうと思う。
帰宅してから、汗の引かぬうちに、しばらく筋肉運動。腹筋や腕立て伏せをやらねばと思うと、途方もなく面倒くさい気持ちになることがあるが、それを乗り越えるのが大事なのだろう、そう思ってとりかかる。
歩く時間は毎日はとれない。時間がうまくとれて、あいかわらずのスピードでなおも歩けるとわかった時にはうれしい。今日の場合、片道35分というタイムでもわかるが、相当の高速で歩けたことになる。円山町から神泉にかけてや、松見坂から大橋にかけての急坂を、スピードを出して歩き降りるのは愉快だった。急坂を高速で下ると、足腰の至るところに大変な負担がかかる。それをうまくこなしていくというのは、たんに歩いているだけのことなのに楽しいものだ。障害の少ないよい道で、ぐんぐんとスピードが上がっていくのも楽しい。走る練習はしたことがないのでけっして走らないのだが、好調な時には、後ろにいった足をさっと地面から上げて、また前にすばやく出していくので、跳ねて進んでいくのに近づくような場合がある。この時の感覚も楽しい。自分の体だけを使って、走りもせずにこれだけのスピード感と浮遊感が得られるということに、子供のような素朴な喜びを感じてしまう。
第205号(二〇〇八年十月十一日)
フランス語で書く作家にノーベル文学賞を与えるのならば、ル・クレジオよりは先ずクンデラに与えるべきだろうとは思う。クンデラ文学は、現代に生き続けることが、そのまま人生の概念の破綻である他ないということを芳醇に浮かび上がらせ、破綻の更新を続ける悦びに読者を誘う。知的で輪郭のはっきりした虚無のスリリングさに触れさせてくれる点では、クンデラは比類がない。
だが、なるほど、ル・クレジオにはノーベル賞がよく似合う。たった一言でル・クレジオ文学を要約すれば、「地球と人類を未曽有の大混乱と悲惨に陥れたヨーロッパ的なるものに抗して」とでもいうことになるだろうが、植民地時代以来のヨーロッパが産出したあらゆるものの怒涛の中で、個人の神経と意識とがどう生き延びうるかを描き続けてきた。初期ル・クレジオは、先進国内部に生きることの神経的痙攣をアクション・ペインティングのようにぶちまけ続け、そうする中でTERRA AMATA(『愛する大地』)におけるように、ユーモアと軽い悟りと紋切り型と少年小説ふうの試みの混合から絶妙なバランス創出を達成する術を獲得した。中期ル・クレジオではLA GUERRE(『戦争』)やLES GEANTS(『巨人たち』)で初期の痙攣的書法を推し進める一方、VOYAGE DE L`AUTRE COTE(『向こう側への旅』)で、現実世界の文法に目配りしながら20世紀の物語を紡ぐことを超克して、荘子世界に近い融通無碍の物語法に一気に飛んでしまう。ある意味では、彼はこの作品で頂点に達してしまったのではないか。その後、MONDO ET AUTRES HISTOIRES(『モンドとその他の物語』)では急転直下、現代社会での孤独な者たちのそれぞれの危機の瞬間を描く平易な物語に向かうが、ル・クレジオを読み続けてきた読者たちは、彼のエネルギーの衰えを感じさせられる時期だったに違いない。その後のL`INCONNU SUR LA TERRE(『地上の見知らぬ人』…翻訳はあったか?)はル・クレジオ的脱力の利いた佳作だが、もはやかつての彼ではなく、日本ではル・クレジオ離れを加速させたのではないか。翻訳紹介も、この頃にはぐっと遅く、少なくなっていた。
そこへ1980年のDESERT(『砂漠』)が刊行される。サルトルやロラン・バルトの死の年に訪れた新たな風だった。ル・クレジオの決定的変貌を証明した屈指の奇跡的な名作で、ぼくはこれを一読した後も手元から離すことができず、読まない時でさえ、あの太い嵩張る原書をいつもカバンに入れていたのを思い出す(とはいえ、いま見直してみると、たった四十一ページしかないのだが)。謎と超越性を帯びた砂漠の民、動乱と悲惨を生き延びていく娘、小説というより叙事詩に戻ろうとするかのような文体と構想は、フランスの表現世界がアラブやアフリカの匂いと音と色彩を大きく受け入れることになる時点を正確に刻印している、と、いま振り返ると思われてくる(ちなみに、叙事詩は、シャトーブリアンが『ナッチェ(ズ)族』と『殉教者たち』で文学史上記念碑的な失敗を遂げて以来150年ほどお蔵入りになっていた形式で、今後、復活するであろう形式と思われる)。さらに五年後の1985年、LE CHERCHEUR D`OR(『黄金探索者』と訳されているが、『黄金』とか『ゴールド』とか『金を求め続けて』などとしたほうがいいのでは、と思う。ブレーズ・サンドラールの匂いも呼び込めていい)が書かれる。これがDESERTと双璧をなす至上の作品で、ここで彼は、たしか祖父がモデルだったと思うが、歴史の動乱の中で黄金を求めて人生を蕩尽し、紺碧の海と碧空の中のめくるめく虚無へと至った男Alexisの物語を描き出した。
十年後の1995年のLA QUARANTAINE(『検疫期間』)も忘れがたい名作だ。ランボーと邂逅した祖父の逸話の周辺に繁茂していくこの物語は、LE CHERCHEUR D`ORの雰囲気を思い出させるようなところがあり、DESERT以来のル・クレジオの集大成に感じられた。音楽でいえばラフマニノフのような、熟成した末のペシミズムを湛えた濃密な語りが素晴らしいものだったが、しかし、ル・クレジオが自分の方法や口調のくり返しに入ったのをはっきりと示す作品でもあった。
個人的な乱暴な批判を平然と言わせてもらえば、ル・クレジオはこの三作までで終わった、と思う時がある。その後も次々と小説を発表していったが、ぼくの思うに、どれももはやDESERTとLE CHERCHEUR D`ORとLA QUARANTAINEを超えることはなかったし、方法的な挑戦は影を潜めてしまったし、さらにきつく言えば、この二作での展開方法の繰り返しに終始するようになってしまったように見える。確実に深化したのは文体で、叙事詩的とぼくは思うが、その度合いがますます進み、大きな波のうねりに似た語りはすっかり定着して、勇渾といえばずいぶん勇渾なものになった。HAZARD(『偶然』)などは、こうした文体効果が最高度に発揮された作品と思う。ちなみに、菅野昭正氏の訳で集英社からこれが出た時、北海道新聞に書評を頼まれたのでこのあたりのことを書いたが、最近は新聞社がネット上にアップしたので、ぼくのこの時の書評はいまもネットで読める。
とはいえ、そうした文体上の達成とともに、物語展開や起承転結のつけ方は、退屈といえば退屈、またいつものル・クレジオ調かと思わされるような流れに出会うことが増えたように思う。この十年ほどは多少皮肉に、あのル・クレジオも、いかにもノーベル賞向きになってしまった…と感じていたぐらいだった。最愛の作家のひとりについて、こんなことを書くのは気がひける。しかし、ル・クレジオには、いつもそれほど期待し続けてきたし、この十年ほどはそれほどがっかりさせられ続けてきたのだった。今度はどんな変貌を?、今度こそは変貌を?、と思いながら、サン=ジェルマン・デ・プレの行きつけの書店やFNACや時にはシャンゼリゼのヴァージン(パリじゅうの商店が休みになってしまう年末年始、しっかり店を開けていてくれる1ヴァージンは本の虫たちの避難所だった。新年の日々の日中を、何度ここで過ごしたかわからない)で、平積みの新刊をいつも手にとってきた。生涯、一度として同じ形式をくり返さなかった奇跡的なフローベールの苦行実践は、やはり、他の作家たちには見出しがたいことなのだろうか。ル・クレジオには今のところ、どうも見出しづらいように感じるのだ。こういう見方が間違っているかどうか、もう一度読み直してたどり直したいと思うのだが、ル・クレジオはけっきょく、忘れ去ったままにしておいていいわけでもないピエール・ロティの『Aziyadeアズィヤデ』に集約されたようなポスト・ロマン主義的感傷性の完成から、じつは、ほぼ一歩も出ていないのではないかという思いも、いまのぼくにはまだ拭い切れないでいる。
ともあれ、ぼくの1980年代はル・クレジオ一色だった。ル・クレジオとだけつき合い続けた歳月がある。なんといっても、DESERT以降のほぼ全作品と彼に関する手に入るかぎりの雑誌記事や資料をリアルタイムでのめり込んで追い続けてきたし、LA QUARANTAINEまでの最高度の不動の達成が彼にはある。あれらを熟読する過程で、それまで根強くしみ込んでいたバルザックと石川淳の影響をぼくは中和することになんとか成功し、デュラスとフローベールに移っていった。この移行がなければ、シャトーブリアンの『墓のかなたからの回想』の躍動的な文体美には不感症のままだったかもしれないし、それと一生つき合っていこうと思うには至らなかったかもしれない。
1986年頃だろうか、87年頃だろうか、渋谷駅2Fの駅そば屋「二葉」の近くで、ル・クレジオを見かけたと思ったことがあった。あの特色ある顔立ちで、まさしくル・クレジオと見えたが、見まちがいだったかもしれない。世界中を旅してまわっている彼だから、ある日、お忍びで渋谷にいてもおかしくはなかった。あっ、と思っている間に、人ごみのむこうにゆっくりと消えて行ってしまった。まるでDESERTの末尾のように。Comme dans un r?ve, ils disparaissaient.「まるで夢のなかのことのように、消え去っていく彼らだった」。
ノーベル文学賞受賞のル・クレジオの第一声は、Le Figaro(フィガロ)紙のサイトから覗くことができる。下記のアドレスからじかに、けっこう長めの彼のインタヴュー録画に飛べる。
http://www.lefigaro.fr/livres/2008/10/09/03005-20081009ARTFIG00546-le-clezio-prix-nobel-de-litterature-.php
第206号(二〇〇八年十月十二日)
この詩葉メール206号に今まさに記しつつあるこの編集贅言は、そのまま、ここに掲載するトロワテ89号「編集贅言集24」の最終章にあたることになる。作品を後追いのかたちで掲載してきた《詩葉メール便》の時間と、作品制作そのものの時間が、この206号を以て遂に一致することになった。そう大げさなことではないにせよ、この206号は、月蝕や日蝕のような瞬間にあたる。こんな瞬間をもっとも劇的に演出したのは、『百年の孤独』の最終部分でのガルシア・マルケスだった。期せずして、いくらかはあれに近い事態に逢着できた気がして、作者、編集者、配信者としては、少し面白く思っている。
このメール便について、配信について、少し記しておく。
春から、このメール便を終結させる方向で進んできた。理由ははっきりしている。こんなものを配信しても誰も読まないし、文字通り、何にもならないためだ。同人誌の制作・郵送も、メール形式での配信も、なにひとつもたらしてはくれなかった。
唯一、続行理由となりえたのは、自分にとって考えたり書いたりする練習になるということ、自足を破って進み続ける契機になるということだったが、どんな状況下であれ自分が書き続けたり考え続けたりするらしいということは、すでに自分の中では証明されたと思っている。人に褒められたり、共感を寄せられたり、励まされたり、勧められたり、価値を認められたりした場合にのみ書き続けるという甘チャンの観念は、とうに払拭されていた。歴史的に見て、時代を超えて価値(価値とは、さまざまな状況下において、その人為的装置の使用者が生き延びていける可能性を拡張しうるような機能を豊かに持つ、という意味である)を持ちうる書き物というのは、書き手が時代の風潮や価値観の外に追いやられたところで書かれている。したがって、誰にも読まれないところでこそ、まさに書くべきであるのだし、そこからこそようやく書くことが始まるのでもある。こういう考え方に立つ私にとっては、書き続けるかどうか自体は、なんらの問題も構成しない。書くに決まっている。問題になりうるのは、配信を継続すべきかどうかだけだった。
正直なところ、この点については解決していない。止めるべきだとも思わないが、続けるべき理由と必要を、もう私は持ってもいない。どちらに動くにも、無理由の海が広がっている。どうせ誰も読まないのだから、という極端に消極的な理由が、奇妙にも最後の線を切らないでいるばかりなのだ。誰も読まないのだからこそ配信し続けよう、とは、なかなか面白い決定の仕方と見なすべきだろう。自我の現在を厳しく認識するよう迫り続けるこの行為理由のはかなさには、じつに鋭い方法論的解決が達成されている。繊細な凝視なくしては気づかれないこの達成は、これまで言語表現を自分なりに浪費し続けてきて与えられた賜物と思う。気に入っている。
近頃のこのメール便で、自分の書き物を呼ぶのに採用している「作品」という表記についても、記しておきたい。
「作品」という言葉ほど、長いあいだ使用を避け続けてきた言葉は少ない。自作を「作品」と呼ぶのは傲慢であり詐術だと思ってきた。ロラン・バルトやフーコーの文学観革命の後に来た私たちの世代は、いわゆる「作者の死」論などを通過してきているので、「作者」をあらかじめ制度的に認知してしまう文学的アンシャンレジーム側の用語「作品」は、批判や冷笑なしには受け入れづらく感じられた。
私が接した詩歌の世界の人々の多くは、この点ではかなり鈍感で、頻繁に発語される「作品」に唖然とさせられてきた。皮肉なことながら、日本の詩歌の世界の人々には、バルト以降の文芸批評を我が事として読み続けてきた者が少ない。サルトルの『文学とはなにか?』ぐらいまでの言説は多少は共有したのだろうが、それ以降の文学論からは大挙して離れたというのが、日本の詩歌人の現実だった。若干の例外はあり、フランスやアメリカ、フランクフルト学派やロシアフォルマリズムなどの文芸批評論を吸収し続けようという意思をもって進んだ人々もあったが、単なる翻訳模倣のような難解で自己満足的な表現を「詩」として提示するに及んで、自壊を遂げた(「自壊」というのは、彼らにその後、失速や方向修正が認められたからだが、私としては彼らのあれらの表現の時期的価値や必然性を過小評価したくはない。いずれ、大がかりに再評価の試みがなされるべきだと思う)。
このあたりの事情やいちいちの事についての細かな心情を簡明に語るのは不可能だが、ともかくも、詩歌人たちと語りあう時に、あえて用語「作品」を使わないことで、私は彼らの文学観と対峙し続けたとは言える。そういう期間は二十年以上に及んだ。なぜ私が簡単に歌集や詩集を纏めないのかも、端的に言えば「作品」をめぐる概念上の闘争を理由とする。他人が使う場合にのみ用語「作品」は使用可能だが、書いた者自身は究極までこれを使用できないと考え続けたところに、私の文芸上の半生があった。
こうした経緯があったにもかかわらず、自分の書き物を「作品」と呼ぶようになったのは、バルトやフーコー周辺の「作者の死」論の虚偽を考え直す必要を感じているためだ。現実に「作者」はいるではないか?(「作者」あるいは「編者」が、自らの手が編んだ「テキスト」によってつねに大規模に決壊されているにしても)。私がたとえばロラン・バルトの一冊を書架から出してくる。それだけで、「作者」(「テキスト」のある瞬間像の「作者」)の存在は証明されているではないか?(その本の水は、バルトという川から溢れて氾濫しており、バルトという川とはなはだしくズレた形状を取り続けているにせよ。また、私にとっては、「作者」は、単語書付け作業や読解作業の一瞬一瞬に無数に存在しうる、その時点時点での全体性そのものを指す)。用語「作品」を用語「テキスト」に言い換えたところで、もともと用語「テキスト」が持つ全性質が用語「作品」にはすべて含有されていた以上(20世紀の批評家たちは、戦略上の理由から用語「作品」の意味範囲を狭めた上で攻撃していた。現代の我々が特に批判しなければいけないのは、この文学戦略上の虚偽である)、二十世紀の束の間の文芸革命はいまや洗い直されて、場合によっては清算されるべきではないのか。そればかりか、いまや、いかに文学の科学を根絶するか、その不可能性を明瞭にさせて、文学の反学性をこそ顕わにし、ふたたび目茶苦茶な言表の場として、とてもではないが学者の手になど負えず論の立てようもない猥雑な混乱し切った言語場を拓くべきではないのか… このようなことをしきりに考えるに至ったためだ。そのために、とりあえずの目印としての境界を示すために「作品」という用語が使われてもよい。たとえば「ゾーン」や「域」や「地帯」などと呼ばれてもかまわないのだが、はじめから「とりあえず」のものとして使用され、意味も確定されずに概念化され切らない語として使われるのならば、なんら問題はないと思われるのだ。
ル・クレジオに関連したきのう十月十一日の編集贅言には、一か所、書き間違いがあった。年末年始のパリで開いている書店に触れた個所で、「パリじゅうの商店が休みになってしまう年末年始、しっかり店を開けていてくれるFNACは本の虫たちの避難所だった。新年の日々の日中を、何度ここで過ごしたかわからない」と書いたが、これはFNACではなく、ヴァージンの間違い。元日、手持ち無沙汰で本屋にでも行くしかないという気持ちになった時、FNACが開いておらず何度かがっかりさせられた。シャンゼリゼのヴァージンはやっていると聞いて訪れて以来、閉店時まで片っぱしから本を見てまわるというのを飽きもせず何日もくり返したりして、よく時間を過ごしたものだった。